
深田晶恵
長年住宅ローンの相談を受け続けているファイナンシャルプランナー(FP)として、「絶対やってはいけないこと」をアドバイスしてきた。多くの人の脳内に「いいこと」だと刷り込まれていて、伝えると相談者が100%驚く、たった一つの意外なことをお伝えする。

第196回
高齢の親が病気などで入院したときにお金がいくらかかるのか、心配な人は多いだろう。頼りがいのある子どもになるために知っておくべきことはたった一つ、「実際にいくら必要なのか」だ。費用を抑えてくれる非常にありがたい制度があるので、一覧表を使いながら詳しく解説したい。
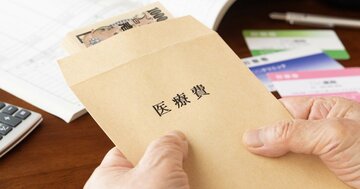
第195回
ファイナンシャルプランナー(FP)である著者のところへ最近、40~50代でのマイホーム購入や買い替えの相談が続いた。実は、40~50代ならではの「落とし穴」にはまってしまう人は少なくない。それも、年収が1000万円を超えるような高年収の会社員の人ほど危ういのだ。「よくあるケース」を基に三つの落とし穴をご紹介する。

第194回
最近取り沙汰されている「住宅ローン金利の上昇」が現実となったとき、変動金利で借りている人には何が起こるのか?実は、金利が急上昇してもすぐには家計に痛みは跳ね返らない。しかしそこには、“時限爆弾”のように時間差で突然の家計破綻に追い込む、「真の恐怖」が潜んでいる。

第193回
「年末調整シーズン」真っ盛りの今、年末調整の「よくあるミスと勘違い」について注意喚起をしたい。今回は3つのケースをご紹介する。併せて、税金を払い過ぎて損をしないように、どう対応すべきかのアドバイスもお届けする。

第192回
「住宅ローンを組んだら、とにかく繰り上げ返済すべき」と考える人はとても多い。「繰り上げ返済呪縛」と言ってもいいくらいだ。しかし実は、「繰り上げ返済をしてもいい人」はとても少ない。「してはダメな人」の三つの条件を紹介しながら、その理由をお伝えしたい。

第191回
法改正があり、10月からパートタイマーなどを対象に「厚生年金・健康保険の適用拡大」が施行された。これに関連して、ファイナンシャルプランナー(FP)である筆者はパートタイマー向けに多くのセミナーを実施した。その場で寄せられた「よくある五つの疑問」を取り上げ、回答していきたい。

第190回
10月に施行される法改正で、いわゆる「パート収入の壁」に影響が生じる。そこで、今回の法改正を機に絶対知っておきたい「壁」に関する3大ポイントについてまとめた。「パート収入6つの壁」の一覧表や、働き損と働き得の分岐点を示したグラフなどの図解を交えて、複雑な制度を分かりやすくお伝えする。

第189回
みなさんはマイナンバーカードを申請して受け取っただろうか?今ならマイナポイントが1人当たり2万円分ももらえるチャンスだ。それに加えてファイナンシャルプランナー(FP)として申請をお勧めしたい理由があと二つある。マイナポイントのお勧め申請方法と併せて詳細をお伝えしたい。

第188回
金利が高い時代に契約した個人年金は、今では考えられないほど高い予定利率が約束されている。この「お宝個人年金」のお得度を搾り尽くす裏ワザが二つある。意外と知られていない受給額アップの手法をお伝えしたい。

第187回
外国では賃金が上がっているのに、日本はこの20年間、賃金が上がっていない――。そんなグラフをニュースで目にした人は多いだろう。何とも悲しくなる話だが、それよりも衝撃的な事実がある。実は、日本のサラリーマンの収入は「手取りベース」で見ると、横ばいどころかガタ落ちしているのだ。手取り年収を試算したグラフを見てほしい。

第186回
節約術の王道といえば、携帯電話料金の見直しだ。しかし、これを面倒に感じる人は多い。何を隠そう、私も何年もの間そうだった。ただ、「ファイナンシャルプランナー(FP)としてそれではいけない」と一念発起して、自分なりのアドバイス方法を見つけた。その「早分かり・カンタン見直し術」をご紹介したい。

第185回
日本銀行の黒田東彦総裁が、「家計の値上げ許容度が高まっている」とした発言について釈明に追い込まれた。それほど値上げラッシュに対する人々の不満や不安が高まっている。そこでファイナンシャルプランナー(FP)として、値上げラッシュを乗り切るための「三つの家計防衛術」をお伝えしたい。キーワードは「見直し・見える化・振り返り」だ。
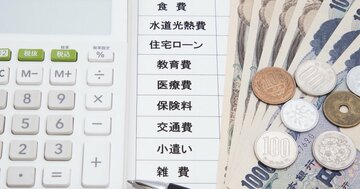
第184回
マンションの価格高騰で住宅ローンの「借り過ぎリスク」が高まっている。住宅ローンの「変動金利×35年返済」マジックが、お金持ちではない人でも6000万~8000万円の高額マンションを買える気にさせているからだ。しかし、住宅ローンを「借りられる」ことと「返せる」ことはイコールではない。そのリスクを十分に認識した上での判断が必須だ。

第183回
定年退職すると突然、自分で健康保険を選ばなくてはいけなくなる。しかも、選び方によって支払う保険料や受けられる給付の内容が変わる「究極の選択」だ。今回は三つの選択肢の中で自分にとってお得な健康保険を選ぶためのポイントを解説する。

第182回
年金の受給開始時期を遅らせる場合、「さかのぼって一括で受け取る」という選択肢もある。以前までその一括受給も選択肢の一つと考えていた筆者だが、このたび考えを変えた。一括受給をしたことで税務署から延滞税の支払いを求められた人がいたのだ。しかもそれを不服として裁判を起こし、敗訴していた。いったい何が起きたのかを解説し、併せて一括受給における注意点も確認してみよう。
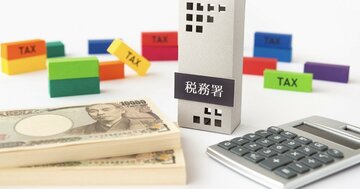
第181回
年金の話題で「繰り下げ受給」は人気テーマの一つ。4月から75歳まで繰り下げの上限年齢が引き上げられたこともあり、例年以上に話題沸騰中だ。しかし、誰でも年金の繰り下げ受給をした方がいいわけではない。「向いている人」と「向いていない人」がいるので、試算をベースに解説しよう。

民間保険は、事故や病気、災害などが起こったときの経済的リスクに備えるために入るものです。「心配だから」とすべての保険に入ると、保険料負担が重くなります。「要る保険」と「要らない保険」を知りましょう。

退職金を手にすると、それまで資産運用に興味がなかった人も「少しでも増やしたい」と思うようになります。気持ちが焦って失敗しないように注意すべきポイントを見てみましょう。

住宅ローンを借りたときには「定年以降もローンが残りそうだけれど、退職金で一括返済すればいいかな」と思っていても、イザ定年を迎えると、一括で返すべきか、このまま返済し続けるか迷いが出てくるものです。見直しのコツを見てみましょう。
