林 總
第31回
オリエンタルランドの財務レバレッジが1.3倍って意外と低いですよね?
貸借対照表を分析する場合は、財務レバレッジに注目することが重要だ。財務レバレッジとは、自己資本に対して何倍の資本を運用したかを示す指標。一流企業の多くは財務レバレッジを巧みに活用して経営を拡大している。

第30回
固定資産は、なぜ自己資本と固定負債以下にしなくてはならないのですか?
会社の長期的な安全性を見る指標に固定長期適合率がある。固定資産と自己資本と固定負債のバランスを見る指標だ。固定長期適合率は、なぜ100%以上ではダメなのか?

第29回
会社の長期的な安全性は、どうやって、判断するのですか?
会社の財務的な安全性には、短期的な安全性と長期的な安全性の2つがある。長期的な安全性を見るには、固定資産と固定負債と自己資本のバランスを見ることがカギになる。

第28回
先生、流動比率を鵜呑みにするのは危険だというのは、どういう意味ですか?
短期的安全性を見る指標のひとつが流動比率だが、一概にこれが高ければ安全というわけでもない。鵜呑みにするのは危険だ。その理由とはどういうことか?

第27回
バランスシートからわかる会社の安全性って、どういうことでしょうか?
バランスシート(貸借対照表)とは、決算日現在のスナップショット(静止画)を表す。バランスシートからわかることは、第一に会社の安全性。企業の財務上の支払能力がどの程度あるかということ。短期的安全性を見る指標に流動比率がある。

第26回
武田薬品工業は、なぜ、売上高の3年分以上の現金を払って、外国の製薬会社を買収したのか?
貸借対照表の資産の部には、有形固定資産と無形固定資産があり、無形固定資産には「のれん」と言われるその会社の信用力なども含まれる。無形固定資産は、見えない現金製造機と言えるが、さらに強力な現金製造機は、目に見えないだけじゃなく貸借対照表にも載らないという…。一体、それって何なのか?

第25回
先生、貸借対照表は決算日のお金の状態を写したスナップショットってどういう意味ですか?
バランスシートの右側で調達したお金は、バランスシートの左側の「お金のダム」「ビジネスプロセス」「現金製造機」の3つの部屋でそれぞれ運用される。バランスシートが表現しているのは、お金の流れではなく、お金が姿を変えた商品や売掛金、固定資産などのスナップショットだ。

第24回
先生、自己資本と他人資本って、一体何がちがうのですか?
貸借対照表の右側(貸方)は、負債と純資産に分かれている。負債は他人資本、純資産は自己資本という。資金の調達元である自己資本と他人資本のちがいを知ろう。
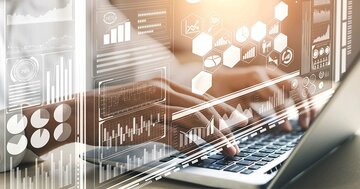
第23回
先生、貸借対照表は会社の財政状態を表しているってどういうことですか?
前回までで貸借対照表の左側、資産の話は終わり。今回からは、貸借対照表の右側。負債と純資産について解説する。これらがどういうものなのかを見ていこう。

第22回
林先生、貸借対照表の左側は3つの部屋に分かれているって、どういうことですか?
貸借対照表(BS)をものにするコツは、細かな会計ルールに縛られるのではなく、全体像を大きくとらえることです。BSの左側の資産とは、どのような構造になっているのか?

第21回
先生、内部留保って、会社がこっそり隠している秘密資金のことですか?
世間では、利益剰余金を「内部留保」と呼んでいる。そして、内部留保が増えると、たとえば、ボーナスとしてもっと従業員に還元するべきだという声が大きくなる。果たして、この主張は本当に正しいのだろうか?

第20回
先生、貸借対照表は、なぜ左右がバランスするのですか?
貸借対照表は英語でバランスシート。バランスとは天秤のことだが、なぜそう呼ばれるのか? それは、左右の金額が天秤のお皿のように均衡しているから。では、なぜ左右が均衡するのか? そのメカニズムとは。

第19回
貸借対照表の右側の他人資本って、買掛金ってなんのことですか?
貸借対照表(BS)の左側は資産で、右側は負債(他人資本)と純資産(自己資本)からなっている。貸借対照表の右側では、資金の調達先(出所)がわかる。資金の調達先は全部で4つあるが、それはどれとどれのことだろうか?

第18回
貸借対照表は2つの箱からできているって、どういうことですか?
損益計算書の説明は前回で終わり。今回から貸借対照表の解説に入ります。貸借対照表の構造がどのようになっているのか? 貸借対照表を攻略するコツは、全体を大きくとらえること。

第17回
税引き後当期純利益は、お金ではないってどういうこと?
損益計算書(PL)の最後に載っているのが、税引き後当期純利益だ。この税引き後当期純利益は、会社が今期に得た利益の金額を表しているが、それはお金ではない。なら一体何を表しているのか?

第16回
トヨタと日産の稼ぐ力のちがいは、決算書のここを見れば一発でわかる!
日本を代表する自動車メーカーのトヨタと日産。しかし、2社の損益計算書を見比べみると、企業としての強さのちがいがあることが一目でわかる箇所がある。さて、それはどこを見ればわかるのか?

第15回
その会社の商品力、新しい価値を生み出す力は、損益計算書を見ればわかるって、本当?
損益計算書には、売上総利益、営業利益、経常利益、税引き前当期純利益、税引き後当期純利益の5つの利益がある。では、その会社の儲けの原動力となる商品力、新しい価値を生み出す力は、損益計算書の一体どこを見ればわかるのだろうか? 林教授からカノンへのレクチャーは続く。

第14回
減価償却は会計が社会科学に貢献した最大の成果ってどういう意味?
会計を知るうえで知っておくべき特殊な費用。それが減価償却費。減価償却費は、19世紀半ば巨額な設備投資をする鉄道会社により発明された。その理由は、期間の業績を正しく算定するため。減価償却は会計が社会科学に貢献した最大の成果とも言える。

第13回
会計は価値の増加が確定したタイミングを重視する
会計は価値の総額が確定したタイミングを重視する。収益-費用=利益なので、どの会計期間の売上(収益)とするか、費用とするかで利益の額は変わってくるからだ。これを会計監査では、カットオフ(期間帰属:当該会計期間を区切ること)という。

第12回
コストの90%は、業績を生まない90%から発生する。業績とコストとは関係がない
損益計算書の利益とは、売上高から費用を引いたその差額のこと。これは言い換えると、期間収益(価値の増加)-期間費用(価値の消費)=期間利益(生成した価値)となる。利益とは、その期間に生成された価値の大きさを表しているのであり、同額のお金が増えたということではない。
