
安藤広大
「リーダーにふさわしいかどうか」を試す、たった1つの質問
【シリーズ累計117万部を突破】「あなたはリーダーにふさわしいか?」。そう語るのは、これまで4000社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、注目のマネジメントスキルを解説する。

課長止まりで終わらない会社員がやっている「たった1つのこと」とは?
【シリーズ累計117万部を突破】「課長止まりで終わらない会社員には、やっていることがある」。そう語るのは、これまで4000社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、注目のマネジメントスキルを解説する。

「出世か、万年ヒラ社員か?」会社員人生の分岐点となる「ある瞬間」とは?
【シリーズ累計117万部を突破】「出世か、万年ヒラ社員か。会社員人生の分岐点となる瞬間がある」。そう語るのは、これまで4000社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、マネジメントスキルを解説する。

絶対に相手にしてはいけない「自社の悪口を言う中堅社員」の特徴
【シリーズ累計117万部を突破】「自社の悪口を言う中堅社員は絶対に相手にしてはいけない」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、マネジメントのポイントを解説する。

【それって寄り添い疲れ?】「部下や後輩に寄り添いすぎて疲弊している…」→組織マネジメントのプロが教える“驚きの解決法”とは?
「部下や後輩に寄り添いすぎて疲弊している。もはや『寄り添い疲れ』だ!」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、組織マネジメントのプロが教える“驚きの解決法”を解説する。

【9割の人ができない!】あなたは自分の働いている会社の「企業理念」が言えますか?
「9割の人は自分の働いている会社の企業理念が言えない」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」になるためのマネジメント方法を解説する。

「努力賞を与えるような会社に絶対に入社してはいけない」その理由とは?
「努力賞を与えるような会社に、絶対に入ってはいけない」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」になるためのマネジメント方法を解説する。
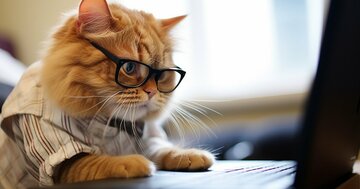
「管理職を任せられるかどうか」を見極める3つの質問
「人を育てる側にまわるか、自分がプレーヤーでいるか。それを見極める3つの質問をしよう」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」になるためのマネジメント方法を解説する。

「超できるリーダー」が無意識にやっている、効果抜群の指導方法とは?
「できるリーダーが無意識にやっている、効果抜群の指導方法がある」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、できるリーダーが無意識にやっている効果抜群の指導方法を解説する。
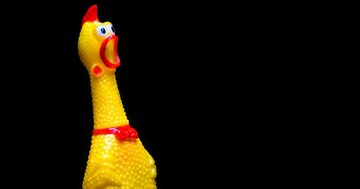
相手にしてはいけない「無能な管理職」に降格人事を突きつけるべき、驚きの理由
「降格の人事は有効である」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」になるためのマネジメント方法を解説する。

相手にしてはいけない「意識が高いだけで全然伸びない若手」のたった1つの特徴
「意識が高いだけで全然伸びない若手には特徴がある」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」のマネジメント方法を解説する。

「人の上に立つ人」が仕事中に考え続けている、たった1つのこと
「人の上に立つ人が仕事中に考え続けるべき、たった1つのことがある」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、マネジメントのために重要な概念について解説する。

相手にしてはいけない「超絶無能な管理職」が共通してやっていること
「相手にしてはいけない超絶無能な管理職には、共通してやっていることがある」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」になるためのマネジメント方法を解説する。

なぜ「私は私」と思い込む人が会社組織で没落していくのか?
「『私は私』と思い込む人は会社組織で没落していきます」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」がやるべき指導方法を解説する。

「なぜアイツが先に出世するんだ!」同僚と比べてしまう人の正しい心理とは?
「同僚と比べてしまうのは、正しい心理です」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」がやるべき指導方法を解説する。

あなたが「できるリーダーかどうか」を試す、3つの質問
「あなたが『できるリーダーかどうか』を試す、3つの質問をしよう」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」か「無能な上司」かを見極める、たった1つの方法を解説する。

「60歳を過ぎても精力的に働ける人」のたった1つの特徴
「60歳を過ぎても精力的に働ける人には、1つの特徴がある」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、人が成長し続けていくための考え方を解説する。

「できる上司」か「無能な上司」かを見極める、たった1つの方法
「優秀な上司か、無能な上司かは、部下ができなかったときの指導にあらわれる」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「できる上司」か「無能な上司」かを見極める、たった1つの方法を解説する。

「みるみる成長するか、伸び悩むか」20代で決定的な差が開く違いとは?
「転勤を受け入れた人と拒んだ人。20代で決定的な差が開く」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、会社員人生でどんどん成長していくための方法を解説する。

知っているだけで部下がドンドン成長する「たった1つの概念」とは何か?
「上司と部下に『ちょうどいい距離感』を生み出す概念がある」。そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、上司と部下に『ちょうどいい距離感』を生み出す指導方法を解説する。
