
後藤謙次
岸田の宏池会解散の決断は、自民党の派閥秩序を大きく揺さぶった。麻生や幹事長の茂木敏充の了解を得ることなく実行した「総理のクーデター」といってもよかった。岸田の解散表明のインパクトは絶大だった。

派閥主催の政治資金パーティーを巡る裏金問題で大きく揺れる自民党に対する国民の目は極めて厳しく、共同通信が実施した直近の世論調査でも、約87%が政治資金規正法の改正による厳格化や厳罰化を求めている。ところが首相の岸田文雄の肝いりで発足した「政治刷新本部」は迷走したまま。自民党の若手議員からも疑問の声が上がった。

「能登半島地震、JAL機炎上、安倍派衆院議員逮捕」──。2024年は松が取れないうちに1年分の重大ニュースの続発で明けた。首相の岸田文雄は地震発生から約1時間後に首相官邸に入り、その日のうちに非常災害対策本部を設置して自ら本部長に就任した。内閣支持率が低迷したまま越年した岸田にとって、令和6年能登半島地震への対応は政権の命運を左右する。

2023年12月19日午前10時過ぎ、東京・平河町の自民党安倍派と二階派の事務所が同時に東京地検特捜部の家宅捜索を受けた。容疑は自民党派閥が主催した政治資金パーティーを巡る政治資金規正法違反。安倍派の疑惑が報じられた当初、首相の岸田文雄は「報道だけで人事に手を付けることはしない」と周辺に語っていたが、その後一気に人事を断行した。

#30
自民党派閥の政治資金パーティー券を巡る「裏金」疑惑で危機に瀕する岸田政権。特集『総予測2024』の本稿では、自民党派閥の行方や「ポスト岸田」の顔触れ、さらに野党の動向なども踏まえて、「ダイヤモンド・オンライン」の人気連載「永田町ライヴ!」の特別編として、政治コラムニストの後藤謙次が混迷必至の2024年政局を読み解く。
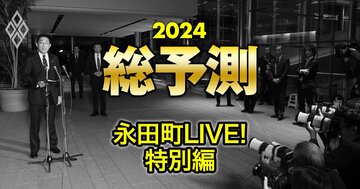
自民党のガバナンスは大丈夫なのか――。自民党の派閥のパーティーを巡る問題は拡大する一方だ。ところが、12月4日に開かれた役員会はわずか10分間。岸田から新たな指示はなく、記者会見した茂木からは事態解明に向けた決意は伝わってこなかった。

政治資金パーティーの政治資金収支報告書の過少記載が明らかになったのは、昨年分まで含めると自民党の6派閥全部と谷垣グループまで全ての派閥とグループ。いわば自民党全体のスキャンダルといっていい。立憲民主党の元首相、野田佳彦は11月22日の衆院予算委員会で首相の岸田文雄を厳しく追及した。

創価学会名誉会長の池田大作が11月15日、老衰のため死去した。首相の岸田文雄が日程をやりくりして池田の弔問に足を運んだことでも、公明党における池田の存在感がいかに大きかったかを物語った。「池田の死」は日本の政治全体の地殻変動を呼び込む可能性がある。

11月に入って政治家の訃報が相次いだ。往年の議員が次々と鬼籍に入る中で、首相の岸田文雄を取り巻く長老政治家たちは衰えるどころかむしろ活発な動きを見せる。
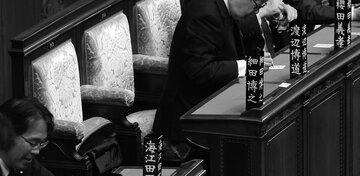
岸田内閣の支持率は今年5月の先進7カ国首脳会議で持ち直して以降は下り坂のまま、発足以来最低の28.3%になった。さらに見逃せないのが自民党の支持率も下降線に入りつつあることだ。こうなると、「次のリーダーは誰か」に光を当て始める。共同通信も「次の総裁にふさわしいのは誰か」を聞いている。

参議院自民党幹事長、世耕弘成の代表質問の波紋がなお収まらない。その光景は長い国会の歴史の中でもほとんど例がないかもしれない。政権与党の大幹部が現職首相の批判を展開したからだ。

ネット上では岸田をやゆする「増税メガネ」という言葉が飛び交う。その払拭もあって岸田が所得税減税にこだわったのかもしれないが、所信表明演説では所得税減税について具体的な言及はなし。しかし、実態は先へ先へと進んでいる。このチグハグ感が今後も尾を引く可能性は否定できない。

「発足以来過去最低」の内閣支持率は、岸田が打ち出す政策が国民の胸に響いていないことを浮き彫りにしている。「先送りできない課題に一つ一つ取り組んでいきたい」と岸田は語るが、政権浮揚にはそれしか選択肢はない。中でも先送りできない最優先の課題に北朝鮮による拉致問題がある。

9月の内閣改造・自民党役員人事を経て取り沙汰された衆議院の「晩秋解散」説は急速に消えつつある。頼みの内閣支持率は、底を打ったかもしれないが上昇に転じる気配はなく、むしろ政権に負荷がかかる問題が次々と押し寄せる。中でも物価高の家計への直撃は深刻度を増すばかりだ。

東京都知事の小池百合子が思わぬピンチに直面している。小池がゴーサインを出した東京・明治神宮外苑地区の再開発を巡って反対の声が押し寄せているからだ。

「95点はあげてもいいんじゃないか」。こう語ったのは元首相の森喜朗。首相の岸田文雄が行った内閣改造と自民党役員人事への評価である。来年の総裁選を見据え、各派の状況に応じて周到に手を打ったことは間違いないが、各メディアが実施した世論調査でも人事刷新による政権浮揚の効果は限定的だった。
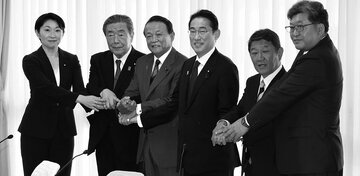
政治家同士の思惑がこれほど激しく交錯した葬儀は珍しかった。8月29日午後、東京・芝公園の東京プリンスホテルで営まれた、「参院のドン」と呼ばれた元自民党参院議員会長、青木幹雄の「お別れの会」のことだ。この日のハイライトは友人代表としてマイクに向かった森だった。

東京電力福島第一原発の「処理水」の海洋放出を巡って中国が激しく反発し、外交問題になりつつある。中国の反発はある程度は想定されたが、「これほど強く出てくるとは思わなかった」というのが日本側の受け止めだった。しかし、日本政府は今も強気だ。「中国には二つの誤算があったのではないか」と日本政府関係者は指摘する。

2021年10月、首相に就任した岸田文雄は福島県の東京電力福島第1原発を訪れ、保管中の大量の処理水について海洋放出を急ぐ意向を強調した。それから1年10カ月。岸田は最後の断を下した。政府の説明が「不十分」なまま、処理水の放出は8月24日に実施することになった。

元首相の安倍晋三が凶弾に倒れてから1年以上にわたり会長不在で混迷を続けている自民党安倍派の後継体制の輪郭がようやく見えてきた。派内に「常任幹事会」を新設し、安倍派会長代理で元文部科学相の塩谷立をその座長とする集団指導体制を導入する案だ。ただし、派内には不満、反発が根強く存在する。
