大矢博之
#9
新型コロナウイルスの感染拡大で多くの企業が打撃を受け、倒産事情も激変した。そこで上場企業3787社の「倒産危険度(Zスコア)」を総点検。リスクの高い493社をあぶり出した。倒産危険度ランキングのワースト401~493位を紹介する。
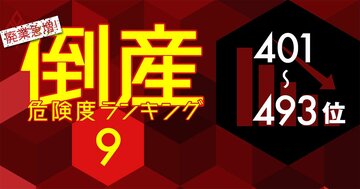
#8
コロナ禍で市場環境が激変した13業界について、それぞれ倒産危険度ランキングを作成した。今回は自動車関連業界を取り上げる。26社が“危険水域”に入った。

#7
新型コロナウイルスの感染拡大で多くの企業が打撃を受け、倒産事情も激変した。そこで上場企業3787社の「倒産危険度(Zスコア)」を総点検。リスクの高い493社をあぶり出した。倒産危険度ランキングのワースト301~400位を紹介する。大手コンビニもランク入りした。

#5
新型コロナウイルスの感染拡大で多くの企業が打撃を受け、倒産事情も激変した。そこで上場企業3787社の「倒産危険度(Zスコア)」を総点検。リスクの高い493社をあぶり出した。倒産危険度ランキングのワースト201~300位を紹介する。絶好調に転じた海運3社のうち1社がランク入りした。

#3
新型コロナウイルスの感染拡大で多くの企業が打撃を受け、倒産事情も激変した。そこで上場企業3787社の「倒産危険度(Zスコア)」を総点検。リスクの高い493社をあぶり出した。倒産危険度ランキングのワースト101~200位を紹介する。

#1
新型コロナウイルスの感染拡大で多くの企業が打撃を受け、倒産事情も激変した。そこで上場企業3787社の「倒産危険度(Zスコア)」を総点検。リスクの高い493社をあぶり出した。倒産危険度ランキングのワースト100を紹介する。

#10
コロナ禍でデジタルシフトが加速したことで、GAFAと呼ばれる米IT大手の業績が好調だ。荒稼ぎするGAFAは、新たな収益の柱の育成に余念がない。GAFAの決算書から見えてきた新規事業の実力を検証する。

#6
量子コンピューターのクラウド公開をきっかけに興味を持ち、「量子星占い」という自作アプリを開発したエンジニアが、東京大学の量子コンピューター研究室の技官に転身した。本人の意志があれば、誰でも量子エリートに成り上がれる時代が到来した。
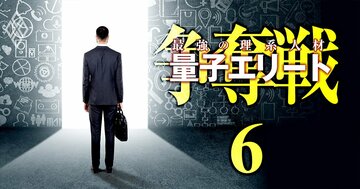
#5
実用化が近いのは電池、素材、医薬品――。自動車業界や化学業界がこんな期待を寄せるのは、複雑で既存のコンピューターでは計算し切れない原子の振る舞いを、量子コンピューターならば計算できるかもしれないからだ。
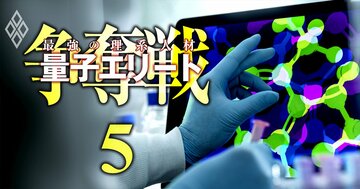
#4
金融3メガの最後の1社がついに動きだした。三井住友フィナンシャルグループがグループ総出で量子人材育成に乗り出す。JPモルガン、ゴールドマン・サックスなどの海外勢や、IBM・慶應義塾大学と組んで先行して活用法を模索する三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループに追い付けるか。

#3
量子コンピューターをクラウド経由で利用できるサービスを、海外のIT大手が強化している。狙うのは自陣営への人材の囲い込み。さながらパソコン黎明期のウィンドウズとマッキントッシュの覇権争いのような状況で、海外勢が利活用の主導権を握り始めた。

#2
希少な量子エリートの獲得競争が激化している。海外では2700万円を超す高額の年収を提示するケースも出始めた。新たな理系人材の受け皿に乏しい日本企業。AI人材をGAFAなどの海外企業に奪われた二の舞いを演じかねない状況に陥っている。

#1
オールジャパンで量子技術イノベーション立国を目指す――。トヨタ自動車、東芝、NTTなど日本を代表する大企業が、量子コンピューターの活用に向けて集結した。産業界が“巨大護送船団”方式で動きだした背景には、先行する海外勢への強い危機感がある。
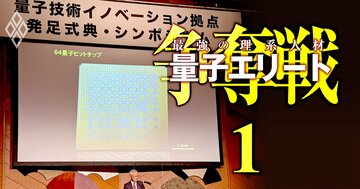
予告
最強の理系人材「量子エリート」争奪戦が激化!“夢の計算機”を巡る企業勢力図
量子コンピューターの急速な発展により実用化の兆しが見えてきたことで、企業が続々と集結している。既存のコンピューターとは異なる仕組みで計算するため、飛躍的な性能向上が期待されている“夢の計算機”。もちろんそれを扱う難易度は最高峰で、今や最強の理系人材となった「量子エリート」を自陣に取り込むための勢力争いが激化している。

コロナ後「K字経済」の実態、世界各国間でも国内企業間でも危険なほどの差が開く!
新型コロナウイルスの感染拡大に翻弄された2020年。多くの企業は大打撃を受け、戦慄の決算発表が迫っている。今回の決算を象徴する言葉は「K字」。コロナ禍からの回復は一律ではなく、回復できる企業と落ち込む企業へと二極化するK字を描くというのだ。明暗を分けるポイントは何か。戦慄のK字決算をダイヤモンド編集部の総力取材で先取りする。

#9
新型コロナウイルスに関連する倒産が全国で1300件を超えた。とりわけ2021年3月は180件を超え、単月で最も多い水準になっている。なぜここにきてコロナ倒産が急増しているのか。コロナ倒産の最新動向を追った。
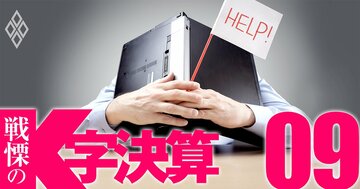
#8
1度目の緊急事態宣言が発令された2020年春、企業の業績は大きく落ち込んだ。そこからの回復度合いや資金繰りなどは企業によって格差がある。K字経済の世界で生き残る企業はどこか。上場500社の“明暗”をランキングした。

#5
蒸発した消費、なくなった仕事……。コロナショックからの回復度合いには地域によって格差があり、また課題も地域ごとに異なる。消費、雇用、地価の三つの要素を基に全国10エリア別のK字型経済からの回復事情を追った。
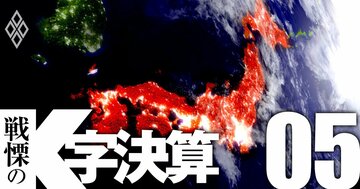
#2
コロナショックで消費環境は激変した。旅行や外食が落ち込む一方でEコマースは絶好調と、業種によって格差が生じている。特集『戦慄のK字決算』(全17回)の#2では、100万人分の消費データを基に、小売りや外食、自動車、アパレルなど主要30業種の回復度合いを分析した。
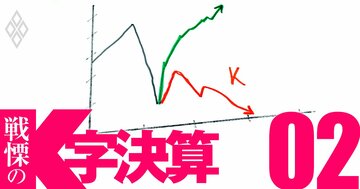
#8
Go Toイートキャンペーンや時短営業への協力金など、飲食店を救うべくさまざまな支援策が講じられている。しかし店の状況によっては、休業しない方がメリットのある場合も少なくない。支援策の効果を総点検した。
