
清水理裕
#31
資源市況や円安効果の追い風を受けて、2023年3月期に空前の好業績となった大手商社。三井物産、伊藤忠商事、丸紅、三菱商事の中でそれぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクを初試算した。各社とも業績を伸ばす中でOB世代が劣勢に立たされているかどうかを検証。一方、勝ち組となったのはどの世代か?このほか専門家による5年後の平均年収予想も掲載する。

#30
業績が好調な3メガバンク。国内金利が上昇すれば、さらなる追い風となりそうだ。三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの中でそれぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクを初試算した。その結果、3メガとも若手が劣位に立たされたが、勝ち組世代は果たして?このほか5年後の平均年収予想では、各社とも現在の水準を大幅に上回る結果となった。
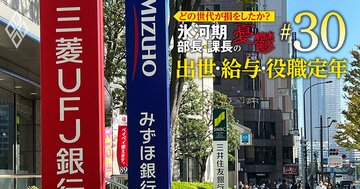
#29
今回は化学セクターの主要企業、花王、富士フイルムホールディングス、資生堂を取り上げる。3社の中でそれぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクを初試算した。花王、資生堂はシニアが優勢であることが判明したが、その一方、富士フイルムは?このほか専門家による5年後の平均年収予想も掲載する。

#28
給料の高さで知られる3メガ損害保険会社に、四大生命保険会社。今回は東京海上ホールディングスと第一生命ホールディングス、さらに三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険を傘下に抱えるMS&ADインシュアランスグループホールディングスの計3社を取り上げる。各社の中で、それぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算。東京海上と第一生命は共に氷河期世代が健闘したが、一方、負け組となった世代は?

#27
国内製薬会社でしのぎを削る武田薬品工業、アステラス製薬、第一三共。今回は、年収が高い製薬業界の中でも、特に高給の企業として知られる3社を取り上げる。各社の中で、それぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算。シビアな成果主義の武田は年配社員が優位だが、氷河期や若手世代はいかに。さらにアステラス、第一三共の勝ち組、負け組はどこか?

#26
新しい少額投資非課税制度(NISA)の2024年開始もあり日本株は歴史的な高水準だが、ネット証券最大手のSBI証券の主導で手数料の引き下げ競争が激化している。今回は大手証券の野村ホールディングスや大和証券グループ本社、SBIホールディングスに加え、リース最大手オリックスの計4社を取り上げる。各社の中で、それぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算。「キープヤング」と若手登用をうたう野村は若手が勝ち組となったが、大和、オリックス、SBIは?

#25
年功序列や長期安定雇用を前提に人事制度を設計してきたNTTグループ。だが、2020年以降、職務の内容によって社員の処遇を決める「ジョブ型組織」へと転換を図ろうとしている。NTTの中で年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算した。氷河期世代が意外にも健闘。その一方で負け組となった世代は?このほか5年後の平均年収予想額では、超大幅アップを見込む結果となった。

#24
コロナ禍で陸海空運の業績は明暗を分けた。鉄道・空運が大打撃を受けた一方、海運は需給逼迫(ひっぱく)による運賃高騰で史上空前の利益を上げた。今回はJR東日本とJR東海、ANAホールディングス、日本郵船の4社を取り上げる。各社の中で、それぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算。ANAはOB世代が勝ち逃げなのかを検証。一方、残り3社で優勢だった世代はどこか。

#23
ゼネコン業界の最上位に君臨し、売上高が1兆円を超えるスーパーゼネコン。今回は鹿島、清水建設の2社を取り上げる。両社の中で、それぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算。鹿島、清水建設ともOBより現役世代が優位に立ったが、その中でも勝ち組になったのは一体どの世代?このほか5年後の平均年収予想額では、現状を上回る結果となった。

#22
重電国内首位の日立製作所は2010年代以降、年齢ではなく、実力によって社員の処遇を決める制度の導入を進めている。日立の中で年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算。現役世代では氷河期が劣位に立たされたが、それでは勝ち組となったのは35歳か。それとも55歳か。OBは得をしたのか。

#21
新車の世界販売台数で、トップをひた走るトヨタ自動車。円安効果を追い風に、2024年3月期の連結純利益は過去最高の3兆9500億円を見込む。トヨタの中で年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算した。その結果、同社は年配の社員が優勢ではあったが、5世代の詳細を見ると差異が……。このほか5年後の平均年収予想額では、現在の水準を大幅に上回る結果となった。

#20
資源高などを背景に、空前の好業績となった大手総合商社の2023年3月期決算。その中でも、純利益で1兆1806億円をたたき出した三菱商事は別格だ。同社の中で年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクの推移を初試算。三菱商事は若手が優勢であることが判明したが、その一方、割を食っている世代は?
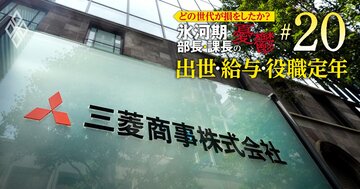
#19
ベストセラー作家の橘玲氏に、行き詰まりを見せている日本の人事制度の問題点について話を聞いた。日本人の働き方に関して、橘氏は「世界一仕事が嫌いで会社を憎み、世界一長時間労働なのに労働生産性は最も低い」と鋭く指摘。さらに、日本の人事制度が内包する残酷な現実についても、独自解説してもらった。

#18
非正規と正社員の格差は「身分差別」役職定年は「大いなる矛盾」、橘玲氏が喝破
ベストセラー作家の橘玲氏に、行き詰まりを見せている日本の人事制度の問題点について話を聞いた。非正規の待遇は「身分差別」であると喝破。役職定年が抱える大きな矛盾点についても、橘氏に独自解説してもらった。

#16
ベストセラー作家の橘玲氏が、日本の社会が直面している世代間格差の問題点について指摘する。ダイヤモンド編集部の取材で判明した、キリングループの年齢別社員数グラフを題材にして、団塊の世代・バブル期入社組とゆとり世代の間で板挟みになっている、就職氷河期世代の惨状を解き明かす。

#15
「上級国民/下級国民」はどの世代?橘玲氏に聞く団塊、バブル、氷河期、ゆとり…割を食うのは誰だ
団塊、バブル、氷河期、ゆとり、どの世代が割を食っているのか?資産運用や人生設計、日本人論など広範なテーマに取り組み、ベストセラーを出し続けている作家の橘玲氏。日本の社会が直面する世代間格差の問題について、橘氏が縦横無尽に論じる。

団塊のしわ寄せで氷河期世代が不幸に?20年間の給料データで判明「世代間格差」の真実
『週刊ダイヤモンド』11月25日号の第1特集は「団塊、バブル、氷河期、ゆとり…どの世代が割を食っているのか?役職定年 部長・課長の残酷」です。主要64社を対象に、年齢別の推計年収と企業内ランクを、ダイヤモンド編集部が初めて作成しました。そこから浮かび上がった世代間格差とは?ここでは清水建設を例に、注目ポイントを解説します。

#31
職種別・業種別・部署別プロンプト31選の後編。電通デジタルや現役の医師、地方自治体などに、実際に使っているプロンプトを教えてもらった。業務の時短につながるものから、競馬予想のように趣味で楽しめるものまで各種取りそろえた。

#30
これまでの記事で紹介できなかった職種別・業種別・部署別プロンプト31選を大公開。前編に当たる今回は、住友商事、NECなどから実際に使っているプロンプトを聞き出した。エクセルや投資案件のリスク評価など、業務負荷の低減に役立つものをそろえた。

#26
ネットショップを手掛ける小規模店舗や個人。時間を取られるのは商品紹介の文章作成だ。だが、ChatGPTを使えば、わずか30秒で済んでしまう。しかも面倒なプロンプトなしで利用できる方法があるのだ。
