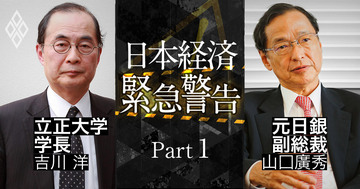吉川 洋
主要国のインフレは、資源・穀物価格の上昇を契機として川上から川下へと物価上昇が波及していく形で加速していった。そこにはインフレ予想が介在する余地はない。「物価を決めるのはインフレ予想ではない」の後編では、物価の決定とインフレーションの発生についての理論的な変遷をたどり、物価を決定する真の要因を検証する。

2020年以降、主要国においてインフレが高進した。その理由として、予想インフレ率の上昇が挙げられることが多い。しかし、物価上昇の過程などを分析して、浮かび上がるのはインフレ予想ではない。物価を決定する真の要因を2回にわたり検証していく。前編では、要因を分析する前提として、日米欧の20年以降の物価動向を整理する。
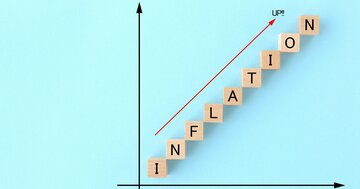
「なぜ日本でイノベーションが生まれないのか」の連載3回目では、日本における「アーキテクト」の不在やリスクを取れる「エコシステム」が乏しいことがイノベーションを生まない理由になっていると指摘した。第4回では、日本においてリスクを取るべき主体は誰なのかを挙げるとともに、イノベーションが生まれない三つ目の要因を検証する。

「なぜ日本でイノベーションが生まれないのか」の連載2回目では、EV(電気自動車)のトップメーカーとなった米テスラのイノベーションを生む土壌を検証した。3回目では、米モデルナ、米テスラのケースと比較しながら、今の日本に欠けているものを浮き彫りにする。

「なぜ日本でイノベーションが生まれないのか」の連載1回目では、イノベーションが起きる条件を探るために、新型コロナウイルスワクチンをいち早く開発した米モデルナを取り上げたが、2回目では、EV(電気自動車)のトップメーカーとなった米テスラのイノベーションを生む土壌を検証する。

日本経済の低迷については、さまざまな要因が指摘されるが、最大の要因は、イノベーションの欠如である。イノベーションはどのような状況の下で生まれてくるのか。なぜ、日本では生まれないのか。4回にわたり、その原因を探っていく。第1回では、新型コロナウイルスワクチンをいち早く開発した米モデルナが、イノベーションを起こした要因を検証する。

2020年3月に、世界の金融市場は流動性危機に陥り、企業も金融機関も現金を確保に走った。そのままいけば金融危機の再来となるところだったが、主要国の中央銀行が大幅な流動性供給に踏み切り、市場を安定させた。日本においても、倒産や失業を抑制することができた。安定を得たものの、そのツケである悪化した財政、過剰流動性の出口戦略は見えない。

連載の2回目では、コロナ禍での財政政策の効果を検証する。雇用調整助成金をはじめとする雇用維持に向けた財政支出は、失業率の上昇を抑制し、一定の成果を上げた。しかし、国民への一律給付金は消費を押し上げるには至らず、効果は乏しかった。Go Toキャンペーンの実施は経済効果もあったものの、感染拡大への影響を考えると功罪相半ばの結果をもたらした。

他の主要国同様、日本もコロナ禍に対し財政・金融政策を総動員して、経済を下支えした。結果として主要国で最悪の財政状況はさらに悪化し、日本銀行の金融緩和にも拍車がかかったものの、正常化の出口に向けた議論はなされないままである。3回にわたり、経済の現状分析とこの1年間の財政・金融政策の評価、今後示すべき道筋の検証をする。第1回では、足元までの経済動向を振り返る。

Part3
吉川立正大学学長と山口元日銀副総裁による緊急警告の第3回は、金融危機前並みに高まった米国の金融リスクが日本経済激震の要因となるメカニズムを解き明かす。長期化する“異次元緩和”は日本の金融機関の体力を奪い、外貨に傾倒した資産運用は国際金融市場の負のショックへの耐性を低下させる。次なる米国のバブル崩壊は日本経済を揺るがす可能性が高い。さらなる金融緩和はそうしたリスクを増大させるだけである。
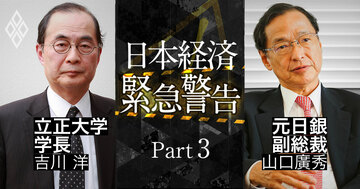
Part2
吉川、山口両氏による緊急警告第2弾では、金融危機前の米国に蓄積していたさまざまなひずみ、金融リスクの積み上がりを検証する。不動産価格の上昇、それを支えた融資の急拡大、融資を証券化した商品の急増、危機前には異変と思われなかった事象が、その後の危機を引き起こす要因となっていった過程を振り返る。
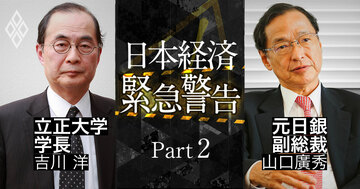
Part1
経済においてバブルは幾度となく膨張と崩壊を繰り返してきた。世界経済の減速傾向が強まる中、再びその危険性が高まっている。どうすればその崩壊の予兆を察知できるのか。まずバブルとは何かを検証する。