
木原洋美
第41回
名医やトップドクターと呼ばれる医師、ゴッドハンド(神の手)を持つといわれる医師、患者から厚い信頼を寄せられる医師、その道を究めようとする医師を取材し、仕事ぶりや仕事哲学などを伝える。今回は第41回。リハビリテーション医学の分野で日本だけでなく、世界をリードする藤田医科大学の医学部リハビリテーション医学I講座主任教授・大高洋平医師に話を聞いた。

なかなか出口が見えてこないコロナ禍の中、マスクをつけることで引き起こされる「マスク頭痛」がクローズアップされている。しかも、マスクとの関連が分かりやすい頭痛だけでなく、帰宅してマスクを外した途端に起きるマスク頭痛まであるという。原因や対処法について、頭痛に詳しい東京女子医科大学病院(東京都新宿区)頭痛外来の清水俊彦客員教授に話を聞いた。

二子玉川で開催された絵画展『アートが痛みを減らすっ展!?』。アートを通して、病気についてのコミュニケーションの活性化、そして理解と行動変容を促すことを目指している。アートと痛み――。一見結び付かなさそうな二つはどのように関係しているのだろうか。仕掛け人は現役歯科医師で自らも画家である長縄拓哉氏に聞いた。

第21回
起床時、スマホに手を伸ばしたマサオミさん(仮名・当時55歳)はある異変に気付いた。手がおかしい。右手の小指と薬指がこわばって動かしにくく、うまく持てないのだ。鈍く痛んでいるような気もする。きつい手袋をしているような感覚だろうか。

第40回
名医やトップドクターと呼ばれる医師、ゴッドハンド(神の手)を持つといわれる医師、患者から厚い信頼を寄せられる医師、その道を究めようとする医師を取材し、仕事ぶりや仕事哲学などを伝える。今回は第40回。ジェネリック医薬品(後発医薬品)普及の立役者である武藤正樹医師が、超高齢化社会を迎える日本に必要な医療の形を語った。

生活習慣病の予防においては、良い生活習慣を身に付けることが重要である。しかし長年かけて培った習慣を変えることは容易ではない。医師も患者の行動を変えることに苦労している。そうした中で、宮城県登米市では、特定健康診査で簡単な「ある数値の測定」を実施したところ、長年頭を悩ませていた市民の高血圧問題が目に見えて改善に転じたという。その方法とは。

ジェネリック医薬品メーカーの小林化工が、医薬品を不正に製造・販売したとして業務停止命令を受けた。水虫などの治療薬として使用される医薬品に睡眠導入薬が混入されていたのである。問題の背景には、医薬品製造における構造的、制度的な課題が見え隠れする。われわれの生活にも大きく関わる医薬品の安全性の問題と、その対策について専門家に聞いた。

医療用麻薬による依存症が増えている。がん患者を中心に、痛み止めとして一回に数百錠を処方されている患者もいるという。医師が処方するからといって安全とは限らない。医療用麻薬に関する知識が不十分な医師も少なくないのだ。今、日本でも深刻な問題となりつつある医療用麻薬の大量使用について、獨協医科大学医学部麻酔科学講座の山口重樹教授に聞いた。

第39回
名医やトップドクターと呼ばれる医師、ゴッドハンド(神の手)を持つといわれる医師、患者から厚い信頼を寄せられる医師、その道を究めようとする医師を取材し、仕事ぶりや仕事哲学などを伝える。今回は第39回。「口腔顔面痛」医療の普及に尽力してきたパイオニアである和嶋浩一歯科医師(慶應義塾大学病院歯科口腔外科学教室非常勤講師)を紹介する。
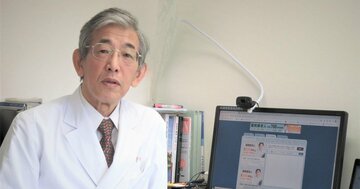
第38回
名医やトップドクターと呼ばれる医師、ゴッドハンド(神の手)を持つといわれる医師、患者から厚い信頼を寄せられる医師、その道を究めようとする医師を取材し、仕事ぶりや仕事哲学などを伝える。今回は第38回。老舗の眼科専門病院の後継者として知られ、すべての人が使いやすく共生できる「ユニバーサルデザイン」を追求している井上賢治医師(井上眼科病院グループ理事長、井上眼科病院院長)紹介する。

緑内障は白内障と違って、治療を受けても失われた視力や視野を取り戻すことはできない。そのため早期発見と治療が非常に重要だが、困ったことに初期のうちに気付く人はほとんどいない。なぜ気付けないのか、早く気付くにはどうしたらいいのかなど、井上眼科病院(東京都)の院長で緑内障に詳しい井上賢治医師に話を聞いた。

第20回
3年前のある日、シンペイさん(仮名・当時58歳)は食事中に思わず顔をしかめた。左頬の内側をがぶりと、かんでしまったのだ。

第37回
名医やトップドクターと呼ばれる医師、ゴッドハンド(神の手)を持つといわれる医師、患者から厚い信頼を寄せられる医師、その道を究めようとする医師を取材し、仕事ぶりや仕事哲学などを伝える。今回は第37回。長時間透析や在宅血液透析など患者の状態やライフスタイルに応じた「最善の透析療法」を追求している腎内科クリニック世田谷院長の菅沼信也医師を紹介する。
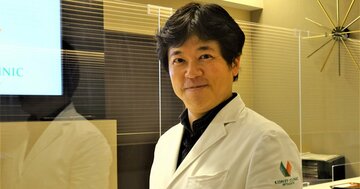
コロナ禍が続く中、花粉症のシーズンに突入した。ここにきて、本来、継続した治療が必要な喘息患者が感染を恐れるなどの理由で、受診を控えてしまうという問題が発生している。喘息患者の「受診控え」はなぜ問題なのか。

第19回
(うっ、痛い。なんだこの痛み)夕食後、パソコンに向かって作業していたセイジさん(仮名・51歳)は額を抑え、低くうめいた。突然左目の奥に痛みが走り、激しい頭痛に襲われたのだ。一瞬、視界に虹のような光の輪が見えたような気もした。

欧米先進国に比べて「病床数が多い」と言われる日本の医療体制。それでも、なぜ、日本の医療は今回のコロナ禍で逼迫(ひっぱく)して、医療崩壊寸前に陥ってしまうのか。その理由を客観的なデータに基づいて検証・解説し、医療関係者の間でも話題となっている『医療崩壊の真実』の著者である渡辺幸子氏(グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン社長)に聞いてみた。

事件や自殺、孤独死などが発生した住宅(不動産)は「事故物件」と呼ばれ、忌み嫌われる存在だ。しかし、こうした物件を積極的に買い取り、「成仏不動産」と称して流通させる事業を行っている会社がある。その「成仏不動産」事業を運営する株式会社MARKSの花原浩二社長に取材してみた。

コロナ禍で、通院頻度が高い透析患者の院内感染リスクが指摘される中、自宅で人工透析を受ける「在宅透析」が注目されている。しかし、日本の在宅透析の普及率は0.2%と著しく低い。その理由や実情について、腎内科クリニック世田谷(東京都)の菅沼信也院長に取材した。
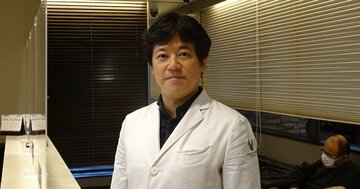
第36回
名医やトップドクターと呼ばれる医師、ゴッドハンド(神の手)を持つといわれる医師、患者から厚い信頼を寄せられる医師、その道を究めようとする医師を取材し、仕事ぶりや仕事哲学などを伝える。今回は第36回。「夜の街の守り神」として呼ばれ、性感染症のスペシャリストとして有名な尾上泰彦医師(性感染症専門医療機関「プライベートケアクリニック東京」院長)を紹介する。

第18回
(よかった、今日は痛くなかった)ヨシアキさん(仮名・45歳)はベッドの上で安堵のため息を漏らし、目を閉じた。透析を始めて3年になるが、穿刺(せんし:血管に針を刺すこと)の痛みだけは全然慣れることができない。
