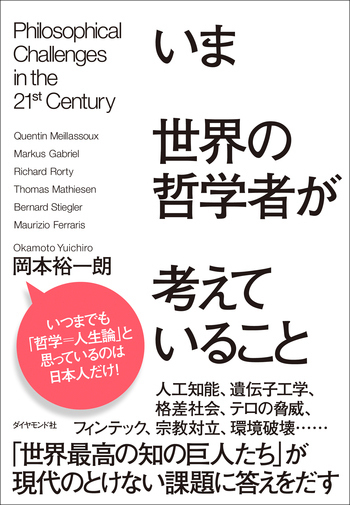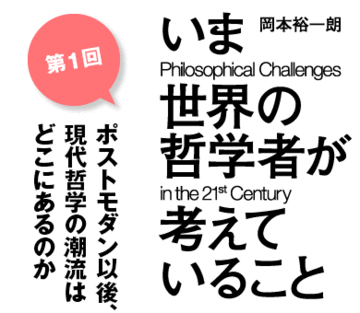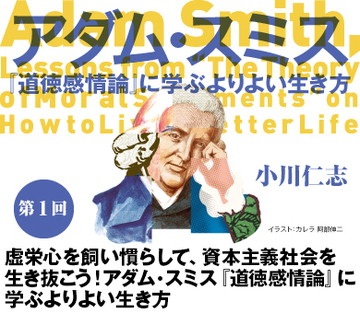ポストモダン以後の「哲学」
20世紀の哲学を「言語論的転回」として理解するとき、確認しておきたいのは、1970年代以降世界的に流行したポストモダン思想との関係です。「ポストモダン」というのは、もともと建築の分野で始まりましたが、その後、文化全体の新たな運動として、時代的な潮流となりました。
哲学的に「ポストモダン」を定式化したのは、ジャン・フランソワ・リオタールの『ポスト・モダンの条件』(1979年)です。彼はポストモダンを「(モダンの)大きな物語に対する不信」と規定しましたが、そこで「大きな物語」と呼ばれたのは、万人が認めるような真理や規範を指しています。たしかに、現代人は、こうした真理や規範を、もはや信じているようには見えません。
それに代わって、リオタールがポストモダンとして提唱したのが、小さな集団の異なる「言語ゲーム」でした。他とは違う「小さな物語」を着想し、多様な方向へ分裂・差異化することが、ポストモダンの流儀となりました。こうして、ポストモダン思想が、20世紀の言語論的転回と結びつくことになります。
言語論的転回では、極端に言えば、(1)「言語によって世界が構築される」と見なされます。これは、一般に「言語構築主義」と呼ばれる立場です。この考えを代表するものとして、ジャック・デリダの表現「テクストの外には何もない」(『グラマトロジーについて』)がしばしば引用されます。
また、「言語構築主義」とともに、ポストモダン思想は、(2)「異なる言語ゲームは共約不可能である」と考えています。言語によって現実が構築されるとすれば、言語が異なるとき、現実も違ってくるのは当然でしょう。そのため、ポストモダンは、他の立場との「差異」を強調し、ついにはいずれの主張も優劣がつけられないという相対主義へと到るわけです。
(1)言語構築主義と(2)相対主義を提唱した哲学者が、アメリカで活躍したポストモダニストのローティです。彼は、『言語論的転回』を編集した後、『哲学と自然の鏡』(1979年)や『プラグマティズムの帰結』(1982年)を出版し、自分の立場を鮮明に打ち出すようになりました。さらには、同時代のフランスやドイツの哲学者たちと対話を進め、アングロサクソン系と大陸系の哲学の相互理解を図ったのです。そのときローティは、みずから「ポストモダニスト」を自認しました。
たしかに、20世紀の後半には、言語論的転回が積極的に推し進められ、そのうえポストモダンの流行によって、社会構築主義や相対主義が主張されるようになりました。そのため、道徳的な「善悪」や、法的な「正義」に関しても、普遍的な真理はなく、多様な意見があるにすぎない、とされました。極端な場合には、自然科学的な事柄に関してさえ、多様な解釈があるだけであって、どの説が正しいのかは決定できない、と言われることがあったのです。
しかしながら、21世紀を迎える頃には、ポストモダンの世界的な流行も終息し、「言語論的転回」に代わる新たな思考が、模索されるようになりました。大別して3つの潮流がありますが、その概説は9/12(月)に公開する次回にゆずることにしましょう。