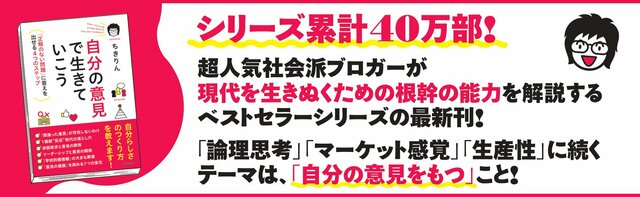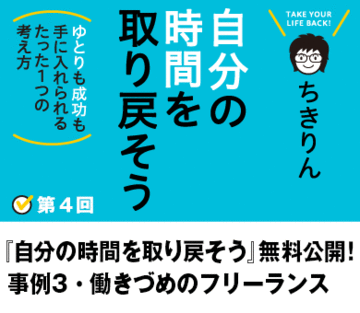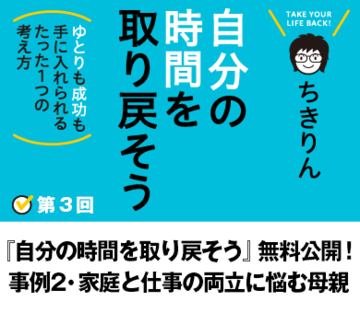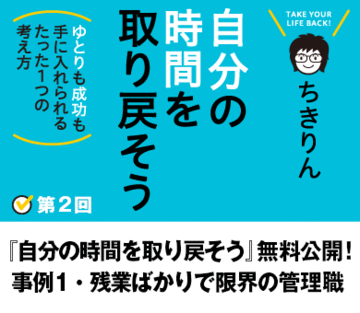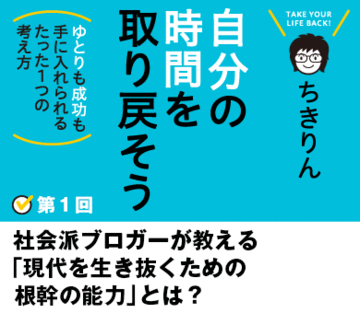多忙な人の生活を振り返りながら働き方を考えるシリーズの最後は、学生起業をした勇二の物語です。順調に事業を立ち上げた勇二ですが、最近、会社のみんなの働き方がなにか変だと感じています。スタートアップなんだから忙しいのは当たり前?でも本当にこのままでいいのでしょうか?
みなさんもぜひ一緒に考えてみてください。
焦る起業家 勇二
都内の大学を卒業した勇二は、就職活動を経験していない。学生時代に仲間と事業を始め、卒業後に株式会社化してそのまま経営者になったからだ。
父親は安定した企業に勤める会社員だが、勇二はその姿に憧れたことがない。愛情を持って育ててくれたことに感謝はしているが、自分もそうなりたいとは思えない。
大学入学後、勇二はすぐに「会社員以外の道」を探し始めた。ツイッターやフェイスブックを駆使し、有名な学生起業家、スタートアップ企業でバリバリ働いている大学の先輩、時にはネット上の有名経営者にも連絡をとり、話を聞いては起業の意思を強くした。
3年生の半ば、就活のために髪を切る同級生を横目に、仲間3人と事業を始めた。ネット上のサービスなので、場所代とサーバー代、それに電気代くらいしかかからない。全員で寝る間も惜しんでサービスを作り込み、あちこちに売り込んでユーザーを増やした。
卒業後には株式会社化し、本格的に事業化。その後、多数の会員を抱える先行企業との提携が実現すると、会員数が一気に増え、勇二の会社は“ブレイク”した。
勇二はメディアの取材や、起業家フォーラムでの講演など広報活動に走り回った。コラボレーションのオファーも次々と持ち込まれ、体はいくつあっても足りない。
そんなある日、創業メンバーのひとりが珍しくまじめな顔で勇二に問いかけた。「このままじゃマズイと思わない?」――勇二は一瞬、言葉につまった。問い返すまでもなく「なんのコトか」わかっている自分に気づいたからだ。
事業は順調に進んでいたが、組織全体でみると、明らかに創業当時よりスピード感に欠けていた。つい最近も新サービスのひとつが予定開始日に間に合わなかった。その前は急に持ち上がった問題について半日たっても誰も手をつけていなかった。
3人で始めた企業も今や社員だけで30人。アルバイトや契約社員を加えると50人に近い。みんな恒常的に夜中まで働いており、オフィスには毎日誰かしら泊まり込んでいる。いつも、そしてどの部署からも「人手が足りない」と悲鳴が上がっていた。
幸い投資家からの評価も高く、資金は潤沢だ。勇二は、「人はいくら雇ってもいい。だからとにかく早くやれ。この分野はスピードがすべてなんだ!」と繰り返していた。
ところが社員も増えているし、みんな必死で働いているのに、必ずしも仕事のスピードは速くなっていない。昔は3人であれだけの仕事をしていたのに、今はその10倍もいて、なんでこんなに時間がかかるのか。創業メンバーが指摘してきたのもまさにその点だった。「こんなところで足踏みしてる場合じゃない。これからまだまだ成長する必要があるっていうのに、こんな状態じゃとても無理だと思わないか?」
なにが問題なのか、あらためて点検すると多くの問題が見つかった。まずは打合せや会議の非効率さだ。各部署の屋台骨を支えるキーパーソンたちは、あらゆる打合せに呼び出され、業務執行に使える時間が足りなくて困っていた。「この資料を見てください」と送りつけられる資料をすべて読んでいたら、半日が終わってしまうという社員もいた。
真夜中まで延々と会議を続けたのに、アクションにつながる明確な結論がなにひとつ出ていない会議も多かった。みんなで興奮して夜通し話し合い、それで満足して終わってしまうのだ。

上司があまりに忙しそうなため、質問をすることがはばかられ、わからないことがあっても聞きに行かない部下もいた(それがために後から起こったトラブルで上司はさらに忙しくなるのだが……)。
仕事の取捨選択もできていなかった。会社に泊まり込むほど働いている社員の仕事を見てみると、優先順位の低い、どうでもいいような仕事に驚くほど長い時間を使っている。コツコツ型で真面目なスタッフは、依頼されたすべての仕事をこなそうと連日、深夜まで働き、とうとう体を壊してしまった。
コミュニケーション上の非効率さも目立った。パートナー企業の超多忙な部長に(電話で話せばすぐにすむ話なのに!)アポをとって会議を設定しようと、10日も待たされている社員もいた。
勇二はクラクラした。このままでは規模50人の会社で終わってしまう。世界に出るどころか、国内においてさえ次々と現れる新しい企業にすぐに抜かれてしまうだろう。
とはいえ勇二のスケジュールも、いっぱいいっぱいだった。しかも営業やネットワーキングには強みのある勇二だが、組織運営にはなんの知見もない。「これはマジでやばい」「いったいどうすればいいんだ?」
勇二は頭をぐるんぐるん回しながら考え始めた。