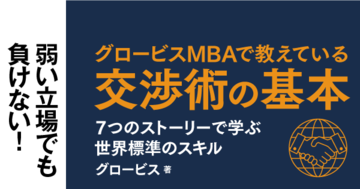交渉決裂は「交渉の終わり」ではない
いや、こう言うべきかもしれない。
交渉決裂は必ずしも交渉の終わりを意味しない。交渉決裂も「交渉プロセス」の一部になりうるのだ、と。
「どういうことか?」と不可解に思う人もいるだろう。
そこで、ある日本人事業家のエピソードを紹介したい。その人物は、ある商品を売り込むために、いちはやく東南アジアに販路を開拓した先駆者だった。しかし、そのビジネスが軌道に乗り始めると、世界的な大資本がその市場への参入を開始。熾烈なシェア獲得競争が始まった。
大資本は資金力にモノを言わせて大量に広告を出すとともに、安値攻勢を仕掛けてきた。日本人事業家は、長年かけて築いた販路を最大限に活かして応戦。シェアの一部は奪われたものの、シェアトップの座を死守していた。ただ、安値競争を強いられたことで、事業が傷ついていたのも事実だった。
そして、市場競争が膠着状況を迎えたころ、大資本から合併の打診があった。「このまま安値競争を続けたら、お互いに傷つくだけだ。手を結ばないか?」というわけだ。もちろん、日本人事業家にとっても“渡りに船”の提案。早速、合併交渉に乗り出した。
ところが、この交渉が難航した。
最大のポイントは合併比率だった。日本人事業家は「シェアトップなのだから、自分が51%以上の株式を保有して、主導権を握らなければならない」と考えていたが、大資本のプライドがあったのだろう、「最大限譲歩しても50%ずつの対等合併」と譲らなかったのだ。
しかし、対等合併では、両者の思惑が異なる局面において事業運営が迷走しかねない。「それは最悪の選択だ。どちらかが主導権を握らなければ、合併はうまくいかない」と日本人事業家は、対等合併を断固として拒否。交渉は1年を超えて続けられたが、どうしても折り合いをつけることができなかった。
そこで、日本人事業家は単独で事業を継続することを決断。交渉決裂を通告した。合併して、さらにシェアを高めるとともに、安値競争を終わらせるのがベストの選択肢だったが、対等合併では絶対にうまくいかない。この事業を成功させるためには、「自分が51%の株式を保有する」という条件が不可欠。それが不可能なのであれば、交渉決裂やむなしと判断したのだ。
しかし、話はここで終わらない。
その後、日本人事業家は大資本に対して徹底的に抗戦。数年をかけてジワジワとシェアを伸ばした結果、ついに大資本が音を上げたのだ。「このままでは撤退に追い込まれる」と危機感をもった大資本は、再び合併交渉を打診。今度は、日本人事業家が「51%の株式」を保有することを認め、あっさりと合意に至ったのだ。