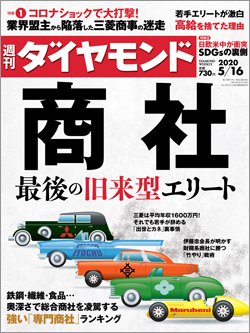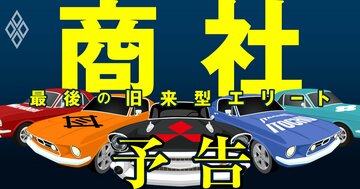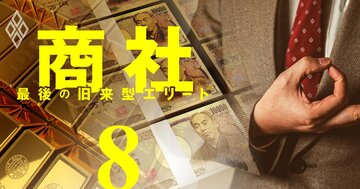各社首脳からは「世界景気のV字回復は極めて困難。L字に近い回復に止まり、21年も緩慢な景気回復に止まる可能性がある」(丸紅社長の柿木真澄氏)、「コロナが要因で人流と物流が途絶え、これによりエネルギーの需要がまさに蒸発した」(三井物産社長の安永竜夫氏)と悲観の声が聞こえる。
岡藤氏もダイヤモンド編集部のインタビューで、コロナ禍について「1年から2年くらいは続く。ワクチンが開発されても、ズタズタになったサプライチェーンを戻すのに時間がかかる。消費者や投資家のマインドも冷え込む。原油価格が戻らず、産油国の通貨暴落や米国のシェール企業の連鎖倒産も起きるかもしれない」との見通しを述べている。
各社は財務規律を強め、コロナ禍の嵐を耐え忍ぼうとするだろう。
短期的にはそれは止むを得ない措置かもしれない。だが、コロナはデジタル化を一層加速させ、ビジネスのあり方や人々の価値観に劇的な変化をもたらす。商社は急変する時代に対応し、旧来型ビジネスモデルを変化しなければ生き残れないだろう。岡藤氏は業界内再編の可能性さえ指摘する。
かつて冬の時代や商社不要論を打破したように、商社は再び変わることができるだろうか。あるいは没落する最後の旧来型エリートとなってしまうのか。彼らは今、正念場を迎えている。