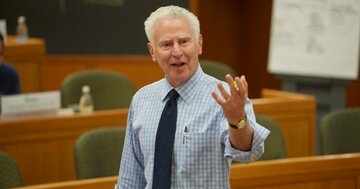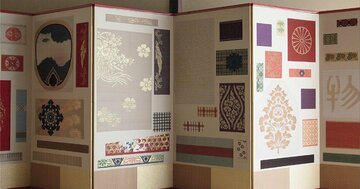カイゼンから、製品やサービスのカクシンへ
ロバート・オースティン教授
(ウェスタン大学アイビー・ビジネス・スクール)
トランスフォーメーションと呼ぶような大きな変革を成し遂げることは難しいものです。今日リーダーにとって、最も困難な課題だと言えるかも知れません。社会が大きく変わっていますので、組織変革は不可避にもかかわらずです。
ここで、2種類の変化を混同しないように注意を喚起したいと思います。一つ目の種類の変化は、自分自身が起こしたのではないものです。世界情勢など自社を取り巻く環境とか競争相手がもたらしたものです。二つ目はリーダー自身が起こし、そちらへ組織を向かわせようとする変化です。
どちらの変化も対処することが難しいです。外から与えられた変化への対応は喫緊の課題です。なぜなら、変化に対応しなければ生き残れないかもしれないからです。
多くの日本企業は、今話題のマイケル・タッシュマン教授らの「両利き性」の議論でいうところの探査(exploration)よりも深耕(exploitation)モードに安住していたように思います。カイゼンはこのモードにとても適合的ですが、カクシンはそうではありません。
日本企業にとってプロセス・イノベーションはより自然にできるものの、「両利き性」を維持してラディカルなイノベーションを起こし、顧客やビジネスモデルに大きな変革をもたらすことはそうでもないということです。
昔、日本の経営者に「革新ということばから想起されるのはプロセス・イノベーションですか製品やサービスのイノベーションですか」と問うたところ、40社中39社の人がプロセス・イノベーションだと回答しました。
もちろんプロセス・イノベーションが悪いわけではなく、効率性向上は日本企業が長年にわたって得意としてきたことです。ただ、プロセス・イノベーションは顧客に対し、価格引き下げなどを通じた間接的なインパクトしか与えないのに対し、ラディカルなイノベーション、あるいはBMI(ビジネスモデル・イノベーション)はより直接的なインパクトがあります。
顧客にとってただ間接的に実感するイノベーションなのか、喜んで対価を支払おうとするイノベーションなのかには差があります。日本企業は後者のことをもっと考えるべきではないかと思います。