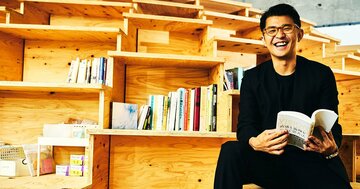人と社会の「障害」を乗り越えるサイボーグ技術
『サイボーグ009』や『仮面ライダー』を端緒とし、その後の漫画・アニメーション・特撮ヒーローの多くが、サイボーグの概念をベースに作られている。米国でも80年に登場したDCコミックスの『サイボーグ』や、日本の特撮から大きな影響を受けた87年の映画『ロボコップ』でこの概念が採用され、広く普及していく。さらに、SFには分類されない作品でも、サイボーグが組み込まれているケースも増えてくる。例えば、尾田栄一郎の海賊漫画『ONE PIECE』では、船大工のフランキーが重傷を負った自分の体を、武器や機械を使って修復するエピソードが描かれている。このように、サイボーグ技術は、機械化技術によって超能力を得るという理論的根拠を持って、SF、特にヒーローもののジャンルに大きな影響を与えてきたのである。
一方で、研究分野としてのサイボーグは、主に障害を助けるさまざまな医療技術を生み出してきた。心臓の動きを支えるペースメーカー、筋肉が動くときの微弱な電流、筋電をもとに機械の身体を動かす義手や義足、目の見えない人や耳の聞こえない人を手助けする人工視覚や人工内耳などは、サイボーグ技術の応用例であり、高齢化に向かう社会において大きなビジネスの機会として注目されている。最近では筋萎縮性側索硬化症(ALS)とサイボーグ技術で戦う、ピーター・スコット-モーガン博士などがいる。
また現在では介護補助技術の一つとして、人間の力を増幅する装着型のロボットが「装着型サイボーグ」と呼ばれることがある。近年ではこうしたサイボーグの能力拡張の側面に注目し、主に情報技術によって拡張能力を実装する「人間拡張(オーグメンテッド・ヒューマン)」という概念も提唱されている。
物語のサイボーグ技術が人間に超人的な力を与え、私たちの社会を脅かす「障害」を解決する姿を描いてきた一方で、現実のサイボーグ技術は、障害に苦しむ人をサポートし、その人自らが解決する技術として進化している。前回触れた、機械技術が人間と社会に組み込まれ、私たちを手助けする未来社会を志向したノーバート・ウィーナーのサイバネティックスのビジョンは、SF作品と科学技術の双方に受け継がれ、お互いに影響を与えながら社会を変える原動力となっていったといえる。