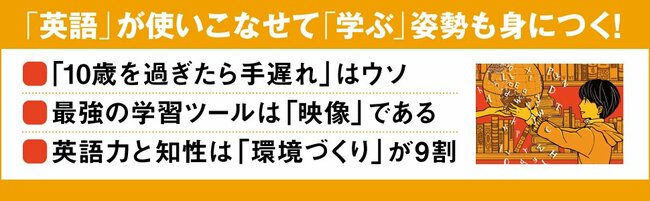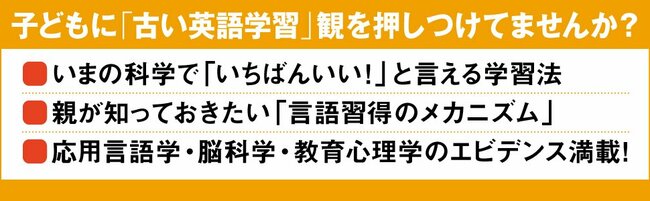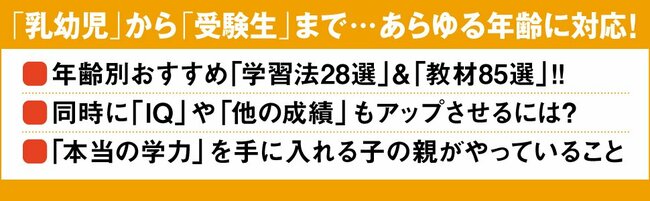子育て世代の英語教育熱は年々、高まる一方だ。昨年から小学校で英語が正式教科となり、さらに今年から始まった大学入学共通テストでは英語の出題パターンが刷新されるなど、英語学習を取り巻く環境が大きく変化しているからだ。
いまや、日本の大学ではなく海外の大学に直接進学するケースも珍しくない。そのため、子どもが学校で後れを取ったり大学受験で失敗したりしないように「家庭で英語をどう教えればいいのか」、「どうすれば英語力が伸びるのか」と悩む保護者も多いだろう。
そこで参考になるのが、元イェール大学助教授で現在は英語塾の代表を務めている斉藤淳氏の著書『ほんとうに頭がよくなる 世界最高の子ども英語』(ダイヤモンド社)だ。
本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、英語教育に関して優秀な親ほど誤解しがちな2つの教育法についてご紹介する。
 Photo:Adobe Stock
Photo:Adobe Stock
誤解1:片言だけでも会話ができれば十分
真実:「幼稚な英語」だと損する!
「英語なんてただの言葉。体当たりで飛び込んで、片言レベルになれば十分!」
日本人の英語力の惨状を見かねてか、こんな意見をよく目にします。この考え方には僕も共感するところがあります。英語は使わなければ意味がありませんし、いつまでも修行ばかりしていないで、さっさと荒野に飛び出せばいいのにと感じることは多々あります。
一方で、「通じさえすればそれでいい」を強調するあまり、文法や細やかな表現を軽視する風潮が広がることにも危機感を覚えます。
短絡的な「英語漬け」教育は見直しが必要
子ども英語の世界で、「通じさえすればいい!」という流れの後押しを受けているのが、イマージョン(immersion)式の教育スタイルです。
イマージョンの語源の「immerse」は「浸す」の意。要するに、英語環境に子どもを投げ込み、英語にどっぷり浸からせる教育だと言えばわかりやすいでしょうか。
「小さいころから英語漬けにすれば、バイリンガルになるはず!」と信じて、幼児のうちからイマージョンスクールに入れる“熱心な”保護者も少なくないようです。
しかし、ビジネスや海外大学への留学でも十分に通用する英語力、さらにそれに留まらない知的体力にも磨きをかけていってほしいのであれば、イマージョンも含めた教育計画は、もう少し長期的な目線で見直す必要があります。
まず、子どものころに見よう見まねで覚えた英語というのは、結局のところ、「子どもレベルの英語」であり、そのままでは社会には通用しません。
さらに、将来的にどんなことを学んでほしいかのビジョンがないまま、幼児期に英語を身につけさせても、その力は実践の機会を迎えないまま、子どもの成長とともにやがて忘却のかなたへと消えてしまうでしょう。
「英語を話せる」だけの人ならたくさんいる
最後に、幼児期のイマージョンは、母語(日本語)による学習の時間を犠牲にして成り立っていることも自覚しておく必要があります。
親の仕事の都合で幼少期を海外で過ごした帰国子女は、外資系企業などに就職した際に、壁にぶつかることが多いと聞いたことがあります。
流暢な英語コミュニケーション能力を買われて採用されたにもかかわらず、蓋を開けてみると、彼/彼女の話す英語がとても幼稚で、ビジネスには相応しくなかったりするからです。
しかも今後は、「英語をしゃべる能力だけはある子」は大して珍しい存在ではなくなるでしょう。だとすると、カジュアルな会話の能力だけでなく、一定の知性に裏打ちされた「大人の英語」をマスターしない限り、大多数の人材のなかに埋もれることになりかねません。
誤解2:12歳では手遅れ。幼時から英語教育を!
真実:「臨界期」は仮説。焦る必要なし
「子どもには言葉を学ぶ力が備わっている」という話の裏返しで、「ある一定年齢を過ぎると、もうバイリンガルにはなれない」と考えている人もいらっしゃるようです。
いわゆる臨界期(Critical Period)という考え方です。一定の時期を過ぎると言語能力の一部が習得されづらくなることは、学術的な研究成果からも確からしいという報告が上がっています。
一方で、これが過度に強調されているもの事実です。とくに幼児向けの英語教室などでは、おそらくマーケティング上の意図もあって、「大きくなってからでは遅い!」などと、早期教育を煽っているところも少なくありません。
まず押さえておいていただきたいのは、臨界期はもともと「母語の習得」に関して提唱された仮説だということです。つまり、ここで想定されているのは、ある言葉を母語として(=ネイティブレベルで)習得するリミットなのです。
早期教育神話は2重に間違っている
それによれば、たとえば6~7歳までにその言語に触れれば、ほぼ誰でもネイティブになれるのですが、そのあたりを過ぎてくると、音の聞き取りや発音の点でネイティブレベルになれない人が少しずつ出てきます。
また、10歳あたりを過ぎると、文をつくる能力などはネイティブになれないと主張する研究もあります。いずれも個人差はありますし、あくまで「仮説」の域を出ていません。
したがって、早期教育神話は、「母語」の習得に関する「仮説」を、「外国語」の文脈で「絶対視」しているという意味で、2重に間違っています。
英語を学ぶのは「早ければ早いほどいい」とは限りませんし、学びはじめるタイミングに手遅れもありません。実際、専門家たちの世界では、「外国語習得については臨界期仮説は当てはまらない」と実証した研究もあります。
早期教育にも一定のメリットはある
一般的に言われる英語の臨界期は、じつは“あってないようなもの”なのです。とはいえ、早くはじめることにも意味はあります。とくに発音などに関しては、子どものころからはじめた学習者のほうがかなり有利です。「音から」英語に入っていく力、英語の「かたまり」を受け入れる力は、小さな子どもにはかないません。
しかも小学校低学年くらいまでであれば、ためらいなく英語の世界に飛び込み、それを楽しもうとしますから、モティベーションなども保ちやすい面があります。
一方、小学校高学年から中学生くらいになると、心理的なハードルがあらわれます。JPREPの子どもたちも、キッズクラスの生徒たちは、こちらが何か質問をすると同時に「Me,me!!」と一斉に手を挙げますが、小学校高学年~中学生のクラスになると、途端にシャイな子が増えます。
人前での発音練習を恥ずかしがったり、異性の目を気にして発言しなくなる、声が小さくなるといったことが起きます。学校の授業で「日本式英語」の発音に触れはじめると、本格的な発音を恥ずかしがるようにもなるのでとても苦労します。
とはいえ、これは年齢特有の問題ですから、致し方ない部分もあるでしょう。その意味で、小さいころから本格的な英語に親しませることにも、よい面はあるだろうと思います。
(本稿は、『ほんとうに頭がよくなる 世界最高の子ども英語』より一部を抜粋・編集したものです)