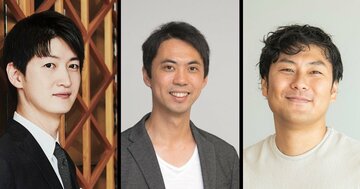最先端に行きすぎず、大衆の気持ちを持ち続ける
小泉:メルカリに関しても、フリマアプリの分野ではフリルが先行していた。今だから言えるけど、僕は「フリル、すごくいいな」と思ったんだよね。でもメルカリに入ったのは、マスに広がっていくことが予測できたから。
平尾:私は「時代をつくる力」だと思いました。小泉さんは時代をリードしてど真ん中を歩んでこられたと思っています。
小泉:たしかに、その嗅覚は自分でも強いと思う。それが僕の強みであり、自分らしさでもあるね。
平尾:めちゃめちゃアントレプレナーじゃないですか(笑)。
小泉:でも一方で、いつもインターネットの先端にいすぎないようにしようと思っているかな。
平尾:どういう意味ですか。
小泉:先端にいすぎると、大衆の気持ちから離れていく気がするから。僕は最先端の技術を使いたいわけではなく、最先端の技術は使いながらも、多くの人の人生に影響を与えるサービスを作りたい、そういう会社を経営したいということ。ミクシィによってSNSという情報発信をするプラットフォームが出てきたことで、人々の生活は変わったよね。メルカリによって売買の手段が広がったよね。そういうなるべく多くの人に影響を与えたいという考え方なので、極論すれば最先端でなくてもいい。
平尾:その考え方は、「76世代(1976年生まれのIT起業家)」のみなさんとは違いがありそうですね。今でこそみなさんいろいろおっしゃいますけど、それぞれお好きなゾーンが強い気がします。でも、小泉さんはユーザー志向なんですね。大衆に寄り添うという意味では、小泉さんはテレビCMもご自身でつくりますよね。
 平尾 丈(ひらお・じょう)
平尾 丈(ひらお・じょう)株式会社じげん代表取締役社長執行役員 CEO
1982年生まれ。2005年慶應義塾大学環境情報学部卒業。東京都中小企業振興公社主催、学生起業家選手権で優秀賞受賞。大学在学中に2社を創業し、1社を経営したまま、2005年リクルート入社。新人として参加した新規事業コンテストNew RINGで複数入賞。インターネットマーケティング局にて、New Value Creationを受賞。
2006年じげんの前身となる企業を設立し、23歳で取締役となる。25歳で代表取締役社長に就任、27歳でMBOを経て独立。2013年30歳で東証マザーズ上場、2018年には35歳で東証一部へ市場変更。創業以来、12期連続で増収増益を達成。2021年3月期の連結売上高は125億円、従業員数は700名を超える。
2011年孫正義後継者選定プログラム:ソフトバンクアカデミア外部1期生に抜擢。2011年より9年連続で「日本テクノロジーFast50」にランキング(国内最多)。2012年より8年連続で日本における「働きがいのある会社」(Great Place to Work Institute Japan)にランキング。2013年「EY Entrepreneur Of the Year 2013 Japan」チャレンジングスピリット部門大賞受賞。2014年AERA「日本を突破する100人」に選出。2018年より2年連続で「Forbes Asia's 200 Best Under A Billion」に選出。
単著として『起業家の思考法 「別解力」で圧倒的成果を生む問題発見・解決・実践の技法』が初の著書。
小泉:そうだね。そういえば、僕はテレビ業界や芸人さんの友だちに「小泉さんは10年早かったらテレビ業界にいた人だ」と言われる。
平尾:たしかにそうかもしれない。
小泉:ヒット番組のプロデューサーか、場合によっては芸人になっていた可能性さえあると言われているよ。
平尾:本当ですか。
小泉:本来そちら側にいるべき人間が、時代によってインターネットを使っているだけなのかもしれない。
平尾:なるほど。
小泉:インターネットとは何か。それを深く考えると、僕は「個人をエンパワーするもの」だと思うんだよね。もともと僕は、決められたフレームワークの中で評価されるのが大嫌い。でも、自己発信型のインターネットで自分の好きなように表現でき、自分の思い通りにできれば、個人はエンパワーメントされる。それが好きだから、ミクシィもメルカリも好きだった。組織づくりでも、上下の縦の構造が嫌いで、個人が下に追いやられている窮屈感が嫌い。だからもっとフラットにしたいという思いがずっとあるんだよね。
――自分にしかできないことに力を注いでいこうという思いがあった?
小泉:誰かがやっていかなければならないことに対して、自分なりの仮説でやっていきたいという思いはあったね。
――そこを言語化されたのは、何がきっかけになったんですか?
小泉:未だに言語化はできていないと思うけど、振り返ると今日みたいなインタビューでメディアに自分のことを話していく過程で、自分はそうだったんだと再確認した。でもやっているときはわかっていなくて、見えてもいない。