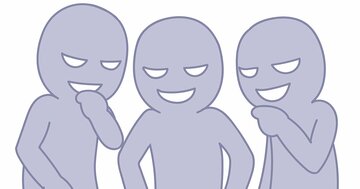正しい行いをする「模範生徒」より、ふざけてばかりの「問題児」の方がずっと
そうして気がつけば、私は「優等生」というカテゴリーから出ることができなくなっていた。キャラクターというのは、一度みんなから決められてしまうと、よっぽど衝撃的な事件がないかぎりは変更が許されない。昨日までいじりキャラだったやつが、いきなり明日からいじられキャラになりたいですと言ってもそれは無理なのだ。ゲームみたいにボタン一つでキャラを変えるなんてできない。
私はいつも先生から褒められた。褒められるためによい行いをしようとつとめた。私はますます「優等生の川代さん」になった。私を「さきちゃん」とか「さき」とか、名前で呼ぶ人はひとりもいなかった。私は「川代さん」以外の何者にもなれなかった。
徐々にクラスのみんなは、大人に模範生徒として褒められるための行動をしなくなっていった。私がいたからだ。私がとくべつ優等生でいて、とくべつ模範生徒でいれば、みんながみんなよい行いをする必要はない。私ひとりがクラス代表としてよい行いをしていれば、それですむのだと、優等生を私ひとりに押し付けたほうが楽だと、みんなが気がついたのだ。みんなは、大人に褒められようとするのをやめた。
でも私は、いくら褒められても、なんとも思わなくなっていた。一時的に褒めてもらえたからなんだというのだ。いくらいい行いをしたからって、みんなの仲間に入れるわけでもない。面白がってもらえるわけでもない。
大人は優等生の私をいい子だと褒めた。えらいと言って頭をなでた。でも私は、先生が模範生徒の私よりも、勉強ができなくてふざけてばかりの「問題児」の方が、ずっと好きなのを知っていた。いくら「よい行い」をしても、「正しいこと」をしても、私を好きになってくれるわけじゃない。
「好き」と「正しい」は違うのだ。
人に好かれることに執着しない人間だからこそ
私は、クラスの中心にいる「人気者」たちが羨ましかった。私も「人気者」のカテゴリーのなかに入りたかった。でもどうやったら入れるかなんてわからなかった。勉強すれば合格できる試験もなかった。人間関係やコミュニケーションには、過去問もなければ、必勝法もなかった。でも私はどうしても人気者になりたかった。「人気者」の立場から見える景色を、一度でいいから見てみたかった。
どうしたら人気者になれるだろうかと必死に考えた。漫画の『キャンディ・キャンディ』に出てくる主人公みたいな、みんなに好かれる人間になるにはどうしたらいいだろうと考えた。キャンディの考え方やものの見方の真似をした。クラスにいる人気者の子がどんな性格なのかを研究した。いろんな人気者の共通点を探そうとした。でもこれという決定的な共通点なんて見つからなかった。明るくて、みんなとよく話して、優しくて。それくらい。おとなしくてあまり話さなくても人がよってくる人もいるし、ぶっきらぼうに見えてもクラスの中心に居場所をちゃんと作っている人もいた。よくわからなかった。
でも悩んでいても仕方がないから、その人気者の真似をした。みんなから囲まれて、愛されて、好かれている人間がやっていそうな仕草や行動や、言葉遣いを真似た。
「最近変わったね」と誰かが言った。「明るくなった」と。「アクティブになった」と。
ああ自分は変われているんだと、確実に成長できているんだと、私は安心した。私の変化をまわりのみんなも感じ取ってくれているのだと思った。自分が人気者になれる日も近いと思った。
でも私のまわりには、人の輪はできなかった。
いつも、私の隣にいる誰かのところに、輪ができた。私はあくまで、その輪をつくる人間の一人にしかなれなかった。
どう頑張っても、どんな努力をしても、いくら人気者の真似をしても、私のまわりに、人は集まってこなかった。
正直に、私には友達が少ないのだと、自分のまわりには人があまり集まらないのだと、母に吐露した。でも母みたいになりたいとは言えなかった。どこか、何かが、嫉妬していた。母に対してすらも。
そうやって悩む私に母はこう言った。
そんなにたくさんの人に囲まれなくてもいいじゃない、と。自分が大切にしたいと思う人が数人そばにいてくれれば、それでいいじゃない。人気者になる必要が、どこにあるの、と。
たしかにそのとおりだと私は思った。別にみんなに好かれたところで、自分にその全員を平等に大切にできるエネルギーも甲斐性もないことくらい、わかっていた。
私にはよく遊ぶ友人が何人かいる。気も合うし、楽しい。そういう人たちに、愛情を向ければそれでいいのかもしれない。広く浅くよりも、狭く深く、の方がずっといい。そもそも、今いる友人を大切にせずに、もっと愛されたいと求めることこそが、贅沢すぎる悩みだ。今のままで十分幸せだと、どうして満足できないのか。
母の言うことはもっともだったし、母も実際にそういう信念を持って人と接しているのがわかった。
でも頭では納得していても、私は心のなかではこうも思っていた。
お母さんはいつも人に囲まれているからそう思うんだよ、と。
母は、自分のまわりに人が集まってこないという苦しみを知らないのだと思った。自覚がないのだ。そして、「人に囲まれたい」だの、「人気者になりたい」だのという悩みも、母にはなかったのだろう。母には承認欲求なんてものは存在しなかった。
そして人に好かれることに執着しない人間だからこそ、母のまわりには人の輪ができるのだということも、私は痛いほどよくわかっていた。母は何かをしてもらうことよりも、人のために何ができるかということしか考えていない。愛されることよりも、いかに愛するかということに尽力していた。そういう母のところに、みんなが愛を求めて集まるのは当然だと思った。無条件で、自分を受け入れてくれる。愛してくれる。自分はここにいてもいいと、安心させてくれる。愛を持った人と一緒にいるのは、楽しいのだ。自分の敵じゃないと思える人のそばにいるのは、楽なのだ。
私みたいに、どうしたら人に認めてもらえるかとか、そういうことばかり気にしているような人間のところに、人はよってこないのだ。シンプルなことだ。人に好かれたいなら、人を好きになればいい。自分が人に愛情をこめて接すればいい。
でも私にはそれができなかった。
なぜなら、私は自分が一番かわいかったからだ。自分が一番大切で、自分に愛情を注ぐのに必死で、人に愛情を向ける余裕なんて、なかった。
私はとてもずるい人間だった。
でもやっぱり誰かに愛されたかった。
みんなに愛されたかった。