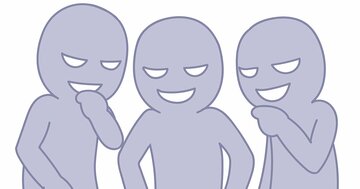気軽に自分の思いを共有・発信しやすいというメリットがある一方、見たくもない他人の華やかな人生が無遠慮に流れ込んでくる現代のSNSの仕組みに、息苦しさを覚えている人も多いはずだ。日本だけに限らず海外でも、SNSで着飾った自分を表現することに明け暮れ、「自分の居場所を見つけなければ」というプレッシャーから病んでしまう人が増殖しているという。「承認欲求とどう向き合うか」といった諸問題は、現代病の一つとも言えるのかもしれない。
そんな、自分自身の承認欲求に振り回され、不安や劣等感から逃れられないという人にぜひ読んでもらいたいのが、エッセイ『私の居場所が見つからない。』(ダイヤモンド社)だ。著者の川代紗生さんは、本書で承認欲求との8年に及ぶ闘いを、12万字に渡って綴っている。「承認欲求」とは果たして何なのか? 現代社会に蠢く新たな病について考察した当エッセイの発売を記念し、今回は、未収録エッセイの一部を抜粋・編集して紹介する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
自分への戒めみたいに、死を想像する瞬間
私はぼんやりと、自分が死んだあとのことを想像する。
たとえば今、私が不慮の事故か突発性の病気か何かで死んでしまったとして、何人の人が私のために集まってくれるだろうかと想像する。何人の人が、私のために、貴重な時間を割いて黒い服を着てやってきて、香典を上げてくれるだろうか。いったい何人の人が、私を惜しんで泣いてくれるだろうか。もっと私と話したかったと、私との思い出がいくつも浮かんでくると言って、別れの言葉を言ってくれるだろうか。私の遺影のまわりには、いくつの花が添えられるのだろうか。
私が今大切に思う人々は、私が死んだことを、どれくらい惜しんでくれるのだろう。
そして私はぼんやりと、さらにふかく想像する。自分の大切な人が死んだあとのことを。
母が死んだら。父が死んだら。恩師が死んだら。恋人が死んだら。親友が死んだら、どう思うだろうか。
親しい人は数少ない。心から信頼出来る友人も片手で足りるくらいしかいない。そんな彼らがもし死んでしまったとしたら、私は大きな痛手を負うだろう。誰にも止められないくらいに、みっともなく、赤子のように泣き腫らすだろう。
そのときのことを私はなるべく、具体的に、鮮明に、色がついて見えるくらいに、立体的に想像する。
そして、強く思う。もっと彼らのことを大切にしなければならないと。人がいつ死ぬかなんてわからない。気がついたときには死んでいたなんてことになったら遅いのだ。
忘れっぽく、自分勝手な私は、そうやってときどき、できるだけリアルに「死」を想像しないことには、まわりの人たちを大切にすることができない。愛情をきちんと向けることができない。行動に起こせない。いざいなくなってしまったら、バカみたいに、「ああしておけばよかった」と後悔するくせに。
だからまるで自分への戒めみたいに、私は死を想像する。
でも、彼らが死んだときのことを想像したあと、決まってこうも考える。
私が信頼している人たちは、皆とても魅力的な人間だ。情熱的で、芯を持っていて、愛情深くて。私と同じように、多くの人が彼らの魅力に吸い寄せられるように集まる。私は彼らのことが好きだ。いなくなられたら困るし、私のそばにいて欲しいと思う。きっと多くの人が、彼らに対してそう思うだろう。
でも私はきっと、彼らの葬式で、彼らを惜しんでたくさんの人が泣く光景を目にしたら、こう思うだろう。
もし、自分が死んだら、こんなに多くの人が、自分のために泣いてくれるのだろうか──と。
「軽蔑の色」がやんわりとにじむホームルーム
子どもの頃からどうしてか、みんなに好かれる人のことが苦手だ。
なにもしていないのに、気が付いたらいつも多くの人に囲まれている人間というのが、この世にはたしかに存在する。とくに自分から大きなアクションをとるでもなく、とくべつ面白いでもなく、とくべつ秀でた派手な特徴や能力があるわけでもない。でも勝手にまわりにどんどん人が集まってくる。いつも気が付いたら、たくさんの人の輪のなかにいる。そんな人間。
私の母は、まさにそういうタイプの人間だった。芸能人並みに美人というわけでも、話をするのがうまいわけでも、スポーツがものすごくできるわけでもなかった。でも私が母と公園に行くと、母はいつもたくさんの子どもに囲まれた。私がひとりで砂の城を作るのに夢中になっているあいだに、母は他の子どもたちの輪のなかにいた。私のおかあさんなのに、と幼心に、嫉妬したのを覚えている。
母は、お笑い芸人のようにすべらない話ができるわけではなかったが、リアクションがとても大きかった。実子の私に対してはもちろん、子どもがしたことに対して真剣に向き合い、そしてたくさん笑っていた。私が自転車に乗れるようになっては大喜びし、オセロで勝負をしては真剣に負けを悔しがった。ころころ変わる母の表情を私も、初対面の子どもたちも面白がった。
母は子どもだけでなく、大人からも好かれた。もちろん好き嫌いは多少あるものの、母自身が居心地がいい、と感じたコミュニティでは、母は人を惹きつけることができた。以前の職場でもみんなからいじられ、面白がられるキャラクターだった。母は転職するときにも多くの人に惜しまれていたし、いくつものプレゼントをもらっていた。なくてはならない存在だった。
「あなたは面白い」とよく言われるけれど、どうしてだろう、と母は不思議がっていたが、私には母がみんなからいじられ、愛されているのも、わかるような気がした。実子である私が一番よくわかっていた、と言ってもいいのかもしれない。母は愛されるべき人間であり、人の輪のなかにいるべき人間だったのだ。
そんな母を見て育ったからかもしれない、私は物心付いた頃から、「人気者」にとても強い憧れを抱いていた。
でも私は人気者と呼ばれるには到底及ばないような「キャラクター」だった。
真面目で、臆病者で、とても校則をやぶることなんてできないような子どもだった。小学生の頃は本ばかり読み、勉強もちゃんとしていたから、いつも比較的いい成績がとれていた。模範生徒として先生からみんなの前で褒められることも多々あった。
川代さんはさっき、ちゃんと目上の方に大きな声で挨拶できましたね、えらいですね。みんなも川代さんを見習いましょう。
みんなの前で褒められるというのは、正直言って鼻高々ではあったが、みんなの面倒くさそうな「はあい」という返事のなかに、軽蔑の色がにじんでいたのを、当時の私は気がついていなかった。
たったひとりでも、「正しい行い」をする生徒が褒められるという行為によって、大人の求めるレベルが上がる。子どもが「正しい行い」をしなければならない理由ができてしまう。大人に褒められるためによい行いをしなければ、という空気が流れる環境で過ごすと、子どもは少しずつ歪んでいく。自分の意思よりも大人の顔色を優先して行動するようになる。