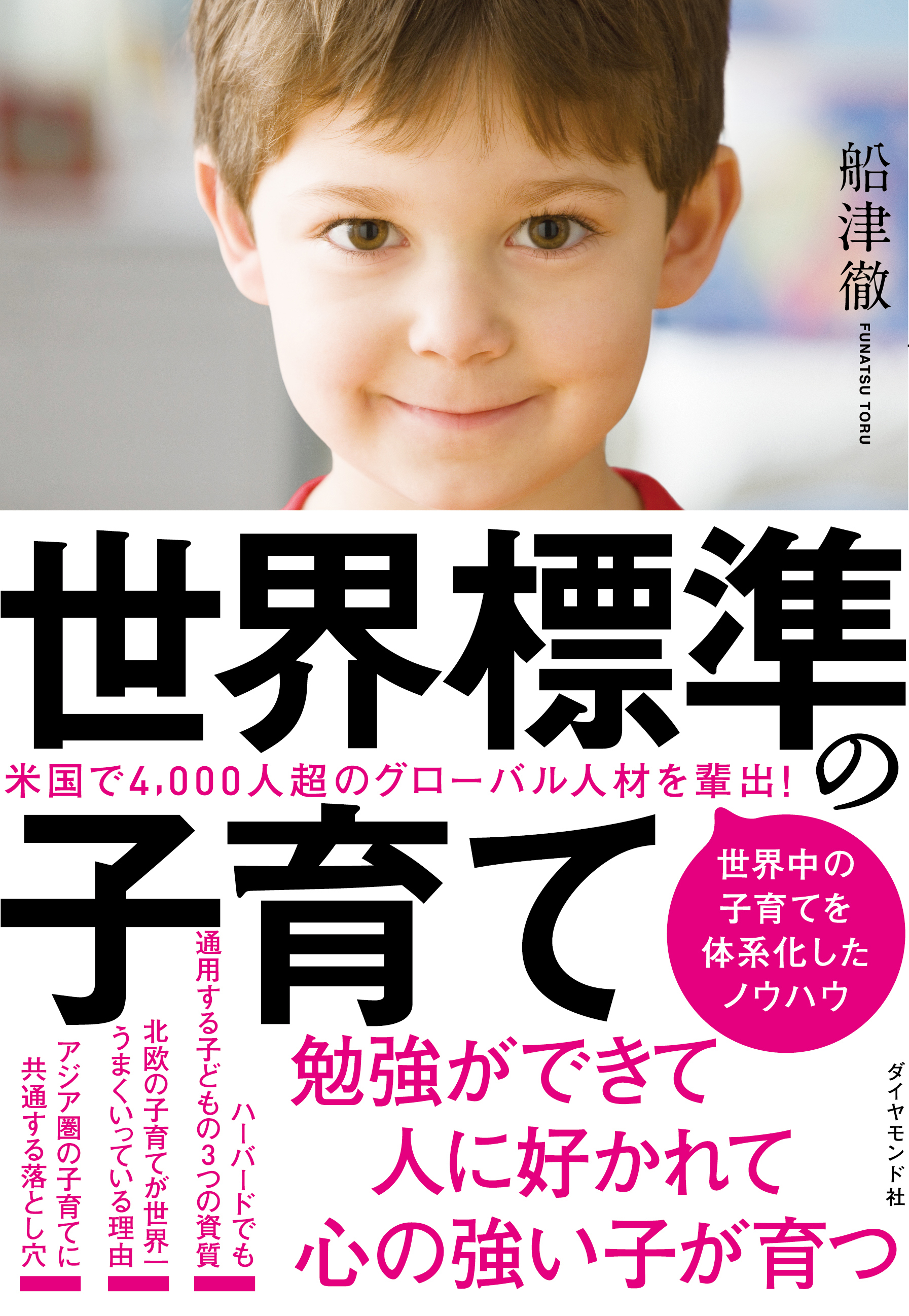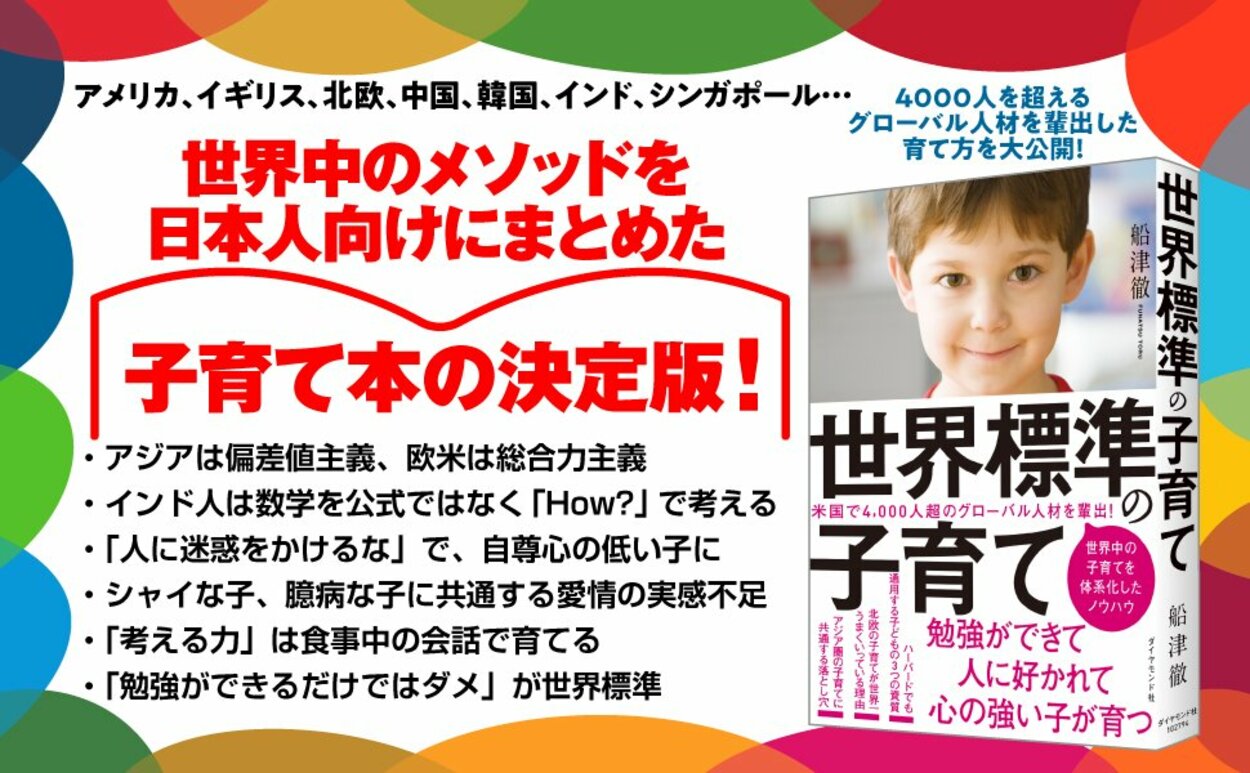子どもたちが生きる数十年後は、いったいどんな未来になっているのでしょうか。それを予想するのは難しいですが「劇的な変化が次々と起きる社会」であることは間違いないでしょう。そんな未来を生き抜くには、どんな力が必要なのでしょうか? そこでお薦めなのが、『世界標準の子育て』です。本書は4000人を超えるグローバル人材を輩出してきた船津徹氏が、世界中の子育ての事例や理論をもとに「未来の子育てのスタンダード」を解説しています。本連載では本書の内容から、これからの時代の子育てに必要な知識をお伝えしていきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
たくさん笑わせて、感情表現が豊かな子にする
0~6歳の子どもに教えるコミュニケーション力で大切なのが「感情表現」です。
欧米人から見ると、日本人は感情表現が乏しく、表情から気持ちを読み取ることが難しいと言われます。
人間は感情表現が豊かな人に親しみを感じるので、人間関係をスムーズにするためにも表情は豊かでないとなりません。
事実、感情表現が豊かな子どもは人気者になります。まわりに自然と人が集まってくるようになり、友だちに恵まれる子になるのです。
感情表現が豊かな子どもに育てるには、子どもの気持ちに親が共感することが大切です。
親が子どもの感情に対して何の反応もせず、心を通わせようとしないと、子どもは「否定された」と感じ、人との関わりに消極的になります。
子どもが嬉しい時は親も喜び、子どもが悲しい時は親も悲しみ、子どもが驚いている時は親も驚いてください。
親が子どもの気持ちに共感すること、子どもの感情に同調することを意識すると、子どもも感情表現が豊かに育ちます。
特に現在の日本では子どもが大人と関わる機会が減っているので、親が意識して感情を演出すること、感情にふれる経験をさせてあげることが大切です。
ことさらに大事なのは、母親の笑顔。お母さんはいつもニコニコを心がけてください。
母親の表情は、必ず子どもにうつります。何千人もの親子を見てきましたが、子どもはお母さんとそっくりな表情をするのです。
もちろん、父親も笑顔になることで、「笑顔になりやすい家庭環境」になるので、意識して表情を明るくしていきましょう。
笑顔が苦手、という人は、常に「口角を上げる」ことを心がけてください。
鏡の前で頬に力を入れて口角を上にギュッと引き上げてみて、これをキープします。
歯を見せて「ニッ」と笑わなくても、口を左右に大きく広げて、口角を上げる(?の筋肉を上に引き上げる)だけで十分スマイルしているように見えます。
特に朝一番は不機嫌な顔になりがちなので、まずは鏡の前で笑顔をつくって子どもに接してみましょう。
子どもをいっぱい笑わせて育てると社交的になる
子どもを笑わせることも非常に重要です。いっぱい笑って育った子どもは快活で素直な性格になります。
大人はみな、それぞれの友人関係では笑いやユーモアを大切にしているはずなのですが、なぜか家庭の中では不機嫌な表情をしている人が多いものです。
もっと家庭内に笑顔とユーモアをまき散らしてください。
子どもを笑わせるのは簡単です。
「にらめっこしましょう、あっぷっぷ!」「いない いない……バー!」と、親がおもしろい表情をつくると、それだけで子どもはキャッキャッと笑って喜びます。
また、父親が馬になって子どもを乗せる。高い高いをする。ほっぺやお腹に口をつけて「ブーッ」と息を吐く。
ひざに乗せてこちょこちょをする。「待てー」と子どもを追いかける。ぬいぐるみや人形におもしろい話をさせる。
「ヘックション!」と大げさなくしゃみをする。遊び方はたくさんあります。
ポイントは、何度も同じ動作を繰り返すことです。何度やっても子どもはキャッキャッと喜びます。
この繰り返しが子どものユーモアを育てていき、社交的な性格をつくっていくのです。