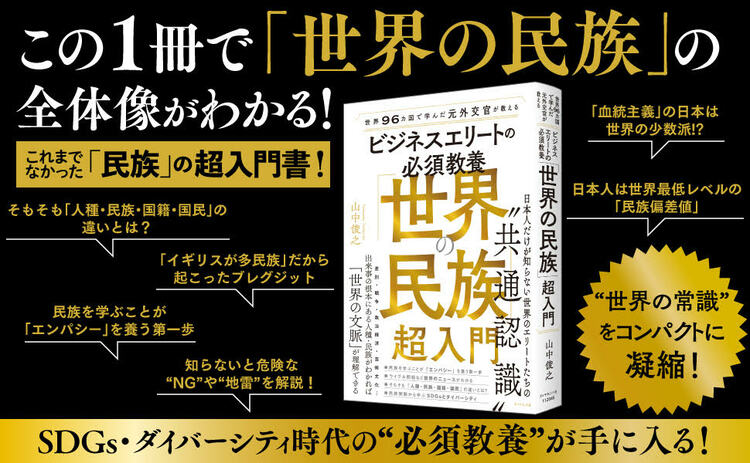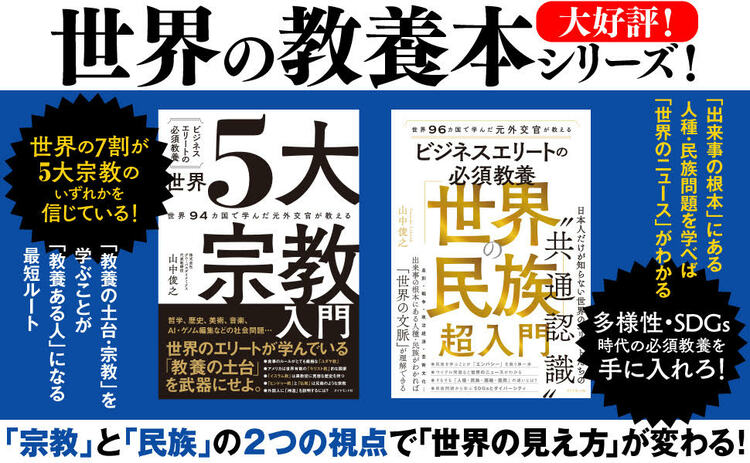「人種・民族に関する問題は根深い…」。コロナ禍で起こった人種差別反対デモを見てそう感じた人が多かっただろう。差別や戦争、政治、経済など、実は世界で起こっている問題の“根っこ”には民族問題があることが多い。芸術や文化にも“民族”を扱ったものは非常に多く、もはやビジネスパーソンの必須教養と言ってもいいだろう。本連載では、世界96ヵ国で学んだ元外交官・山中俊之氏による著書、『ビジネスエリートの必須教養「世界の民族」超入門』(ダイヤモンド社)の内容から、多様性・SDGs時代の世界の常識をお伝えしていく。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ヨーロッパ屈指の名家だったハプスブルク家
国や地域をまたがり、さまざまな民族を支配するのが「帝国」です。
ヨーロッパを理解する上では、ヨーロッパの帝国ハプスブルク家についての知識は必須項目。横串でヨーロッパを捉えることで、民族への理解が深まります。
10世紀頃、現在のスイスが拠点の貴族だったハプスブルク家は次第に勢力を伸ばし、13世紀にはハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝が誕生しました。つまり、カトリックの政治的トップになったということです。
その後、神聖ローマ皇帝の地位をハプスブルク家の人間が継承することになり、同家はあらゆる国の王家、有力貴族と婚姻関係を結ぶことで、ヨーロッパ全体に勢力を拡大します。
スペイン・ハプスブルク家、オーストリア・ハプスブルク家がその代表で、どちらもカトリックの国として繁栄しました。
「ハプスブルク家の支配地に住む者はドイツ人だ、オーストリア人だ」という理解は必ずしも正確ではなく、強いていうならヨーロッパ人。東ヨーロッパにまでおよんだ広大な帝国でした。
そんなハプスブルク家と対立していたのがフランスです。
オーストリア・ハプスブルク家の皇女マリー・アントワネットとフランス皇太子ルイ16世の婚姻は平凡な政略結婚ではなく、不倶戴天の敵である二大勢力が手を結ぼうという、ヨーロッパ和平の命題でもありました。
しかし歴史上、最も注目されたカップルは、フランス革命で処刑されてしまいます。その後、近代化の波がやってきて、ハプスブルク家は戦争をするたびに敗北し、縮小されていくのです。
政略結婚などを通じた政治的駆け引きや文化的な権威づけには長けていたものの、戦争には弱い一族でした。イギリス皇室が現存するのに対して、ハプスブルク家は消滅してしまいました。
多様性を受け入れるコスモポリタンな国々
グローバル時代の今、「ヨーロッパで本当にコスモポリタン(世界主義)である国はどこか?」と問われたら、私は小さな国をいくつか挙げます。
まずは、他民族を迎え入れるハプスブルク家のDNAを持つオーストリア。
ウィーンは、今でもヨーロッパ有数の文化と芸術の街であり、コスモポリタン的なものを持っています。ハプスブルク帝国がいろいろな民族の人を迎え入れてきた名残でしょう。
冷戦下では東西ヨーロッパの中心だったために、中東欧からきた人も少なくありません。さらに、ウィーンには国際機関がたくさんあり、日本の外務省も、国際機関が多い土地に置く「代表部」をウィーンに置いています。
コスモポリタンな国をさらに挙げるならば永世中立国であり、国際機関を多く持つスイス。
西ヨーロッパでも最高レベルの多言語国家で、フランス語、ドイツ語、イタリア語があらゆる場所で同時に普通に話されており、複数の言語を一定以上のレベルで話せる人の割合が高い国です。
多民族・多言語であるからこそ永世中立国として国を作った。この着眼点も、コスモポリタン的です。
EUの主要機関があるベルギーもコスモポリタンな国。ベルギーの北部はオランダ語に近いゲルマン系のフラマン語、南部はフランス語に近いラテン系のワロン語です。
ブリュッセルはゲルマンとラテンの両方がいる、まさに連合体であるEUの象徴のような場所です。
まさに象徴のような場所だからEUはブリュッセルを拠点に選んだのではないかと私は考えることもあります。
以上の3国とはやや異なりますが、北欧にもコスモポリタンな要素を持つ国があります。それはノーベル賞を主導しているスウェーデンとノルウェー。
小さな国であり、大国のネットワークに属することもなく、一歩引いて世界を見るというマインドを持っています。
私はノーベル賞の授賞式会場であるストックホルムの市庁舎に行ったことがありますが、セレモニーを想像しながら、「もしノーベル賞がアメリカ主導のものだったら、アメリカの意向に沿った人しか受賞できなかっただろう」としばし感慨に耽りました。
人口が少ない小国は市場が小さく、世界とビジネスをしないと経済が成り立たない。だからこそ可能性に満ちています。その小さな国が多民族であれば、多様性という今日の武器も携えることができるのです。
かつてあらゆる権力者は、大きな領土を求めました。しかし、今後は大国になることが必ずしも正解ではありません。
むしろ大国になってしまうと、他の国から嫌われる――それを中国やロシアという”ご近所さん”がいる私たちはよく知っています。