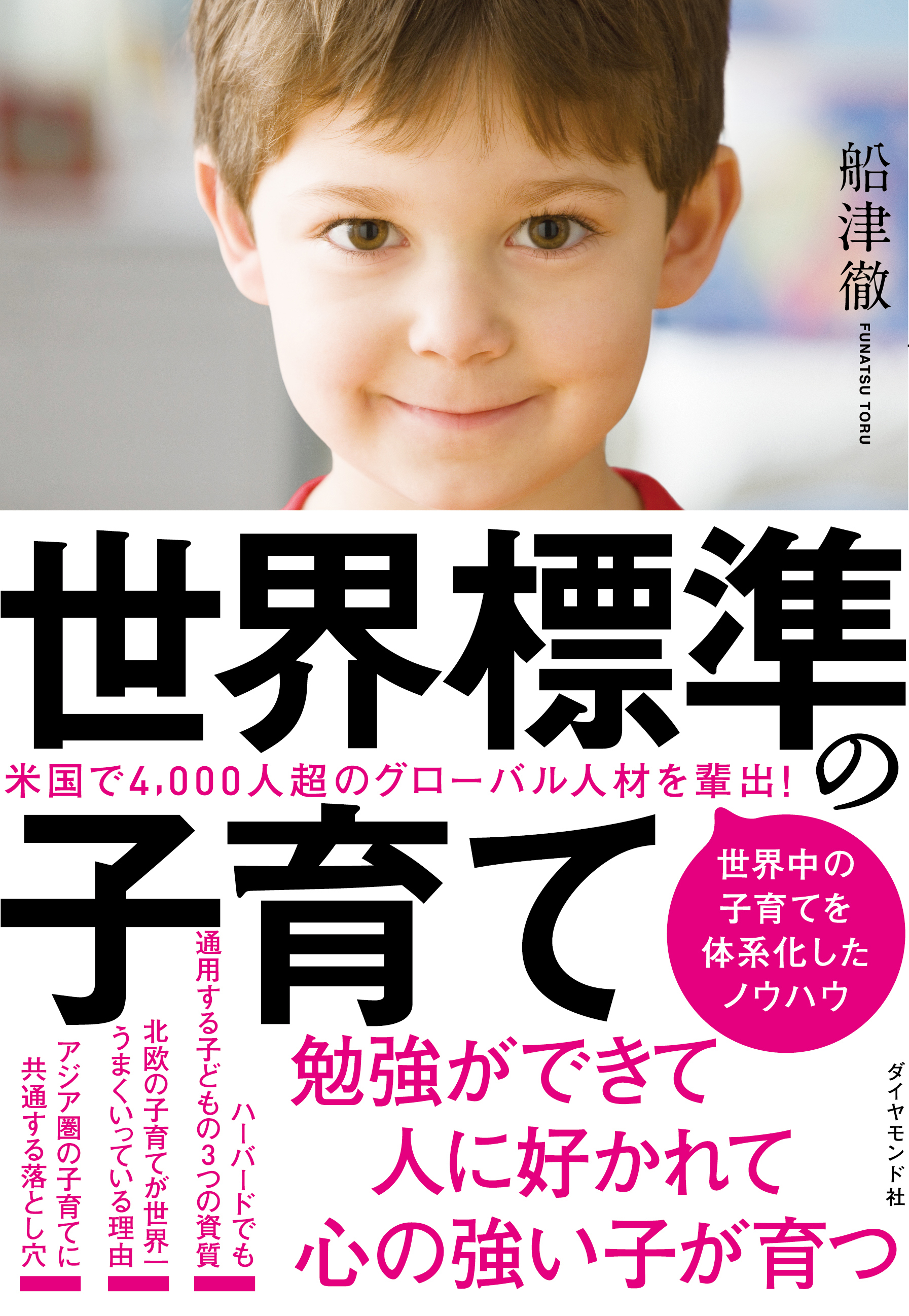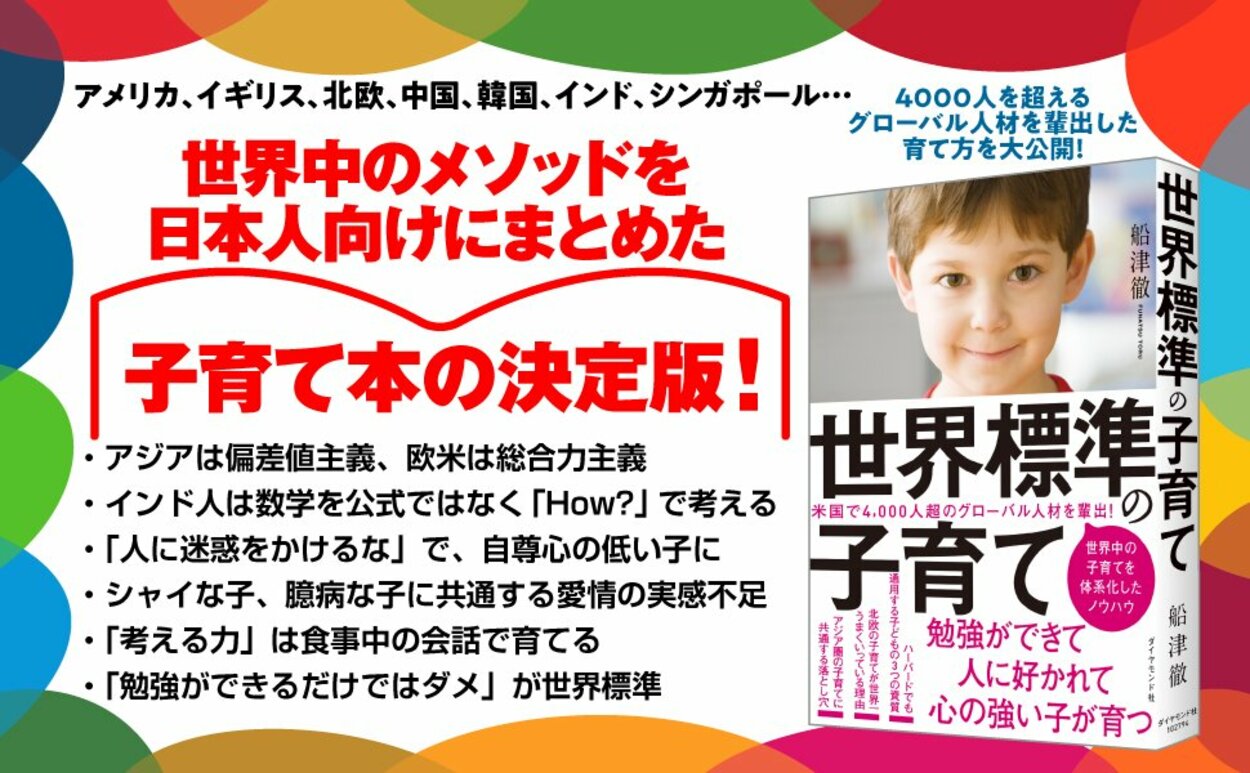子どもたちが生きる数十年後は、いったいどんな未来になっているのでしょうか。それを予想するのは難しいですが「劇的な変化が次々と起きる社会」であることは間違いないでしょう。そんな未来を生き抜くには、どんな力が必要なのでしょうか? そこでお薦めなのが、『世界標準の子育て』です。本書は4000人を超えるグローバル人材を輩出してきた船津徹氏が、世界中の子育ての事例や理論をもとに「未来の子育てのスタンダード」を解説しています。本連載では本書の内容から、これからの時代の子育てに必要な知識をお伝えしていきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
居心地が良いのは成長が止まっているサイン
「カンフォトゾーン/Comfort Zone」という言葉をご存じでしょうか?
「Comfort/居心地が良い」「Zone/地域・場所」──自分にとって「居心地の良い状態・場所」のことです。気の置けない仲間や安心できる場所です。
欧米の親がティーンエイジャーによく言う言葉が“Get out of comfort zone”です。「居心地の良い場所から脱出せよ!」ということですね。
「気の合う仲間と過ごすのが青春だろう」と思われる方もいるかもしれませんが、「この仲間は最高だ!」「ここは居心地がいい!」という感覚は、「成長が止まっているサイン」でもあります。
だから、「居心地が良い時ほど注意しなさい!」と子どもに警告するのです。
たとえばスポーツ。どんなチームにもうまい選手とヘタな選手がいます。多くの場合、チーム内のグループはうまい選手とヘタな選手に分かれていきます。
ヘタな選手は、「つらい気持ち」や「劣等感」を共有できる仲間と一緒にいたがります。そこにいれば、自分が劣っているという感覚が薄まるからです。
そしてグループにいる時間が長くなるにつれ「居心地が良くなってしまう」のです。
子どもがうまいグループにいる場合も同様です。子どもにとってトップでいることは居心地が良いことです。
しかし、「自分が一番」という状態よりも、さらに自分よりも優秀な人がいるレベルの高い環境にチャレンジしたほうが大きく成長できます。
人は、あえて居心地が悪い場所へ行くことで、知識や技能を向上させられるのです。
少し難しい環境、今よりもレベルが高い環境に子どもをチャレンジさせることによって「成長を止めない」ようにすることが、子どもの成長に必要な「根拠のある自信」をより強く、確信に変えていくために必要です。
子どもが時を多く過ごしている環境(仲間)を観察してください。そして成長を止めないように、上のレベルの環境を与えるように配慮しましょう。
実力よりも「ちょっと上」を目指す
子どもを新しい環境にチャレンジさせる時のポイントは「手の届く範囲」であること。
子どもの実力よりもはるか上の環境に入れてしまうと、自信喪失し、やる気を失うことがあるので注意してください。
たとえば子どもの高校受験、大学受験にも「カンフォトゾーン」を考慮しましょう。
ベストな選択は、実力よりも少し高いレベルの学校です。間違いなく合格できる学校、実力よりも低いレベルの学校に入っても、入学した後の成長が小さくなってしまいます。
少し上のレベルの環境に身を置くと、まわりの生徒から多くの刺激を受けます。
そして「自分も負けないようにがんばろう!」と学業や課外活動にさらに努力するようになります。
そして学生時代を通して成長を続けられるようになるのです。
「カンフォトゾーンから脱出せよ!」と言うのは簡単ですが、実践するには勇気が必要です。
人は誰もが「ラクな道」「甘い水」を選びたくなるもので、だからこそ居心地の良い環境から外に踏み出す時は親が背中を押してあげることが必要です。
まずは親が「サマースクールに参加してみない?」「演劇に参加してみない?」「ボランティアに挑戦してみない?」「短期留学してみない?」と提案をしてあげてください。
子どもは「イヤだ!」と反発するでしょうが、どこで誰と何をするのか、そこでどんな経験が得られるのか、それが将来どれだけプラスになるのかをきちんと説明すれば、たいていの子どもは「やってみようかな」という気持ちになるものです。