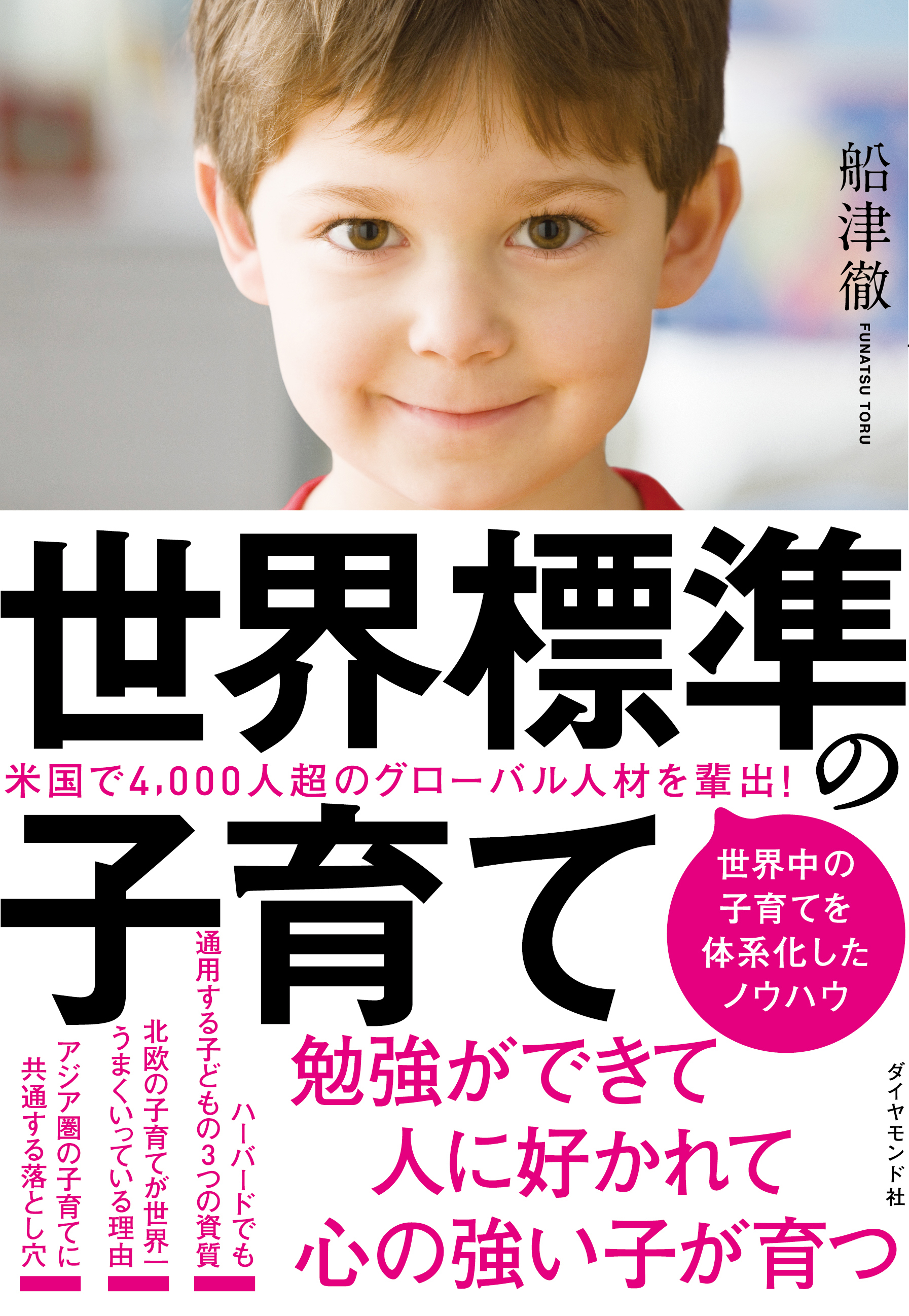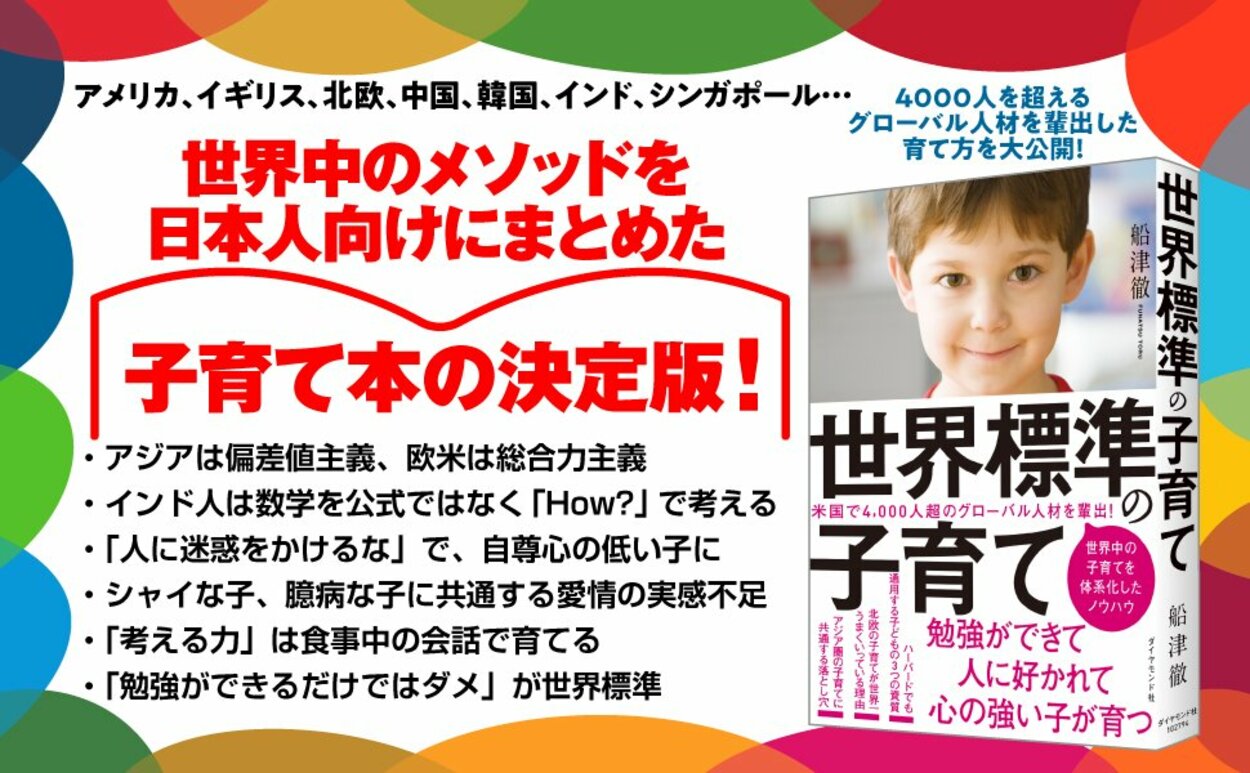子どもたちが生きる数十年後は、いったいどんな未来になっているのでしょうか。それを予想するのは難しいですが「劇的な変化が次々と起きる社会」であることは間違いないでしょう。そんな未来を生き抜くには、どんな力が必要なのでしょうか? そこでお薦めなのが、『世界標準の子育て』です。本書は4000人を超えるグローバル人材を輩出してきた船津徹氏が、世界中の子育ての事例や理論をもとに「未来の子育てのスタンダード」を解説しています。本連載では本書の内容から、これからの時代の子育てに必要な知識をお伝えしていきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
思春期の反抗は「大人」へのステップ、放っておくのが基本
ティーンエイジャー(思春期)になると、子どものトラブルは、反抗期、人間関係(異性関係)に関すること、進学や進路についてのことが中心になります。
まず、ティーンの反抗期は「放っておくこと」「受け流すこと」が基本対応です。
子どもがあまり親と話したがらなくなったら、親は子どもを子ども扱いせず、一人前の大人として扱うように心がけてください。
子どもから話すことを期待せず、親の側から日常的な「雑談」や「意見交換」を求めてみましょう。
ティーンになるとホルモンバランスが変わることもあって、子どもは情緒不安定に陥りやすくなります。基本は子どもが不機嫌な時は関わらないことです。
子ども扱いして「ああしなさい」「こうしなさい」と口うるさく言うと、さらに反抗的になります。
ティーンエイジャーを暇にさせてはいけない
欧米では子どもがティーンエイジャーになると「Keep kids busy/忙しくさせておく」ことを心がけます。
部活、塾、趣味、ボランティア、アルバイトなど、多くの活動に参加させて、多様な人付き合いをしているとイライラが分散するのです。
また忙しければ、無用なトラブルに巻き込まれることも少なくなります。
また、もう一つの対策として「タイムマネジメント/時間管理」を教えてください。自分のスケジュールを自分で管理できるように導くのです。
手帳やスマートフォンのアプリを使って「タイムマネジメント」を意識させましょう。
好きな時間に寝て、好きな時間に起きて、好きな時間に食べて、好きな時間に遊んでという不規則な生活をしていれば、宿題の提出は遅れ、テスト勉強は進まず、どんどん成績が落ちてしまいます。
部活の時間、宿題の時間、遊ぶ時間、食事の時間(夕食はなるべく家族でとる)など、スケジュールを決めて、守ることを家庭のルールとしましょう。
なぜスケジュール管理が重要かというと、子どもがスケジュール管理をできなければ、親が「宿題やりなさい」「早くしなさい」と言わなければならず、親子の衝突が絶えなくなるからです。
余計な言い争いを防ぐためにも、自分のマネジメントは自分でできるように指導しましょう。
また、中高生の子どもには向き不向きにかかわらず、身体を動かすスポーツに参加することをすすめてください。スポーツが苦手ならば、ダンスや演劇でも構いません。
身体を動かす活動をしていないと、ストレスを発散する機会を失い、イライラが蓄積してしまうのです。