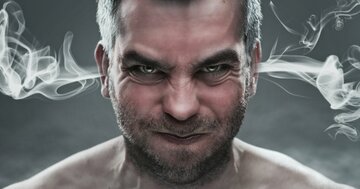「病気になりたくない」というのは、すべての人に共通する願いです。しかし、病気にならないためにどんな行動をとるべきなのかは「よくわからない…」という方が多いのではないでしょうか。
そんななか、「科学的に正しい」健康習慣の身につけ方を明かした、公衆衛生学者・林英恵さんの最新刊『健康になる技術 大全』が話題を呼んでいます。最先端のエビデンスをベースにした「健康に長生きする方法」を伝授する本書に、読者からは「健康関連本としてはブッチギリのベスト」「一家に1冊置いておくべき」と激推しの声が続々と届いています。
本稿では、本書より一部を抜粋・編集して、食の分野で重要な「2つの考え方」を明かします 。
監修:イチローカワチ(ハーバード公衆衛生大学院教授 元学部長)
*書籍『健康になる技術 大全』の「食事の章」はケンブリッジ大学疫学ユニット上級研究員 今村文昭博士による監修
 Photo:Adobe Stock
Photo:Adobe Stock
「食べ物」が原因で亡くなる人が多い
世界では健康的ではない食事が理由で、5人に1人(毎年1100万人)が亡くなっていると考えられています(*1)。
昔は、日本や欧米でも飢餓などの食べられないことが原因で死ぬことが食における大きな問題でした。しかし、現在、先進国では食べられないことで死ぬ人たちは減りつつあり、その代わり、食べることが問題となることが増えています。実際、世界の死因の中で、食べ物が原因で亡くなる人は、たばこについで2番目に多いのです(*1)。
食に対する2つの考え方
日本のテレビや新聞で、「~を食べると認知症に良い!」といったうたい文句で作られている番組や記事をよく見かけます。この手法は、学問の世界では「還元主義・リダクショニズム(reductionism)」といいます。簡単に説明すると、複雑な事象を、単一のシンプルな要素に着目して結論づけることを指します(*2)。
一方、この考え方に相対する考え方が「食の相乗効果・フードシナジー(food synergy)」という概念です(*2)。還元主義に対して、食べ物の組み合わせや、食べるタイミング、食に関する姿勢を含む「食生活に関わるすべての要素の相乗効果」が大事という考え方です。
この考え方を紹介している論文では、還元主義に偏ってしまうことを「1枚の葉(=1つの栄養素や食べ物)を見て森(食全体としての相乗効果)を想像することはできない」と批判しています(*2)。つまり、様々な葉の存在を理解しながらも、森全体をしっかりと見るのがフードシナジーの考え方とイメージすると良いでしょう。
日本では「還元主義」的な情報が多い
これは食についての考え方の違いを表したもので、どちらが良い悪いではなく、両方必要な考え方です(*3)。特定の食べ物や栄養素に着目することは、病気のメカニズム(どのように病気が発症するのか)や栄養素の働きを理解するためにとても大事なことです。
一方で、この視点だけで食事を考えてしまうと、食生活において全体的な食事のバランスを考える、「森を見ること」の視点が欠けてしまう可能性があります。日本のメディアでは、私が知る限り、還元主義的なものが多い印象です。影響を受けすぎてしまうと、「~を毎日食べているので、がんにはならないから大丈夫」といった、極端な発想に陥ってしまうリスクを感じています。
1つの食べ物や栄養素の役割について知識を深めつつ、全体として何をどのように食すれば良いか、本書を通じて理解していただければと思います。
(本稿は、林英恵著『健康になる技術 大全』より一部を抜粋・編集して構成したものです)