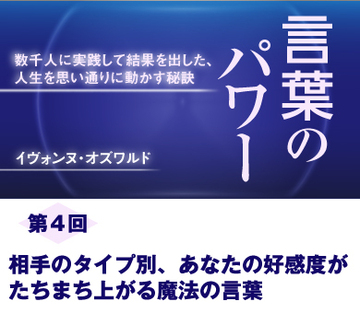僕は仕事中毒だった
最初は、失った時間を取り戻そうとした。子どもたちを学校へ送っていったり、野球の試合を観戦したり、宿題を手伝ったりした。
運動して、体重を落とし、血圧を下げる計画も立てた。エリザベスと一緒に美術館へ行くのも楽しかった。もう何年もそうしたことはしていなかったからだ。
しかし、何週間かたつと、働かないでいることが気になり、いらいらしはじめた。友人たちに再会するどころか、彼らからの電話さえとらなくなった。子どもたちの遊び相手にもならず、昼寝をした。エリザベスと出かけるのをやめ、家に残ってテレビ番組「ロー・アンド・オーダー」の、すでに見たことがあるエピソードをふたたび見た。
朝は十時か十一時までベッドでごろごろしていると、解雇された瞬間や、解雇を決定した人たちのことが脳裏に浮かんでくる。
ポットいっぱいにコーヒーを作り、カップに注いでがぶがぶと飲んだ。そのうち、カフェインのとりすぎで神経が高ぶり、新聞を読んだり、ニュース番組を観たりすることもできなくなった。
働いていないという負い目で頭がいっぱいになり、ゴミを出すときも、隣人に手を振るときも、飼い犬のピップと散歩に行くときも、そのことばかり考えた。
こんな事態は予期していなかったので、次にどんな仕事をしたいかがわからなかったのだ。その事実に狼狽し、これからどうするつもりか、と誰かに訊かれるかもしれないような会話を避けるようになった。
僕は仕事中毒だった。そのせいで、家族をずいぶん犠牲にした。
エリザベスには、もう何年も前からこう言われていた。「あなたはわたしの話をきいてくれない」。
その通りだった。家にいるときも仕事のことを考えていたから、エリザベスが、家事のほかに、子どもたちの世話の八割以上を引き受けてくれていた。だが、あまりに忙しかったために、それに感謝すらしていなかった。
彼女の負担を軽くするために努力するときもあった。ただ、それは、文句を言われず仕事をするために先手を打ったにすぎなかった。
仕事ばかりしていたせいで、子どもたちとの関係はうまくいかなくなっていた。もうすぐ十一歳になるベンジャミンは僕に近づくのを恐れ、彼の双子の妹キャロラインは、ベビーシッターにこう言った。「パパはいつも怖い顔をしてる」。ふたりとも、僕と距離を置きはじめていた。
もうすぐ八歳のノアは、エリザベスと僕が寝ているベッドにもぐりこんできて抱き締めてもらいたがっていたが、それに応えるには書斎のコンピュータの前に座って仕事をするのをやめ、ベッドに寝ていなければならない。
しかし、それはなかなかできないことだった。
仕事のしすぎは遺伝である。父も仕事中毒で、祖父も、曾祖父もそうだった。曾祖父は、リトアニアの農夫で、朝三時に起きて、畑を耕しに出かけたそうだ。
一生懸命働くことが重んじられる世界で、クラヴィッツ一族は誰よりも熱心に働いた。もちろん、一族の男性のほとんどは、六十代前半に心臓発作を起こして死んだ。
ほとんどがわずかな友人しかもたなかったが、怠け者として非難されたことはなかった。クラヴィッツの男たちは、生きるために働き、働きすぎて死んだのである。