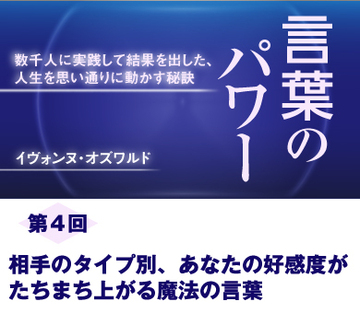段ボールのなかの思い出たち
社会も僕たちの病を深刻化させた。僕が働いた二十年のあいだ、仕事を減らすように言われたことはなかった。たとえ言われたとしても、上司は、残業代を節減するよう上から厳しく命令されただけで、本気だったわけではない。
良い夫、良い父親、良い友人でいたり、地元の教育委員会のメンバーになったり、たとえその権利があるにしても休暇を取ったりしていては昇進できなかった。
昼も夜も働き、仕事を最優先にする社員として認められなければ出世は望めない。子どもの学校の保護者面談に出席したり、携帯電話の電源をオフにしたりしていては、給料も上がらない。
毎朝、上司よりも早く出勤し、昼休みも働く必要があった。週末も、祭日も、休暇も返上し、常に連絡が取れるようでなければならなかったのだ。
リストラされて以来、僕はそうしたことを考えた。これまで仕事に打ち込むあまりに多くのものを失ったことに思い至った。そのため、新しい仕事を見つけるのにあまり乗り気になれなかった。
もちろん、仕事も簡単には見つかるとは思えない。僕は五十四歳だったし、いくら著名な雑誌の編集長であったといっても、雑誌業界は根本的な改革の過程にあり、多くの編集者が職を失っていたからだ。
エリザベスの収入と僕の退職手当を合わせれば、なんとか一年間はやっていけるだろう。その間、再就職のための新しいスキルを学んでもいい。
いや、それよりも、その時間を、自分について、そして自分にとって真に大切なものについて、もっとよく理解して、より幸福で、感謝の心を持った人間になるために使うのはどうだろうか。僕はそうしたいと思った。
しかし、どこから、どうやって始めればいいのだろうか。
その答えは、偶然やって来た。十三年間、職場のクロゼットにあったいくつかの段ボール箱が、郊外の別荘へ届いたときだった。それには、過去四十年間の思い出がすべて詰まっていた。
箱は、マンハッタンの狭いアパートメントには保管場所を見つけられず、職場に置いておいたものだった。それまで別荘に送らずにいたのは、いつも忙しくて、箱のことや、心をかき乱す思い出について、考える時間がなかったからだ。
しかし、いま、僕には時間がある。別荘に一週間滞在し、箱の中身を確認し、これまで積み重ねてきた人生の思い出を整理することにした。その大がかりで厄介な計画は、楽しみでもあり、気が滅入るものでもあった。別荘に残すもの、マンハッタンのアパートメントに持ってくるもの、捨てるものを分けなければならない。
最初の数箱を開けた。当時、かなり慌てて中身を詰め込んだらしい。大学時代のノートやレポートが、中央アメリカの巨大な地図や、銅でコーティングした僕のベビーシューズと一緒の箱に入っていた。
また、一九九二年の共和党と民主党の党大会で集めた記念品は、高校時代のスタジアムジャンパーにくるんであった。
ある箱には、幼稚園時代からの成績表が入っていた。母は、良いものと悪いものに分けて、それぞれをホチキスで留めていた。
友人や、七歳、十一歳、十九歳、二十六歳のときのガールフレンドのリスト、家族が飼っていたペットや母方の祖母やがんで死んだ友人にあてた追悼文も見つかった。
別の箱からは、父の手紙が大量に出てきた。父は、僕が大学生になってから週に一度、手紙を書いて寄こした。カッコや疑問符や強調のための赤字を変わった形で使うのが、父の手紙の特徴だった。
僕は同室の友人と、なにか秘密のメッセージがあるのではないかと何時間もかけて読み解こうとした。しかし、なにも見つからなかった。僕は父の手紙に困惑しつつも、心を動かされたので、すべてを保存しておいたのだ。その箱には、古い野球帽がいくつかと、バリで買ったインドネシアの影絵用の人形も入っていた。
変わったものも、すばらしいものもあった。そして、驚いた。これはみんな封じ込めたり、忘れたりしていた僕の一部分なのだ。
イスラエルのキブツでバナナを収穫したときに使った大型ナイフを見つけたとき、かつて冒険を渇望していた自分を思い出した。ほとんど解読できない夢日記は、まったく金がなく、夜も眠れないほど将来を不安に思いながらも、友人たちの助けでなんとか暮らしていた時代のものだった。