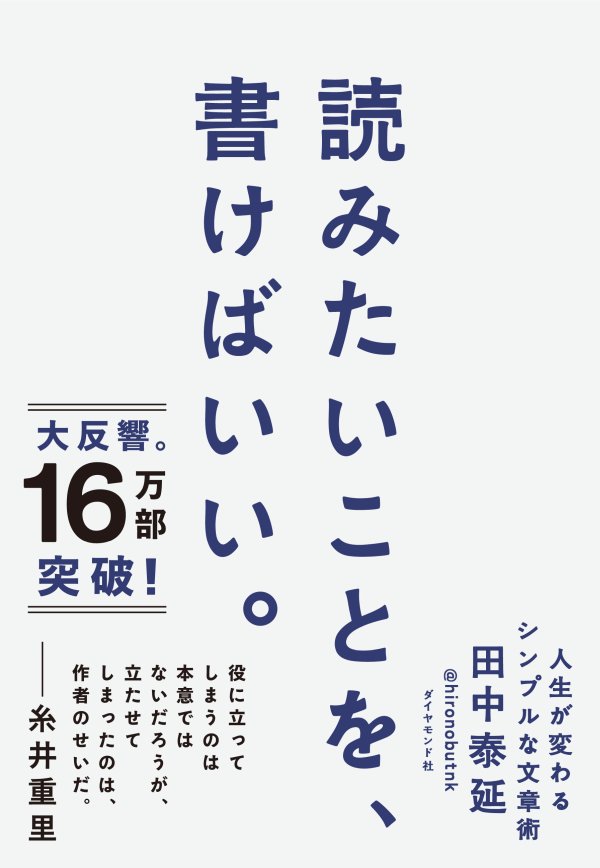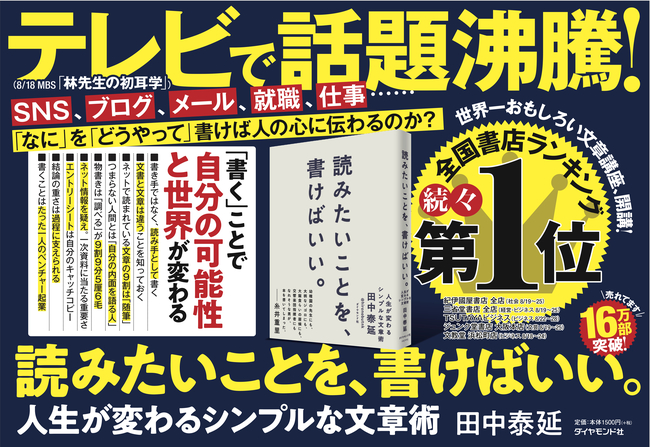古賀 「ここまでやらないと読者は気づいてくれないだろう」と思ってるんですから。そういう文章は、やっぱり読んでいて気持ちのいいものではないと思います。
田中 東海林さんの文章には身体性があると思うんですが、文章の身体性って、いまわたしたちが醤油なしの刺身を想像したように、後からわかることなんですよね。
――なるほど。思い出したときに気づくわけですね。
田中 そして、他人が読んで「あの文章は身体性がある」って言うものです。
古賀 そう。自分で言うことじゃないんですよね。
田中 自分から「身体性がある文章が書けた」って言う人は、面接で「僕にはリーダーシップがあります」って言ってるのと同じです。「いやいや、リーダーシップがあるかどうか決めるのはあなたの周りにいる人じゃない?」と。
もうひとつ、「身体性」と聞いてわたしが思い出すのは、中学生のときにはじめて読んだ宮本輝さんの『錦繍』という小説です。
――男女が往復書簡を交わすお話ですよね。
田中 タイトルの「錦繍」は、色鮮やかで美しい織物や、その複雑な模様のことを指す言葉で、当時は「そういう意味なんだ」くらいにしか思っていませんでした。それから何十年も経って、いい大人になってから秋の紅葉した山々を見たときに突然、「あぁ、これが“錦繍”なのか」とわかったんです。「錦繍」という言葉の意味と、あの文学をはじめて理解できた。さらに後になって、錦繍が「男女の織りなす機微」のことも表しているとわかり、一周回って改めて「本当の着物もそうなってるじゃん!」と気がつきました(笑)。
――だんだんわかるように。
田中 そうなんです。はじめて読んだ10代の頃から、20代、30代、40代と長い時間をかけてちょっとずつ言葉の意味や物語の意味を理解していったわけです。こういう「本当に気づく」みたいな体験は身体性だと思うんですよ。
古賀 すごくよくわかります。僕の場合は音楽でした。中学生ではじめてボブ・ディランの音楽を聴いたとき、まったくわかんなかったんですよ。このお経みたいな音楽の何がいいんだろうって。ジョン・レノンも桑田佳祐も、みんなボブ・ディランを尊敬しているから、そのすごさを自分もわかりたかったんですけど、レコードを何枚聴いても全然わかんない。そのまま20代後半くらいまで過ごしました。
――みんながベタ褒めしているのに自分だけわからないと、疎外感がありそうです。
古賀 はい。それがあるとき、ブートレグ(海賊版)でしか出回ってなかったライブ版のCDが正規版で発売になったんですね。それを聴いてみたら、もう「ダーーンッ!」と、全部わかったんです。自分が客席にいて、ステージにいるボブ・ディランと一本の糸でつながってるような感覚になった。「こんなすごい音楽があるんだ!」というくらい感動して。それ以来、どのCDを聴いてもボブ・ディランのかっこよさやすごさがわかるようになったんです。
――お二人とも、頭で理解するというより、身体的な体験を通して物事を本当に理解する経験をされたんですね。

古賀 そう。だから泰延さんのお話のように、「わからないものにしがみついて、なんとかわかろうとする」という姿勢が、身体性を理解することにつながるんだと思います。
――そうか。身体性というのは受け手の話なんですね。
古賀 今、Amazonレビューとかを見ていると「わからない=つまらない、価値がない」と判断して、切り捨ててしまう人が多いですよね。
田中 ある。めっちゃある。ありまくり。
古賀 それってものすごくもったいないと思います。わからないって、貴重な経験ですから。
――古賀さんは『さみしい夜にはペンを持て』の中でも、「深く考えずに、手っ取り早くことばを決めるのは危険だ」という話を書かれていますよね。
 他者より先に、自分との人間関係を築くための本。『さみしい夜にはペンを持て』古賀史健・著
他者より先に、自分との人間関係を築くための本。『さみしい夜にはペンを持て』古賀史健・著
古賀 はい。「気持ちをことばにする面倒くささに負けてしまった結果、ことばの暴力が生まれる」という話を書きました。わからないものをすぐに切り捨てるのも、それに近いことだと思うんです。わからない悔しさをずっと抱えていられたら、何かの瞬間にふと、わかるときがくる。そういう感覚を知ることが読書のたのしさでもあるんじゃないでしょうか。
(第2回おわり)
第1回 ベストセラーライター2人が語る「AIに取って代わられる文章」の特徴 https://diamond.jp/articles/-/331527