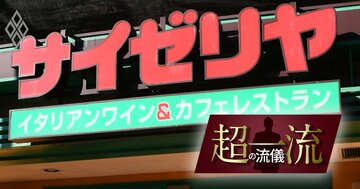このような情報収集を重ねて、最後に取引したいと考えている本命の業者を訪問します。するとその段階では相当なベテランレベルの知識を得ている状態で商談を進められるので、有利な条件での取引が成立します。
最後の商談でも、こちらから情報をひけらかしたり条件を提示したりはしません。黙っていればいいのです。「沈黙はカネなり」ですね。お互いに緊張していますから、ことあるごとに黙ってしまうと、相手がだんだん条件の面で譲歩してきます。
このような交渉の戦術をどこで身に付けたのかと問われることがありますが、もう直感です。自分が仕掛けられたら嫌なことを、相手に仕掛ければよいのだと。つまり、商談とは論戦ではなく、図々しさの出番なのですね。
次々と障害が立ちはだかる山の開墾
米の次はレタスやルッコラ、イタリアンパセリなどの葉菜の生産に挑みます。そこで「自由に使え」と言われた山を活用しようと考えます。標高900メートルから平地までの標高差を利用すれば、オールシーズンの生産体制ができるのではないかと考えます。夏は標高の高い地帯で栽培し、春と秋は平地の露地栽培を行う。そして冬は大規模なハウス栽培を行うのです。このアイデアは、信州の農業を参考にしました。信州の夏レタスは標高千数百メートル級の高地が利用されています。
そこで山の開墾を始めましたが次々と壁が立ちはだかります。まず、数トンサイズの岩の除去が必要でした。すさまじい労力が必要になります。しかも当時の社長からは「その岩は後で城の城壁にするからとっておいてくれ」と言われます。社長は本気でそこに「サイゼリヤ城」を建てるつもりでいたようです。しかしそんな巨大な岩を丸ごと掘り出すことは無理でした。社長は本気で「城を建てろ」と言っていましたが、無視しました。
予算が足りなければ社長に直談判
そのうち、現場がストーンクラッシャーの購入を希望してきました。その名の通り岩を砕く重機で、1台8000万円もします。それだけで予算が使い尽くされてしまいますので、私は社長のところに行って事情を話し、「すみませんが、1本お願いできないでしょうか?」と人差し指を立てて示しました。1億円ですね。
「分かった」。社長は私費で用意してくれたのです。言ってみるものだと思いました。何事も最初から無理だと決め付けないことが私のポリシー、図々しさの出番ですね。
そうして日本に数台しかないストーンクラッシャーを手に入れました。おかげで開墾が一気に進みましたが、使い終わると使い道が無くなりました。それでその後は福島県に貸し出しています。放射能の除染作業に大いに役立ったと感謝されました。