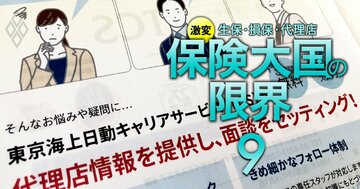Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
ビッグモーター問題で大揺れの損害保険業界に、保険料の事前調整行為、いわゆるカルテル問題が勃発した。行き過ぎたトップラインやシェアを重視する損保業界の構造問題が浮き掘りになった。特集『生保・損保・代理店の正念場』(全31回)の#19では、そのあしき業界慣行を詳述する。(ダイヤモンド編集部編集委員 藤田章夫)
トップラインやシェア重視
悪しき業界慣行が露呈
大手損害保険4社が企業向けの共同保険契約で、独占禁止法違反となる保険料の事前調整、いわゆる「カルテル」を行っていた事案。
2023年12月26日に、東京海上日動火災保険と損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の大手4社が、金融庁から行政処分を受ける事態に陥った。
事の発端は、東急グループの共同保険契約において、22年11月に東京海上の営業担当者が、損保ジャパンと三井住友海上、あいおいの担当者に保険料の事前調整を持ち掛けたことだ。対象となる保険契約は、東京海上が主幹事を務める大企業向けの火災保険の一種、「企業財産包括保険(企財包)」だ。
それと同時に、損保ジャパンが主幹事を務める「企業総合賠償責任保険(賠責)」でも同様に保険料の調整行為が行われていた。
150社超に上るグループ会社を擁する東急だけに、その最大保険金額は2兆円を超える。そのぶん保険料も高額となり、更改前の契約の保険料合計は3年で20億円超。それが補償対象となる物件が増えたため保険金額が増大し、かつ実際に発生した損害額などを加味した結果、新たな契約の保険料は30億円を超える見込みとなっていた。
大幅な保険料増額により、東京海上の担当者は損保3社の担当者とショートメッセージなどで連絡を取り合い、保険料を調整した上で東急側に提示するなどした。ところが、損保各社が横並びの保険料を提示したことに疑問を持った東急側が、再見積もり請求だけでなく、経緯報告までをも求める事態となってしまった。
その結果、3年契約を1年に短縮した入札が行われ、企財包は東京海上が主幹事となり、賠責や利益包括保険などは損保ジャパンが主幹事となって契約更改が行われた。保険料水準は、3年に換算すると2割ほど安くなっている。
これらが東急を巡る一連のカルテルの経緯だが、その後も調査を進めていくと、仙台国際空港や京成電鉄、ENEOSなど疑義のある案件が大量に発覚。金融庁が損保各社からの報告を精査したところ、少なくとも1社の保険会社においては、不適切な行為が行われた企業数は576社に上った。
金融庁は、もはやカルテルは損保業界における構造的な問題だと位置付け、ビッグモーター問題と共に有識者会議を組成し、議論を深めることとした。
次ページでは、第1回の有識者会議でのまとめに加え、カルテル後に行われた東急グループの契約更改による損保各社のシェアの変動について、詳述していく。