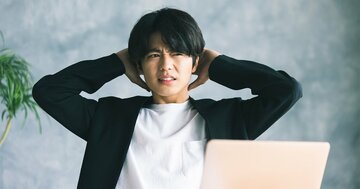「自分にはこれもある」
新しい自分を見つけよう
頭をあげてみるといつの間にか老けた自分がいて、仲は大変いいけれど、もっと奥さんとゆっくり過ごしてもよかったのではなど、未練と後悔の連鎖を覚えたのです。
これは「社会的なアイデンティティー/役割」と「個人的なアイデンティティー/固有性」(※)を混同している部分が大きいと思われます。
(※)…編集部注:アイデンティティーには「社会的なアイデンティティー(social identity)/役割」と「個人的なアイデンティティー(personal identity)/固有性」という概念がある。前者は「役者」に例えられ、「外」から与えられ(託さ)れた役割を基にして振る舞うことが暗黙のうちに求められる(=たとえば、医師は医師らしく振舞わないと、いかに医師として優秀であろうと、患者に大きな不安を抱かせることになる)ため、よく「役者」に例えられる。一方後者は、外部の役割に依存せず、自分自身の選択に基づいたオリジナルのアイデンティティーを意味する。自分で生み出したアイデンティティー(=「個人的なアイデンティティー(personal identity)/固有性」)を通じて生きたほうが、しあわせを手に入れる可能性が高いが、日本社会は「社会的なアイデンティティー(social identity)/役割」を追求する場面が多く、自身の感情を無意識のうちに強く制御する傾向がかなり高い。
Gさんは、まず、ご自身の内面を徐々に打ち明けて、心の苦しみと向き合うことで、身体的な症状が和らぎました。
心の苦しみと向き合いたくないとき、私たちは身体でその苦痛を表すからです。
苦しみを抑圧すれば消えるだろうという無意識的な欲求が働きますが、結局身体の症状がずっと治らない状態になり、長期間で言うと正しい対策とはいえません。
次に、心の苦しみを軽くするために、新しい自分・しあわせな自分を見つけ出す作業が必要だと説明しました。
会社以外での満足が不可欠だろうと推測できたため、配置転換なども選択肢としてありうるのではと話しました。責任の少ない場所に移動すれば、私生活にもっと視野を広げられるからです。
Gさんは配置転換をしてもらい、業務量が激減したことで、プライベートの自分も満喫し、ジムに通うようになり、体に対する自信を少し取り戻しました。
まだ少し、自分が努力の末に手に入れて、結果手放すことになってしまったものに未練が残っている部分もあるものの、それ以上に日々の楽しさを再び感じるようになり、物事をポジティブに考えるようになったのです。
Gさんのケースにおいて、「社会的なアイデンティティー/役割」と「個人的なアイデンティティー/固有性」を混同する恐ろしさがわかるでしょう。特に、この課題に向き合わないまま中年になると、クライシスが生じる可能性があります。
役割の喪失、役割の獲得、どちらにおいても「結局自分は何者なのか?」という問いかけに、苛まれるリスクがあります。
それを避けるためには、複数の役割を育てることが大事なのではないかと思います。
「自分はこれができなければ、これがある」
そうすることで、不均等にリソースを配分するリスクも少なくなり、たとえば身体能力(運動など)とキャリア、またプライベートなどにいくつもの役割を獲得できるため、自信が剥奪されてしまうリスクも低くなるのです。