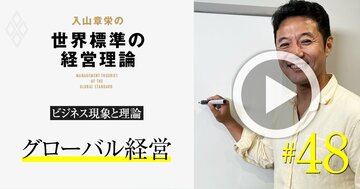モノを所有することの
意味が大きく変わった
ウーバー革命の核心その2:所有の傍流化
ウーバーの社会的なインパクトの持つもう一つの側面は、それがモノを所有することが不要となる方向での革命ということです。
アメリカではウーバリゼーションにより車自体のcollateral(傍流)化が起こっていると言われています。傍流化とはどういうことかというと、たとえば1980年代の日本で、男性が女性にモテるためには、格好のいい車を所有している必要がありました。昔は車を所有すること自体が重要だったのです。
車自体のcollateral(傍流)化ということは、車はそうした所有の対象としての価値を失い、移動という「便益」を得るためには、車を所有する必要がなくなるということです。
車の所有が経済的価値や収入源として再評価されるようになった、ということにもなります。将来、自動運転が一般化すると、車が車庫で眠っている時間はなくなり、24時間、価値を生み出し続ける収入源となるかもしれません。
このように「車が傍流化した」事実を眺めると、車の所有やその利用の背後にある意味や社会の価値観すべてが変わっていることが理解できます。
モノの価値やその役割が変化し、多岐にわたるようになったことを示しています。言い換えると主役は「モノ自体」ではなくなったということであり、モノのもたらす多様な「便益」が分解され、それぞれが経済的価値を生むようになったということです。
地球環境までも見据えた
モビリティサービスの拡大
ウーバリゼーションが進行し、消費者は自動車というモノを所有するのではなく、モビリティというサービスを、必要な場所で、必要なときに、必要な時間だけ調達できるようになりつつあります。
サービスとしてのモビリティが普及すれば、車を所有し自分で運転する必要もなくなります。車の所有は、地球環境に大きな影響をもたらしており、ライドシェアはそれに対抗するための切り札と目されています。