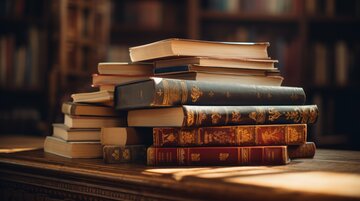「ずば抜けて頭のいい人」が挑戦した“難しすぎる問題”
世界的名著『存在と時間』を著したマルティン・ハイデガーの哲学をストーリー仕立てで解説した『あした死ぬ幸福の王子』が発売されます。ハイデガーが唱える「死の先駆的覚悟(死を自覚したとき、はじめて人は自分の人生を生きることができる)」に焦点をあて、私たちに「人生とは何か?」を問いかけます。なぜ幸せを実感できないのか、なぜ不安に襲われるのか、なぜ生きる意味を見いだせないのか。本連載は、同書から抜粋する形で、ハイデガー哲学のエッセンスを紹介するものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
20世紀最大の哲学者、ハイデガーの挑戦
【あらすじ】
本書の舞台は中世ヨーロッパ。傲慢な王子は、ある日サソリに刺され、余命幾ばくかの身に。絶望した王子は死の恐怖に耐えられず、自ら命を絶とうとします。そこに謎の老人が現れ、こう告げます。
「自分の死期を知らされるなんて、おまえはとてつもなく幸福なやつだ」
ハイデガー哲学を学んだ王子は、「限りある時間」をどう過ごすのでしょうか?
【本編】
「ハイデガーの哲学を学ぶ最初の一歩として、彼が考えた『存在とは何か?』がどういう問いなのか、そこから理解していこう。この問いは、もっと簡単に『あるとは何か?』と言い換えても良い。さて、ここに釣り竿が『ある』。おまえはこれをどういうことだと思う?」
そう言って先生は持っていた釣り竿をいきなり手渡してきた。突然のことにわけもわからないまま、とにかく受け取った竿を握り締めて考えてはみたものの、何も思い浮かばない。
「すみません、どういうことかと言われても……、やはり釣り竿が『ある』としか言いようがないというか……」
超難問! 「存在とは何か?」
「いやいや、それでよい。まさにそれだ。『○○がある、それはどういうことか』と問われて、『そんなこと言われても、あるとしか言えない』というのは正常な反応だ。そして、その答え方こそがまさしくこの問いの本質そのものでもある」
「それが問いの本質? ちょっとまだよくわかりません。とりあえず『ある』を説明するのは簡単そうに見えて、想像以上に難しいということだけはわかりましたが……」
「うむ、あわてることはない。もう少しゆっくりと考えてみるといい」
先生に促され、私はもう一度釣り竿をよく眺めてみた。そして、持っている手から竿の材質や質感を注意深く感じてみる。すると―すぐに、はっきりと―これが「ある」という確信が生じた。
が、にもかかわらず、その確固たる確信の内容を口に出そうとすると、なぜか言葉にならない。どう言葉にしようとしても「あるものはある」としか言えない、そんな言葉の行き止まりに突き当たるような感覚があった。
先生は、こちらをじっと見ていた。決してからかっているわけでも、答えをもったいぶっているわけでもなく、なにか体感的な理解を私にさせようとしているように思えた。
ならばこちらも真剣に考えなくてはならない。
人間の思考には「限界」がある
釣り竿が「ある」、その「ある」とは何か―私は、ふと思ったことを口走った。
「こういうのはどうでしょうか。まず木の棒があって、その先に糸があります。そして、その糸の先には針がついています。こうしたモノが釣り竿で、それが『釣り竿がある』ということではないでしょうか?」
「うむ、それも良い答えだ。実際、古代から多くの識者たちがみなそうした考え方で存在を捉えようとしてきた。なるほど、たしかに釣り竿は、そういう構造をしているし、そうした要素から構成されていると言ってよいだろう。だが、ハイデガーは、そうした存在の捉え方に疑問を呈している。まずそもそも今のおまえの言葉遣いの中に、存在の説明として明らかな破綻が現れているのだが、そのことに気づくだろうか」
「どういうことでしょう?」
「今、おまえは『木の棒がある』と答えただろう? ほら、また『ある』という言葉を使っている。聞かれているのは『あるとは何か』という問いだ。それなのに、その答えの中に『ある』という言葉が出てくるのはおかしなことではないだろうか。たとえば、おまえだって『笑うとは何か?』の問いに、『あははと笑うことです』と答えられたら違和感を覚えるはずだ」
「たしかに、そうですね」
「だから、そうした説明のやり方では、『存在(ある)とは何か』の問いに答えることは原理的にできないのだとハイデガーは主張する。このことをわかりやすく理解するため、おまえが言ったことを端的に文字として書いてみよう」
そう言って先生は懐から紙を取り出し、さっとペンを走らせて書いたものを私に見せた。
釣り竿がある → 竿がある、糸がある、針がある
「どうだろう。こうして書くと一目瞭然ではないだろうか」
「そうですね。結局、『ある』を繰り返しているだけで『ある』そのものについて何も言えていません」
人間の「思考の癖」とは?
「そうだ。これをもっと一般化して考えると、こういうことになる」
Xがある → Aがある、Bがある、Cがある
「いいだろうか。基本的におまえたち人間は、今示した例のように、存在しているモノを、部分に分割しその構造を明らかにすることで理解しようとする思考の癖を持っている。だが、見ての通り、こうした説明では決して『ある』の説明にはならない。
なぜなら、ただ『ある』という言葉を繰り返しているにすぎないからだ。つまり、こうした物事をバラバラに分割して把握しようとする自然科学的な探究方法では、それをどんなに突き詰めようと『存在の謎』を明らかにできる可能性は一切ないということだ」
(本原稿は『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』の第1章を抜粋・編集したものです)