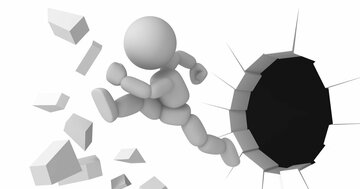音楽そのものだけではなく、演奏者であるバンドや取り巻きたちのスタイル(パンク・ファッション)も、世を騒がせた。ちんぴらっぽい、あるいは世間の良識を嘲笑うかのような「過激」きわまりない装いこそが、まずなんと言っても「パンク」のイメージを決定づけたのかもしれない。
 『教養としてのパンク・ロック』川崎 大助(著)光文社
『教養としてのパンク・ロック』川崎 大助(著)光文社
加えてパンク・ロッカーたちの言動や哲学、作品を彩ったグラフィック・デザインなども、たびたび衝撃を呼んだ。音楽業界なんかはるかに跳び越えて、広い世間において、社会的に、ときには政治的にも物議をかもした。具体的には、イギリスのタブロイド系大衆新聞お気に入りのスキャンダル題材として、パンク・ロックおよびパンクスは、なにかにつけ叩かれることになる。
そしていつしか、「パンク」という言葉は人口に膾炙(かいしゃ)し、前述のような形容詞としても定着していったわけだ。英語圏のみならず、世界中で。ここ日本でも。