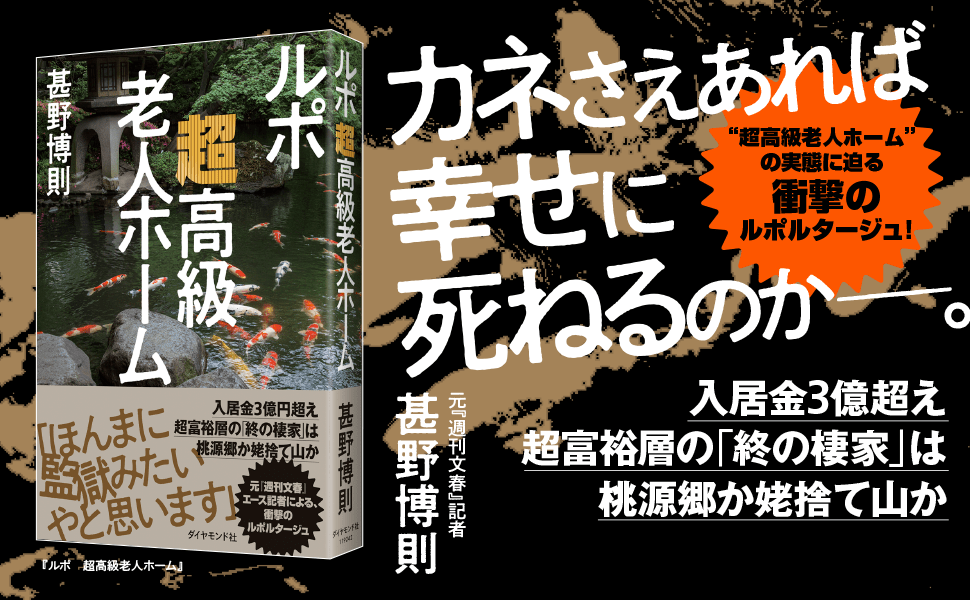「ヤクザとして厳しい」
高齢者が長々と権力者の座に居座るので、認知症を発症する親分はけっこういる。
勇退してもらいたくても、「親分は絶対だ。それがヤクザの掟だ! 親分に従わないのか!」とまくし立てる取り巻きに邪魔され、ボケた親分は死ぬまで居座り続ける。
絶対権力者の周囲には、その威光を利用して私腹を肥やしている腹心がいて、彼らが親分を囲い込むのだ。人によっては若い衆を虐めまくり、搾取の限りを尽くしてきたので復讐が怖く、暴力団を辞められないという事情もある。
もちろん大病をしても辞めない。とはいえ、当事者たちは複雑なようだ。
「例えば脳梗塞になって、身体が麻痺し、リハビリを続けて義理事(暴力団社会の冠婚葬祭)の場に復帰しても、昔のような迫力はなくなっちゃうんだよ。
個人差がでかく、一概には言えないが、ワルどもを束ねるんだから、本音をいえばちょっと無理がある。程度や人によっては、ヤクザとして厳しい」(広域団体幹部)
老害とは本来、「年をとった人が企業の高い地位にいすわって、若返りがさまたげられる状態」(『新選国語辞典』)を指す。
暴力団は構造的に老害に陥りやすいのだ。実際、高齢化が著しい。当人も組織も不幸に見えるのだが、改善する兆しはまるでない。
アラ還組員が「お茶汲み」も
取材でも暴力団の高齢化を実感する。20代の組員をほぼ見かけないので、義理場でたまに見かけると、理由もないのに写真を撮ってしまう。
日常の中でもひしひしと感じる。お茶汲みはどこの暴力団でも見習い・最末端の組員が担当する。イメージでいえば、つい最近まで暴走族だった新米組員だろうか。
ところが某事務所に取材に行った際には、年金を受給できるであろう年齢の組員がお茶を運んできて仰天した。
近くに「おばあちゃんの原宿」と称される繁華街があったとはいえ、好んで高齢者をリクルートはしないだろう。つまり、組員のなり手がいないのだ。
暴力団事務所でこうした下働きをすれば、食事と布団、小遣いくらいはもらえる。考えようによっては、社会の裏側にあるセーフティーネットである。
実際、ここからはみ出しても、刑務所という衣食住+医療費無料の受け皿がある。
存外、表社会より暖かいかもしれない。
1966年、北海道生まれ。日本大学芸術学部除籍。雑誌・広告カメラマンを経て、ヤクザ専門誌『実話時代』編集部に入社。『実話時代BULL』編集長を務めた後、フリーライターに転身。実話誌、週刊誌を中心に、幅広くアウトロー関連の記事を寄稿している。著書は『サカナとヤクザ』(小学館)、『潜入ルポ ヤクザの修羅場』(文春新書)、『ヤクザと原発』(文藝春秋)など多数。