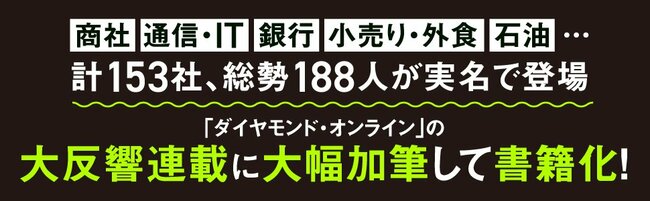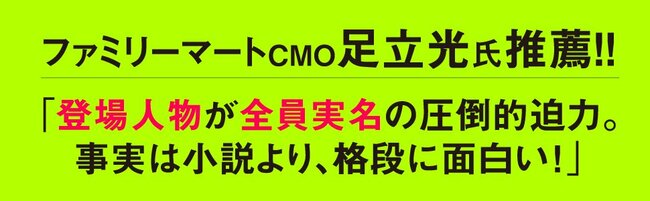Photo:JIJI
Photo:JIJI
日本初の共通ポイント、Tポイントはスタートから丸2年たった2005年秋に最大の危機に見舞われる。中核を担う加盟店のローソンが電撃離脱を表明したのだ。『ポイント経済圏20年戦争』から一部抜粋し、ローソン脱退の舞台裏を明らかにする。(ダイヤモンド編集部)
ローソンがTポイントを電撃離脱
最大のライバル、Pontaを立ち上げ
「何だかおかしいな」。05年初め、Tポイントの加盟店を支援するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)子会社、Tカード&マーケティングの利用推進チームのリーダーだった大野健司は、違和感を覚えていた。おかしかったのはTポイントの主要加盟店であるローソンの担当者の言動である。
大野は、元々は経営破綻した大手百貨店、そごうの出身である。そごうの経営が傾いたときに、CCCが参画した衛星放送事業、ディレクTVに移った。そこでのちにTポイントを考案する笠原和彦と出会う。99年にCCCがディレクTVから撤退すると、笠原の部下として、Tポイントの立ち上げに奔走することになる。
大野は、Tポイントが立ち上がると、新たなミッションを託される。それが、加盟店と連携して、Tポイントの販促策や効果検証を実行する業務である。
二人三脚で販促策などに積極的に取り組む加盟店があった一方で、ローソンのマーケティング部門のマネジャーは、大野にたびたび難題を突き付けてきた。次第に、Tポイントの効果がやり玉に上がる。大野は、データをより丁寧に説明し、販促策にも知恵を絞っていた。半年ほどローソン側の理解を得るべく、四苦八苦を繰り返していた。
05年9月、Tポイントはとてつもない激震に見舞われる。「効果がないので、Tポイントから抜けたい」。大野と面会したローソンのマネジャーが突然そう告げたのだ。離脱通告である。まさに青天のへきれきだった。「ああ、このポイントビジネスは終わったな」。大野は目の前が真っ暗になった。そして、自身のクビも覚悟した。
ポイントビジネスにとって、コンビニ不在は致命的だ。大野がTポイントは終わったと考えたのも当然だった。
オフィスに飛ぶように戻った大野は、即座に笠原に報告する。焦った笠原はすぐにアポイントを入れる。相手は、ローソン社長の新浪剛史である。
「nanaco(ナナコ)が出てくるんですよ」。新浪は笠原らにそう言った。わずか4カ月前に、セブンを傘下に持つセブン&アイ・ホールディングスが流通業界では初となる電子マネー、nanacoを翌春からスタートさせる方針を大々的に表明したばかりだった。
新浪は最大手のセブンの動きを極度に警戒していた。そして、ローソンパスという自社ポイントの強化に軸足を移したい旨を説明した。結局、笠原らは新浪を翻意させることはできなかった。
なぜローソンはTポイントを離脱する道を選んだのか。当時のローソン幹部はこう打ち明ける。「自社でデータを持てないことが大きかった」。実際、ローソンの利用客の購買データはCCCが保有し、ローソンは思うままに使うことができなかったのだ。
ただし、本当の答えを、笠原や大野は後に知ることになる。
Tポイント脱退から2年半後の09年10月、ローソンは同社の株式の3割を保有する三菱商事と新たな共通ポイント、Ponta(ポンタ)を10年春に立ち上げると発表した。Tポイントにとって最大のライバルが誕生したのだ。しかも、主軸はローソンである。
ポイント事業を運営するロイヤリティ マーケティングは、08年末に三菱商事の子会社として発足していた。Tポイントからの脱退は、三菱商事やローソンが新たなポイント経済圏の構築を見据えた「初手」だったのだ。
実際、当時のローソン関係者によると、「CCC側から『もうやめてほしい』と言ってもらうように」という指示が幹部から現場に下ろされていたという。大野が半年にわたって無理難題を突き付けられたり、効果を疑問視されたりしたことにも合点がいく。
Tポイントはローソンの電撃離脱によって、立ち上げ以来、存亡の機を迎えることになる。笠原は、ローソンが抜けた穴を補うべく、新たなパートナー探しに駆けずり回ることになる。(敬称略)