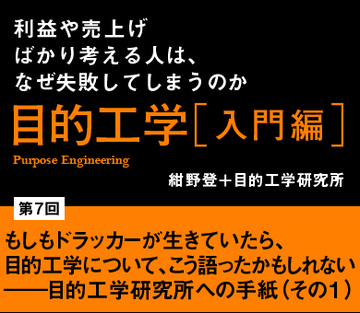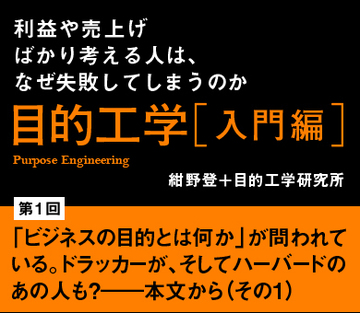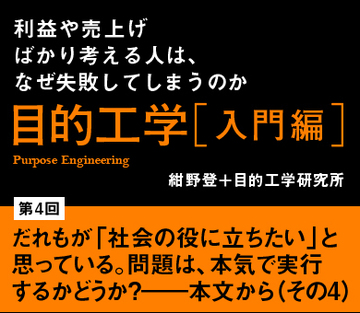「世のため人のため」の価値観は
日本企業の持続力の源泉のひとつ
野中 今おっしゃった企業の社会的責任ということに関連して、ちょっとおもしろいエピソードがあります。最近、うち(一橋大学)の大学院で「One Asia」というプログラムをやっていて、中国、韓国、日本の企業に関する比較研究を始めているのですが、その中で国営企業も含めた中国企業の幹部を日本に呼んで、日本企業のトップと話をしてもらう機会がありました。
そうすると、彼らは一様に驚く。日本のトップはみな「共通善、コモングッド」――要するに「世のため人のために事業している」――というような話をするが、あれはいったい何なんだ、と。
これは我々日本人からすると当たり前過ぎて気づかないようなことなのだけれども、外国人にしてみたら、不思議でしょうがない。中国経済の原動力は華僑に象徴されるような、ネットワーク・キャピタリズムです。それによって急速に経済発展する一方、国営企業と民営企業の間に歴然とした差があったり、国民の所得格差も社会問題になっていたりします。
韓国にしてもそう。あれは言うなれば「財閥キャピタリズム」でしょう。国内からも、財閥は栄えても国民は、という批判もあるようですから。
そんな中、「日本企業の持続力を可能にしている要素はいったいなんなんだ?」というテーマが改めて注目され、中国・韓国の企業からも高い関心を集めるようになっています。海外から来た人たちの目で改めて日本企業のあり方を見直すと「ああそうか、日本企業はだから長く生き延びて来られたのか」という発見がいくつもある、と言うんです。
 紺野登(こんの・のぼる)
紺野登(こんの・のぼる) 多摩大学大学院教授、ならびにKIRO(知識イノベーション研究所)代表。京都工芸繊維大学新世代オフィス研究センター(NEO)特任教授、東京大学i.schoolエグゼクティブ・フェロー。その他大手設計事務所のアドバイザーなどをつとめる。早稲田大学理工学部建築学科卒業。博士(経営情報学)。 組織や社会の知識生態学(ナレッジエコロジー)をテーマに、リーダーシップ教育、組織変革、研究所などのワークプレイス・デザイン、都市開発プロジェクトなどの実務にかかわる。
紺野 90年代アメリカでかつて起こったことと同様の動きが今、リーマンショック以後のアジアで起きている、と考えてみてはどうでしょう。
振り返ると、野中先生が日本企業の製品開発をコンセプト化してまとめた「知識創造理論」は90年代にアメリカで評価され、世界中に広まりました。それ以前の80年代、アメリカ企業は日本企業に軒並みシェアを奪われそうになり、「これではまずい」と真剣に日本企業のあり方を研究したんですね。
その時に、ちょうど野中先生が発表されていた「現実のイノベーションは暗黙知と形式知のスパイラルアップによって起こる」という知識創造の理論とそれをモデル化した「SECIモデル」を知り、形式知一辺倒だったアメリカ企業が暗黙知の重要性を認識していった、という流れがあったかと思います。
野中 アメリカの近代経営学は「経営は科学である」という考え方が主流を占め、人間の主観を扱うなど科学的経営学のすることではない、という風潮もありました。実際、駆け出しの頃の私の研究に大きな影響を与えたハーバート・サイモンも、そうした考え方の持ち主でした。
彼は人間の持つ情報処理能力には限界があり、それゆえ完全に合理的にはなれない、と考えた。したがって、経営における意思決定から人間の価値判断を除いてしまえば、判断しなければならない範囲が限定され、合理的かつ科学的な判断ができるはずだ、と主張した。
紺野 そうした考え方に基づくと、組織は人間が合理的判断をするための単なる装置に過ぎなくなってしまい、そこで働く人たちの人間性は無視されてしまいます。つまり、組織がどんどん非人間的にもなっていく。
野中 そう、それが大きな問題です。しかし今、彼らが排除した価値判断こそが経営にとって必要な時代に入ってきた。つまり「何のためにビジネスをしているのか」ということが問われるようになったのです。そこであらためて注目されるようになったのがアリストテレスの目的論であり、ピーター・ドラッカーの指摘した「企業は社会的機関である」という考え方だと思います。