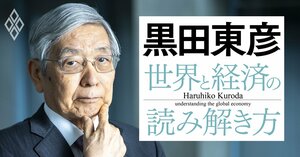Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
空の旅で楽しみなのが機内食。ANAやJALの国際線では日本人好みの趣向を凝らしたもの、外資系エアラインではお国柄や各社の特徴を生かしたメニューが提供されている。航空業界の発展と共に進化してきた機内食の歴史を振り返ってみよう。(ライター 前林広樹)
黎明期:世界初の機内食は100年以上前!
機内食の登場は、なんと100年以上前にさかのぼる。1919年、ハンドリー・ページ・トランスポート社(現:ブリティッシュ・エアウェイズ)が英ロンドンから仏パリに向かう旅客機の中で、サンドイッチとフルーツ、チョコレートを有料で提供した。これが歴史上、飛行機で最初に提供された機内食である。
その後1930年代になると、航空機の大型化に伴い、ギャレー(食事を用意するスペース)がダグラスDC-3で導入された。コーヒーや紅茶を温かいまま提供できるようになったのは画期的だった。
なお、日本で最初の機内食は諸説あるが、1930年代に東京の鈴の森海岸から伊豆半島の下田を経由し、静岡県の清水までの飛行機で出された軽食や紅茶だと言われている。
そして本格的な機内食は、1951年にJAL国内線の初便(東京〜大阪〜福岡)で提供された、ボックスサンドイッチと紅茶・コーヒーとされる。
このサンドイッチはどこで作られ、どのようにして運ばれたのか。
※次ページで貴重な写真を公開!