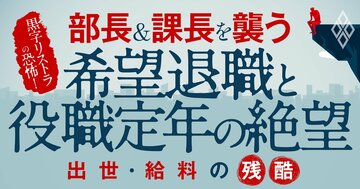「髪の毛がたくさんあったおかげで、頭皮はなんとか助かった。髪はご覧の通りボロボロになっちゃったけど、避難所で誰かに見られる心配をしている余裕もないし、綺麗な格好をしている必要はないから」
 サンタモニカの消防署にバイデン大統領の車列が到着 Photo by M.Nagano
サンタモニカの消防署にバイデン大統領の車列が到着 Photo by M.Nagano
そう言いながらも、燃え残った髪の毛を髪飾りでまとめていた。
同じパリセーズから避難してきた同年代のフランソワーズさんは、昼寝をしている間に、火の手が自宅の裏庭にすでに迫っていたという。慌てて愛犬を抱えてサンダル履きで杖をつきながら車に飛び乗って逃げた。所持品は何ひとつない。「常備薬すら持ち出せなかった」と彼女が言うと、ジュリアさんも「私も皮膚癌の薬を忘れてきた」と言う。
「パリセーズの住民は全員が富裕層だと思われているけど、私は金持ちなんかじゃない。街のハードウェアストアで働いていたぐらいだし」とジュリアさん。
途方に暮れる避難民たち
「ノート1冊、ペン1本持ち出せなかった」
 避難所のジュリアさん(左)とフランソワーズさん(右) Photo by M.Nagano
避難所のジュリアさん(左)とフランソワーズさん(右) Photo by M.Nagano
ジュリアさんもフランソワーズさんも独身で、これから自分たちの力で再建するしかない、と語る。「保険のこと、書類のこと、いろんなことをひとつひとつ書いて記録していかなきゃいけないんだけど、ノート1冊、ペン1本持ち出せなかった」とフランソワーズさん。筆者が記者用の小さなノートを手渡すと「ありがとう」と言い、ふたりで赤十字が配布する毛布を取りに行った。
避難してきた人たちの多くは、極限状態の中を命からがら逃げて来た。ショック状態にある上、仕切りがない避難所で夜眠ることは難しいだろう。ジュリアさんは「昨夜は10分ぐらいうとうとした程度」と言う。それでも皆驚くほど礼儀正しく、お互いを思いやり、シャンプーを手渡すボランティアの大学生たちの呼びかけにも応えていた。
赤十字ボランティアのまとめ役のカーメラ・アン・バークさんはボランティア歴30年以上で、数々の火災の避難民の世話をしてきた。「私たちの一番の使命は、避難民のお腹がすかないようにすること。3食提供して、それ以外にもたくさんの食糧を用意している」と言うとおり、避難所の入り口には地元の住民が寄付したパンや果物やクッキーなどが山積みになっていた。
サンタモニカ市内の避難命令が出た地区に住む女性、ガブリエラさんは「避難所に来てからほとんど眠れない」と言う。それでも車を持っていない彼女にとって、自宅が火災に巻き込まれる前に、簡易ベッドがある場所に避難できたことはラッキーだと言える。