食堂車はなくなり
車内販売も多くが廃止に
もうひとつ利用形態の変化を示すのが供食サービスの在り方だ。1986年時点では、東海道新幹線は一部の臨時列車を除くすべての「ひかり」が食堂車またはビュッフェを連結していたが、定員が減少する上、高速化の妨げになるため、新型車両では廃止され2000年までにサービスを終了した。
ふだん利用しない人にとって食堂車は特別な体験だが、頻繁に利用する人の目からみれば割高で、そこまでおいしいものではない。それに加えて、自由席に座れなかった人が食堂車に居座るなどの問題もあり、当初の役割を果たさなくなっていた。
さらに2000年代以降、駅構内に専門店が並び、ホーム売店のコンビニ化が進む。多種多様な飲食物を安価に購入できるようになると、いつ来るか、商品が残っているかも分からない車内販売は存在感を失い、その多くが廃止されている。
もちろんこれらはひとつの見方に過ぎない。駅員など係員の大幅削減やローカル線の存続問題などサービス縮小の懸念がある事は事実だし、都市部・新幹線を中心とした増発や速達化、車両の刷新、バリアフリー化の促進など改善された部分も大きい。
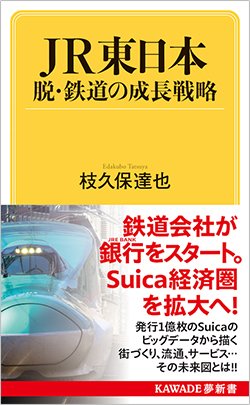 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
重要なのは「国鉄かJRか」ではなく、鉄道サービスの在り方は経営環境の変化で常に変化するということだ。長距離輸送だけでなく、議論が進むローカル線の存続問題も、そのひとつと言えるだろう。
昔から「企業の寿命は30年」という真偽不明な説があるが、実際に日本の鉄道は1872年の官設鉄道新橋~横浜間開業から1906年の鉄道国有法成立までの34年、それから日本国有鉄道成立までの43年、国鉄の37年と、概ね40年前後の間隔で体制を転換してきた。
ローカル線の存続問題、人口減少社会における需要縮小、人手不足など今後、鉄道の経営環境は急速かつ劇的な変化を迎える。JRの歴史が国鉄を超えた今、次世代の鉄道サービスの在るべき姿、そして「ポストJR体制」の議論が求められているのではないだろうか。







