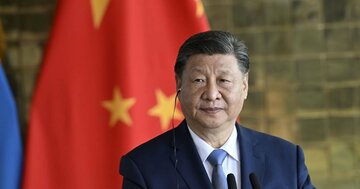矢継ぎ早に関税を発動するも
法人税率引き下げと規制緩和は不透明
政権発足直後、トランプ氏は海外進出した米国企業や海外の企業に対して、「法人税率が低下する米国で製品を製造してほしい、さもなければ高い関税を負担せよ」と選択を迫った。関税と法人税率引き下げの組み合わせで、海外企業の米国での投資を増やすことを目指している。
鉄鋼からAI(人工知能)チップまで、米国を世界最大、最強の製造大国に育て上げ、経済成長を加速させる。それが、トランプ氏の基本的な経済運営の発想だ。
企業の事業運営をサポートするために、シェールガス、オイルの生産増加のための規制緩和も進めると表明した。個人消費の底上げに、2017年の個人所得減税の恒久化も公約に含めた。
トランプ氏は、インフレの芽を摘むため原油価格の引き下げも重視。サウジアラビアに原油価格を下げるよう求めた。実際に原油価格が下がれば、米FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げも可能というのがトランプ氏の主張だ。
金利低下に関して、ベッセント財務長官は長期金利(10年国債の流通利回り)を注視しているという。長期金利が低く抑えられると、企業の設備投資意欲を刺激することができるからだろう。
関税以外の政策で、今のところ変化があったのは原油価格だろう。トランプ大統領がプーチン大統領と、ウクライナ戦争の停戦交渉開始で合意したことが伝わると、ロシアからの原油供給が増えるとの観測から、WTI原油先物価格は70ドル/バレル台に下落した。
シェールガスの増産は、デジタル技術の活用で生産性が高まったとみられ、増産への期待感はある。一方で、現時点で稼働していないシェールガス田の生産コストは高く、規制緩和してもガスや石油の増産は難しいとの見方もある。トランプ氏が描く、エネルギー価格の下落の実現は簡単ではない。
肝心の法人税率の引き下げについては、トランプ政権はまだ踏み込んだ内容を示していない。トランプ氏は1期目の政権発足直後と異なり、減税よりも、関税政策を打ち出した。鉄鋼や自動車に加えて、半導体や医薬品にも追加の関税を適用する考えのようだ。
他方、相変わらず批判の的となることも多い。カナダを51番目の州にするとの発言は、米国の信頼感を毀損(きそん)したと報じられている。今のところ、トランプ氏の政策は米国経済の成長よりも、世界経済の不確実性を高める方が多いだろう。