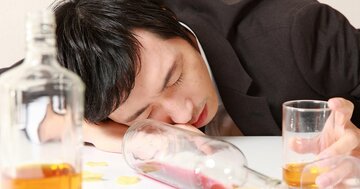しかしこの感冒薬には、肝毒性のある成分が含まれていたため、過量服薬をくりかえすなかで重篤な肝機能障害を呈する子どもも出てきました。
こうした事態を受けて、2023年4月からこの感冒薬もようやく販売個数制限の対象となりましたが、「ときすでに遅し」でした。というのも、乱用者のあいだではブームはすでにメチルエフェドリン・ジヒドロコデイン含有製品から別の製品へと移っていたからです。いま子どもたちが夢中になっているのは、デキストロメトルファンという鎮咳成分が含有される市販薬です。
このデキストロメトルファン、確かに依存性はジヒドロコデインよりも弱いですが、大量摂取すると幻覚薬ケタミンと類似の薬理作用を発揮し、幻覚を惹起します。また、柑橘系果汁との相互作用で、予期せぬ血中濃度の上昇を起こし、すでに死亡事例も発生しています。
一般に薬物規制をむやみに強化すると、闇市場が繁盛するとともに、以前よりも危険な薬物が流通するようになります。
危険ドラッグ使用による
死亡者数や交通事故被害者が増加
1920年~33年に米国で実施された禁酒法がそうでした。その時期、短時間の隠れ飲みで十分に酔えて、しかも輸送効率もよいことから、流通するのはもっぱらアルコール度数の高い蒸留酒となりました。また、ギャングたちが密造する酒なので品質にも大いに問題があり、有害な工業用アルコール含有製品が出回ってしまったのです。
今日の北米におけるオピオイド・クライシス(編集部注/麻薬性鎮痛薬の過剰摂取による急性中毒が社会問題化している状況)もそうです。
最初は、製薬メーカーの不適切な広報・営業によりオキシコンチンという処方薬オピオイドから拡大しはじめ、オキシコンチンの処方規制を行うと、依存症に陥った人々はやむなく違法なヘロインを乱用するようになりました。さらに、違法ヘロインの取り締まりを強化すると、今度は、再び処方オピオイドそれもヘロインの50倍もの強さを持つフェンタニルへとエスカレートしていったのです。
実は、わが国もすでに同じ失敗をしています。危険ドラッグ対策がそうです。最終的には販売店舗を一掃して鎮静化に成功したものの、そのプロセスでは、規制強化を進めるたびに、危険ドラッグ使用による死亡者数や交通事故被害者が増加していきました。同じ轍を今度は市販薬で踏まないことを願うばかりです。