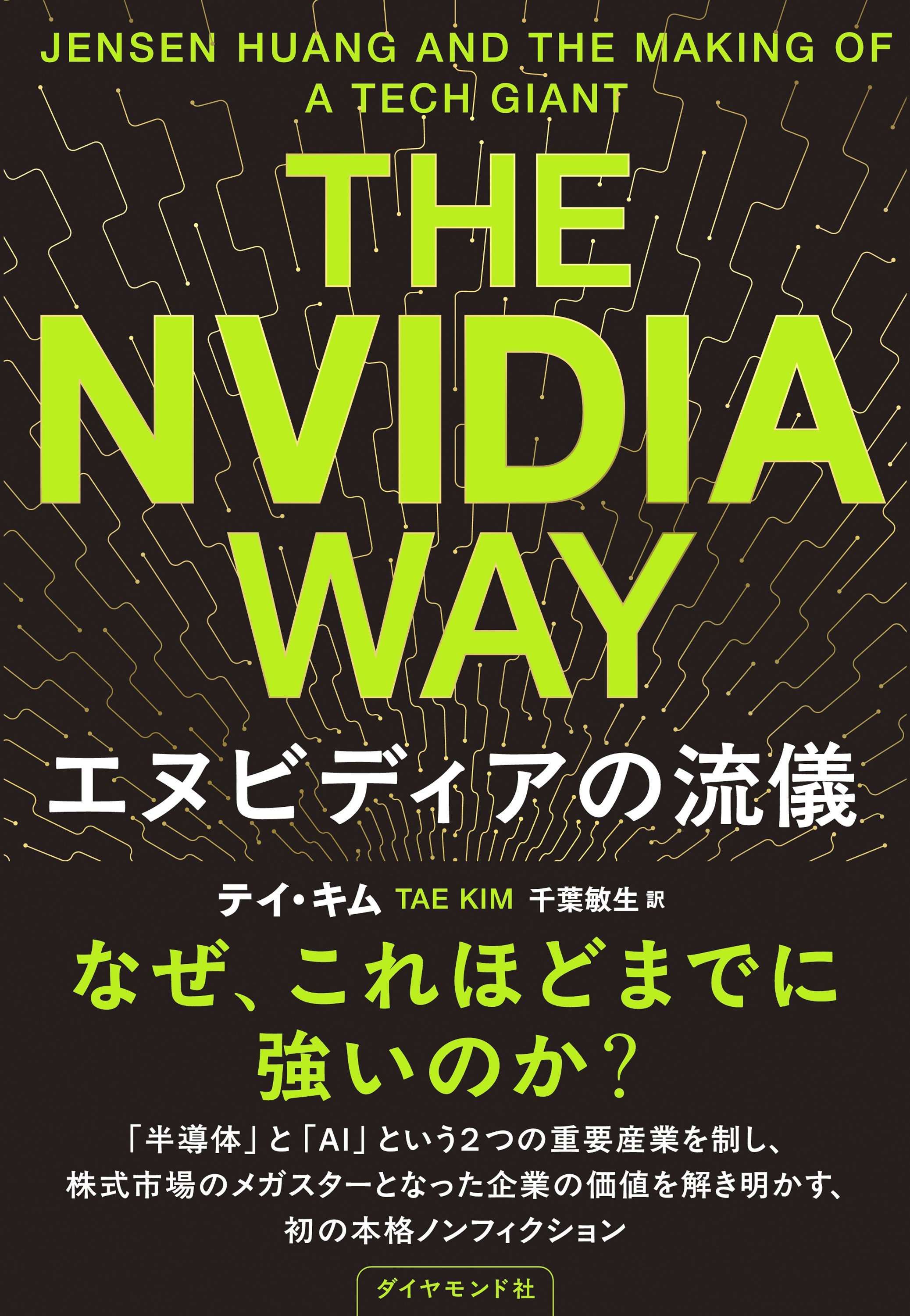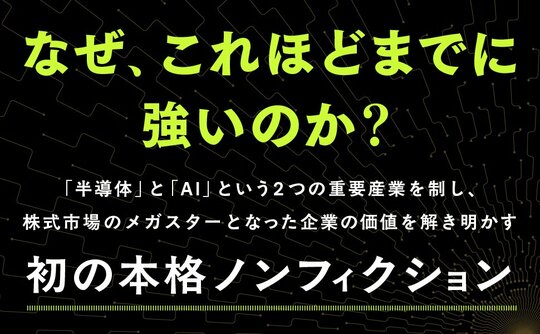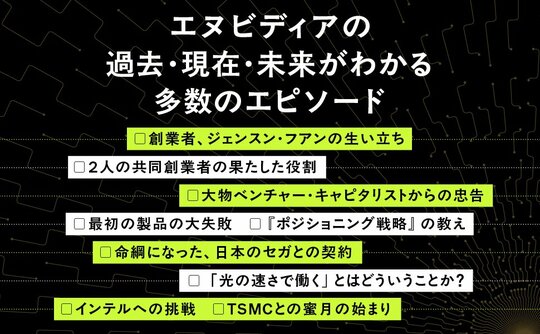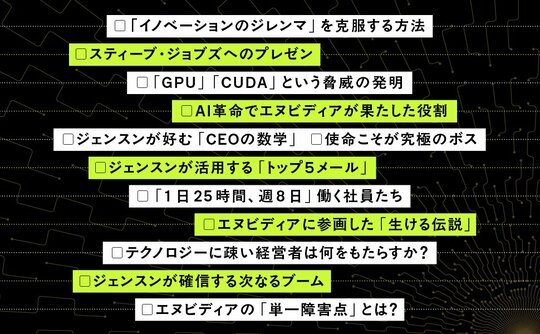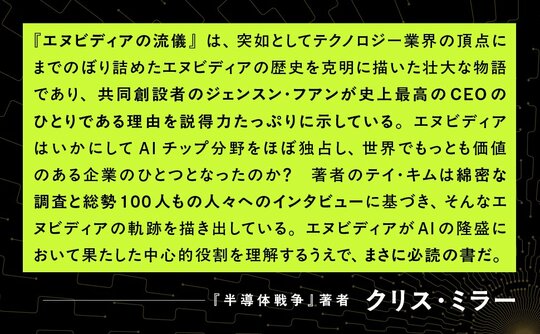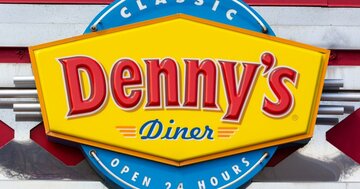アップル、マイクロソフトと世界の時価総額ランキング1位を争い、誰もが知る企業となったエヌビディア。「半導体」と「AI」という2つの重要産業を制し、誇張ではなく、米国の株式市場、そして世界経済の命運を握る存在となった。
しかし、その製品とビジネスの複雑さから、エヌビディアが「なぜ、これほどまでに強いのか?」については、日本でも世界でも真に理解されているとは言えない状況だ。『The Nvidia way エヌビディアの流儀』は、その疑問に正面から答える、エヌビディアについての初の本格ノンフィクションである。
今回は同書より、エヌビディアの企業文化と、創業者ジェンスン・フアンの価値観を端的に表すエピソードを紹介する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「私は毎回1位じゃなきゃ気がすまない上司のもとで働いているのだ」
ときには、エヌビディアのスピードへのこだわりが品質の低下につながることもあった。少なくとも、ジェンスンが自社に課した高い基準と比べれば。
コーポレート・マーケティング部長のアンドリュー・ローガンは、エヌビディアのあるチップがコンピュータ雑誌の賞で2位に甘んじたときのことを覚えている。彼の元勤め先であるS3の幹部たちなら、自社製品がトップ3に入っただけでも大喜びするだろう。エヌビディアでは違った。
「初めて2位になったとき、ジェンスンがきっぱりと言ったんだ。2位は最初の敗者だと」とローガンは言った。「あの言葉は忘れない。そのときに気づいたんだ。ああ、私は毎回1位じゃなきゃ気がすまない上司のもとで働いているのだ、と。とてつもないプレッシャーだったよ」
いかなる基準で見ても、RIVA128は優秀なチップだった。高解像度のグラフィックスを競合他社よりもずっと高いフレーム・レートで描き出すことができたし、『クエイク』のようにビジュアル面で高い性能が求められるゲームも、遅れが生じることなく最高品質で動作した。おまけに、史上最大のチップだったにもかかわらず、初期の需要に応えられるくらいすばやく生産することもできた。それでも、チップをタイムリーに発売するためには一定の妥協が不可欠だった。RIVA128は煙や雲といった一部の種類の画像を描き出すのにディザリングを用いていた。ディザリングとは、一種の意図的なノイズを加えることにより、視覚的に不規則な部分を目立たなくする技術のことだ。
多くのゲーマーがこの問題に気づいたため、ある主要PC雑誌がエヌビディアの主力グラフィックス・チップに関する暴露記事を掲載することを決めた。エヌビディアのRIVAシリーズが描画した画像と、3dfxやレンディション社の現世代の同等のカードが描画した画像を、見開きページに大きく並べて比較したのだ。エヌビディアの画像はぼやけてにじんでいた。結局、その雑誌はエヌビディアの画像を3つのなかの最下位に評価し、「ひどい見た目だ」と評した。
記事を見るなり、ジェンスンは数人の幹部を自室に呼んだ。テーブルにはその雑誌の特集号が開いて置かれてあった。彼はRIVA128の出力画像がこれほどひどい理由を問いただした。主任科学者のデイヴィッド・カークは、チップをスケジュールどおりに完成させるため(そして会社を救うため)、画質の面で一定の妥協を行なったためだと答えた。その答えを聞くと、ジェンスンはいっそう激怒し、ひとつの指標だけでなくすべての指標で他社のチップを上回るよう厳命した。
あまりに大声での怒鳴り合いが繰り広げられたので、ウォルト・ドノヴァンは気になってしょうがなかった。コンピュータ・ゲーム開発者会議(CGDC)でRIVA128のデモを見て、その場でエヌビディアに入社の希望を出した例のチップ・アーキテクトだ。彼はエヌビディア本社のなかでも、ジェンスンの執務室とは正反対の場所で働いていたため、ジェンスンのお小言はほとんど届かない距離にいた。おまけに、彼は両耳に補聴器を着けるほど重度の聴覚障害を抱えていた。しかし、今回は無視できないほどの騒ぎだったので、みずから議論に加わった。
ドノヴァンは、エヌビディアの次世代チップ、その名も「RIVA TNT」シリーズでは、ディザリングの問題が解決するばかりか、グラフィックス品質のどの指標においても業界の最先端を行くものになる、とジェンスンをなだめた。そして、雑誌が3社のなかで最高だと評価したレンディション社の画像を指差した。
「RIVA TNTの画像はこんなふうになると思います」と彼は言った。
それでも、ジェンスンの怒りは収まらず、彼はひとりきりにしてくれと言わんばかりに叫んだ。「出ていけ!」