血圧上昇の程度が、朝よりも夕方のほうが大きいことに注目してください。
すなわち、心筋梗塞や脳卒中などの血管に起因する病気が、朝だけでなく夕方にも多い1つの理由は、血圧のイブニングサージの存在でした。
さらに最近では、病気の発症が夕方にも多い理由として、サーカディアンリズムやサーカセミディアンリズムとは別に、約8時間のリズムの関与も注目されています。
約8時間のリズムは、ラテン語で「8」を意味する「オクト」を用いて「サーカオクトホーランリズム」とよばれ、人の睡眠時間が約7.5時間であることに由来するリズムであると考えられています。詳細はまだ十分にはわかっていません。
「月曜日」や「冬」も
病気になりやすい“魔”の時間
病気が発症するタイミングの背景として、サーカディアンリズムやサーカセミディアンリズム以外にも、約7日のリズムや約1年のリズムが報告されています。
心筋梗塞後の狭心症の発症タイミングに約7日のリズムがあり、週末、または月曜日に多いことや、心筋梗塞に起因する心臓死に約1年のリズムがあり、6月から9月に比べて、12月から1月に33%も多いことなどが報告されているのです。
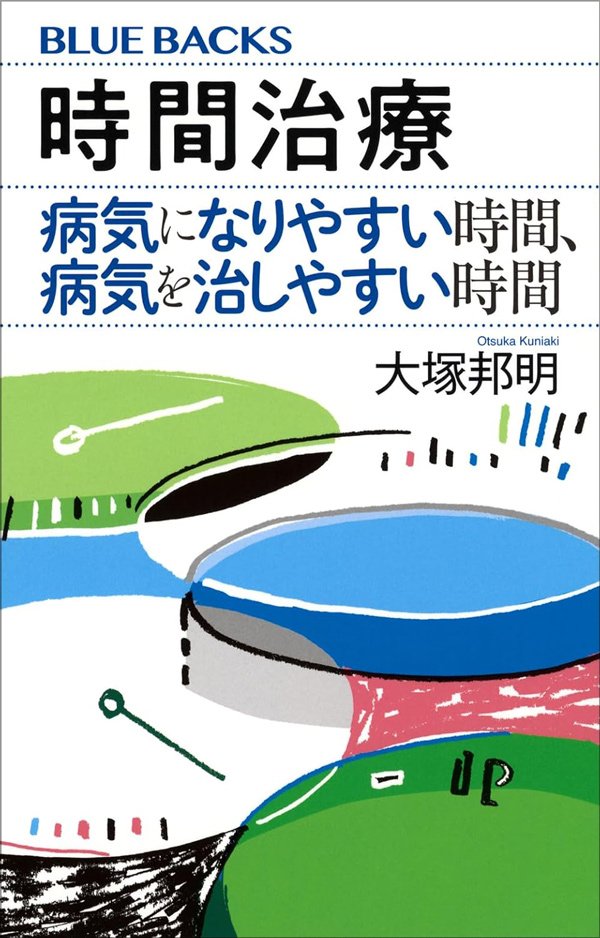 『時間治療 病気になりやすい時間、病気を治しやすい時間』(大塚邦明、講談社)
『時間治療 病気になりやすい時間、病気を治しやすい時間』(大塚邦明、講談社)
血液の溶けやすさ(線溶能)にはサーカセプタン(約7日)リズムがあり、月曜日に血液が溶けにくくなることが、狭心症が月曜日に多いことの原因かもしれません。また、血液の固まりやすさ(凝固能)にはサーカニュアル(約1年)リズム(概年リズム)があり、冬季に血液が固まりやすくなることが、心臓死が12月から1月に多いことの一因とも考えられます。
自律神経やホルモンのはたらきに約7日のリズムや約1年のリズムがあり、その影響で病気になりやすい時間帯にも約7日のリズムや約1年のリズムが現れると考えられていますが、その詳細はいまだ十分には明らかにされておらず、これからの研究に俟ちたいと思います。







