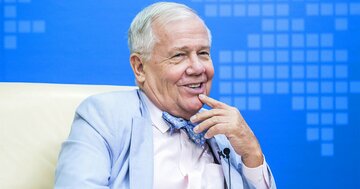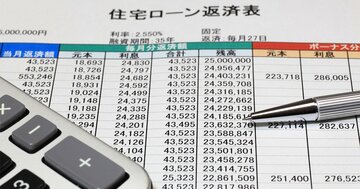1億円で購入した不動産が翌日に2億円で売れるといった状況が続いたため、多くの不動産業者がこぞって不動産を売買した。そして、個人の投資家もその輪に加わった。
個人投資においては不動産マーケットだけでなく、軒並み好調な日本企業への株式投資も活発化した。私から言わせるとほとんど知識のない、素人のような投資家までもが、株で大儲けする状況が続いたのである。
美術品も投資の対象に
企業も投資家も名画を買い漁る
美術品への投資も活発だった。大手損保会社がゴッホの名画『ひまわり』を53億円で購入したことは世界を驚かせた。ピカソやシャガールといった他の有名な芸術家の作品も、バブル経済の時期に日本の企業や投資家が買い漁った。
しかし、バブル経済は中身を伴わないものだ。政府は金融機関に対して、不動産を購入するための融資の総量を規制するとの通達を行い、借り過ぎや貸し過ぎを防ごうとした。
日銀も政府の動きと合わせるかのように、段階的に公定歩合を引き上げることで、融資が受けづらい状態をつくる金融対策を取った。FRBの優秀な議長、ウィリアム・マーティンの金融引き締め政策である。
政府や日銀の政策により、企業や個人は以前と比べて融資を受ける数が減り、並行して投資意欲も低下した。しかしその結果、不動産や株式の価格は暴落し、大損をする人があふれた。正確には、正しい金額に戻っただけなのだが。
マーティンのアメリカのように、日本はその後、好景気となることはなく、現在に至るまで景気が回復しない、失われた30年を経験していくことになる。アメリカと日本では、何が違っていたのか?
日米両国の明暗を分けたのは不良債権処理のスピードだと私は見ているし、多くの専門家も、そのように考えている。実は日本のバブル経済が崩壊したのと同じ時期に、スウェーデンでも同様の現象が起きていた。しかし、スウェーデンは不良債権の処理を迅速に進めたことで、5年ほどでバブル崩壊から立ち直っている。
ゼロ金利も量的緩和も効果なし
「異次元の金融緩和」はどうか?
一方で、日本は不良債権の処理に15年もの年月を要した。不動産を担保としていた銀行の不良債権の出所が不確かであったこと、どこの銀行が潰れるか、人々が疑心暗鬼となったことが、処理スピードを遅らせた要因だと言われている。
さらに、処理に時間がかかったことが、人材育成などその他の経済活動にも悪影響を及ぼした。不良債権処理にこれだけの時間がかかった要因は、政府や日銀の対応の遅れやその内容だと私は考えているし、多くの識者がそのような見解を持っている。