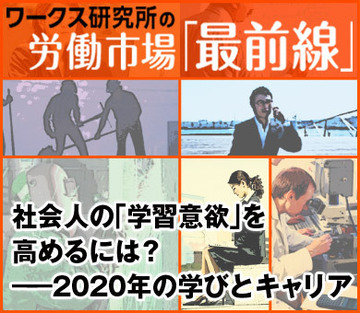提出必須な「研究計画書」とは何か?
誰もわからなかったその意味と重要性に着目
筆者が大学生だったのは1970年代後半でした。「大学院へ行こうかな」と一瞬脳裏をよぎったことはだれにでもあるでしょう。入試問題を見ると、だいたいどの大学も外国語2つ、専門科目2つ以上、小論文が課せられていました。
とくに外国語2つが恐ろしくむずかしい。1年生のうちから相当勉強していないと無理だ、とすぐに断念しました。外国語2つの壁が高かったと記憶しています。学者になった同級生はみな、高校生のころからよく勉強していたのでしょう。
大学院の定員が増えているので、文科系で学者になれる院生の比率は大きく下がっています。現在の大学院は学者を養成するのは目的の1つにすぎず、他にも目的があるわけです。もちろん目的は個々の院生が発見するものでしょうが。
大学院入学の壁が恐ろしく低くなると、目的が重要になります。本書『研究計画書の考え方』は、大学院重点化開始から7年後、社会人院生も増え、大学院大衆化のさなかに刊行されました。
本書には文科省による大学院拡充の目的が、大学審議会答申を引用してこう記されています。
1. 学術研究の高度化と優れた研究者の育成機能の強化
2. 高度専門職業人の育成機能、社会人の再教育機能の強化
3. 教育研究を通じた国際貢献が特に求められており、いずれの面からも大学院の更なる整備充実が必要である。(答申第1章3節)
(19ページ)
たしかに「1. 研究者の育成」は一部にすぎないことがわかります。著者、妹尾堅一郎さんの慧眼は、このような大学院大衆化のなかで「研究計画書」の重要性に着目した点にあります。
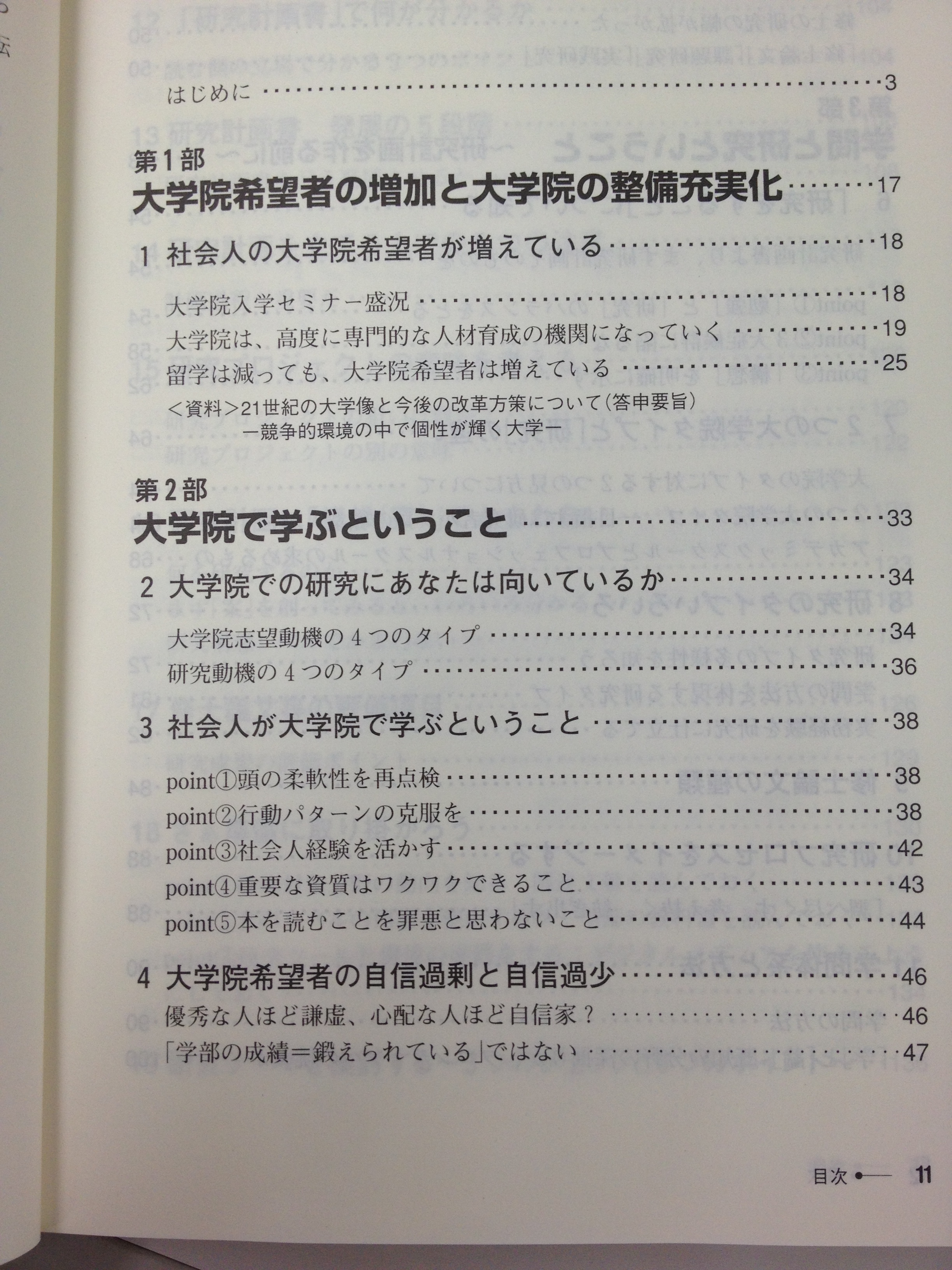 前半部の目次。「ハウツー」ではなく、大学院で何をするのかに重点が置かれています。
前半部の目次。「ハウツー」ではなく、大学院で何をするのかに重点が置かれています。[画像を拡大する]
「研究計画書」は入試問題ではありません。応募する際に必要な提出文書です。これは数十年前も大衆化した現在も変わりません。しかし、本書が出版されるまでは、当の大学院生以外、「研究計画書」とは何か、だれもよくわからなかったのです。
(本書の特色は)「書き方のハウツー」よりも「研究についての考え方」を重視した点である。書き方のイロハなんて、所詮は小手先のハウツーに過ぎないのである。大切なのは、「研究そのものについての考え方」なのだ。これがしっかりしていない計画書は、いくら文書の書き方を工夫しても、底の浅いものになってしまう。化粧でカバーできる部分はたかが知れている。
(3〜4ページ)