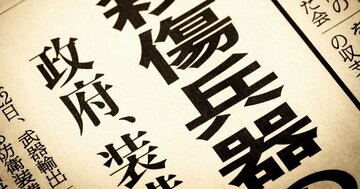写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
ウクライナに軍事侵攻中のロシアでは、大量のドローンやミサイルを調達し戦場に投入しているが、そうした兵器の中に、日本企業の部品が組み込まれているという。自社商品が、流れ流れて独裁国家の武器調達や人権侵害に一役買ってしまうケースは少なくない。「勝手に使っただけ」「ウチは知らない」の言い訳はもはや通らない時代に、企業はどう対応すべきなのか。※本稿は、羽生田慶介『ビジネスと地政学・経済安全保障』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。
ロシア軍のウクライナ侵略に
日本製の民生品が使われている
ある日突然、身に覚えのない「罪」で国際的な非難の声にさらされる日本企業が増えている。自社製品に強制労働によって生産された原材料・部品が含まれていたことや、自社製品が人権侵害を助長する機器や武器の部品として使われていたことを報道で知るケースだ。企業にとっては、まさに寝耳に水、青天の霹靂だ。しかし、今や「知らなかった」では済まされない時代となった。
調達面での人権侵害の排除は、企業にとって喫緊の課題だ。米国のウイグル強制労働防止法(UFLPA)のように、強制労働などの関与を理由とした輸入差し止めの事例がすでに多数出ている。これに対する日本企業の取り組みも進みつつある。これに加えて、日本企業が対応を迫られているのが、サプライチェーンの「川下」、つまり、販売後の製品の行方の管理だ。特に、ある製品の用途が問題となった際に、自社製品がその部品として使われていたために対応が必要となるケースが増えている。