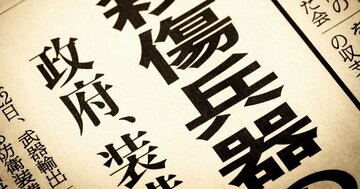しかし、ひとたび自社製品が戦争に関与し、人権侵害を助長していると指摘されれば、レピュテーション(編集部注/人々が購買や就職、取引などを行う際に意味を持つ、企業への評価)の低下を避けるのは難しい。国際社会で非難を浴び、不買運動につながったケースや、訴訟となったケースもある。指摘を受けた際の対応の拙さが、さらなるレピュテーションの低下を招いた事例もある。「売った後のことは知りません」はもはや通用しないのだ。
第三国を経由した
ロシアへの輸出禁止
こうした状況を受け、主要国が規制強化に動いている。ロシアで軍事転用されている製品の迂回輸出の管理強化は、G7諸国が協調して進めている。2024年4月のG7外相会合では、G7諸国による制裁や輸出制限を回避・迂回しようとするいかなる試みにも対抗し、兵器生産に必要な装置などをロシアが入手するのを支援する第三国の企業や個人に制裁を科す方針が確認された。
日本では、外為法や輸出貿易管理令に基づき、ロシアを仕向け地とする物資の輸出が禁じられている。これには、指定団体との直接取引だけでなく、間接取引も含まれている。経済産業省は、ロシア以外の国・地域に向けて輸出する場合であっても、最終仕向け国、最終用途や最終需要者などをよく確認するよう企業に求めている。
また、ロシア以外の国・地域を経由・通過してロシアに輸出する行為(迂回輸出)は輸出禁止措置違反となることに注意を促している。さらに、制裁迂回に関与した疑いのある団体を指定し、その団体向けの輸出を禁止している。これまでに、中国やインド、カザフスタンなどの団体が指定されている。
特に注意を要する品目もリスト化されている(「共通高優先度品目リスト」)。これは、日本と主要国が協力し、ウクライナで見つかったロシア軍兵器に使用されていた部品などを調査・特定した結果をまとめたものだ。2024年2月の改訂版には、「集積回路等の電子部品」「通信用途に使用される機器」「数値制御式(編集部注/コンピューターなどによって自動化すること)工作機械関連品目」などの50品目が掲載されている。米国では、同リスト掲載品目を当局の許可なしにロシアに輸出した企業が330万ドルの罰金を科せられた例がある。