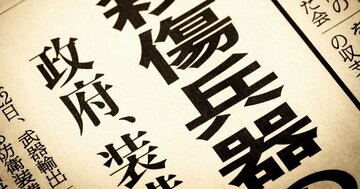ロシアでは、同国内で事業を継続している企業が、直接的・間接的にウクライナ侵攻を支援しているとして国際的な非難を浴びた。ウクライナ政府は、ロシアで事業を続けることは、納税などを通じてロシアのウクライナ侵攻を支えているとして、該当する外国企業を「戦争支援企業」として特定し、ロシアでの事業の停止や撤退を求めた。同リストは、客観性に問題があるなどと批判を受け、2024年3月に廃止されたが、約50社が掲載され、日本企業も含まれていた。
中国・新疆ウイグル自治区での人権侵害が国際的に批判される中で、同自治区での生産を続けていた独フォルクスワーゲンは、2024年11月に同自治区にある中国企業との合弁工場の売却を発表した。同社は、売却は経済的理由によるものだと説明しているが、株主などから同自治区からの撤退を求める圧力が高まっていた。
 『ビジネスと地政学・経済安全保障』(日経BP)
『ビジネスと地政学・経済安全保障』(日経BP)羽生田慶介 著
日本の大手商社の子会社は、イスラエルの軍事企業との協業に関する覚書(MOU)を結んでいたが、これはイスラエルのガザにおける人権侵害への加担だとして日本の学生団体などから批判されていた。同社は、国際司法裁判所(ICJ)がイスラエルに対し、ジェノサイド(集団虐殺)行為の防止を命じたことや日本政府がそれを支持したことを受け、2024年2月に同覚書を終了した。
ミャンマーでは、国軍系企業との協業や現地事業の継続が、配当や納税などを通じて軍事政権による人権侵害に加担しているとして非難の的になった。ロシアでもミャンマーでも、撤退には当局の承認や多額の損失の発生など困難が伴うが、人権リスクやレピュテーションリスクの回避のため、撤退に踏み切った日本企業は少なくない。こうしたリスクも、地政学・経済安保リスクの1つとして捉え、対応することが重要だ。