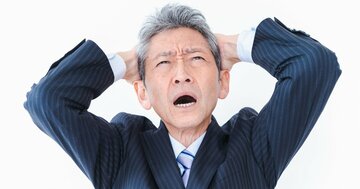借金なんてなかったのに…実は“連帯保証人”だった父の死が招いた悲劇
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる!【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
■知らないと危険!相続放棄に関わる3つの重要ルール
亡くなった被相続人が借金を抱えていた場合、さまざまな法律が関係してきます。
ここでは知らないと大きな問題になりかねない3つのルールを説明します。
①財産を処分すると自動的に「単純承認」になる
民法のルールでは、「亡くなった被相続人の財産の処分」に該当する行為をすると、自動的に故人の財産と債務をすべて引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされ、3カ月以内であっても相続放棄ができなくなります。
たとえば、亡くなった被相続人が生前に加入していた医療保険から入院給付金が支給され、それを相続発生後に相続人が受けとってしまうと、被相続人の借金を引き継がざるを得なくなるのです。
◎財産の処分に該当するケース
✓ 相続財産の売却・贈与・相続財産に属する家屋のとり壊し、高価な美術品の損壊
✓ 経済的価値のあるものの形見分け
✓ 株主総会において相続人が議決権行使をする
✓ 亡くなった被相続人所有の貸家の賃料振込先を自己名義の口座へ変更
✓ 準確定申告をして還付金を受けとる(納税するケースは解釈が分かれる)
✓ 生存中の給付金(入院給付金・通院給付金・傷害医療費用保険金)を受けとる
●財産の処分に該当しないケース
✓ 相続人固有の財産(死亡保険金含む)で被相続人の借金などを弁済
✓ 相続財産からの葬儀費用・仏壇・墓石の購入費用の支払い
(不相当に高額なケースを除く)
✓ 経済的価値のないものの形見分け
②借金を引き継ぐ人を遺産分割協議で決められない
次に押さえておきたいのが、「亡くなった被相続人の借金は法定相続分で分けるのが原則」というルールです。
たとえば、相続人が兄弟2人なら法定相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、相続放棄をしない限りは、被相続人の借金を兄弟で半分ずつ引き継ぐことになります。より正確にいうと、相続人で借金の負担割合を決めることは可能なのですが、それを銀行などの債権者には主張できないのです。
つまり、銀行などの債権者からは、法定相続分で請求されてしまうわけです。
このルールは遺産分割協議の内容に左右されず、たとえ「A銀行の借金1000万円は長男が相続する」と遺産分割協議書に書かれていても、A銀行は次男にも借金の返済を迫ります。このように法定相続分で借金が引き継がれることを「重畳的債務引受」といいます。
これを特定の人だけが借金を負う形にしたければ、債権者と交渉して、「免責的債務引受」を了承してもらわなくてはいけません。故人が銀行からお金を借りていたのであれば、その銀行に「財産をこういう分け方にしたいので、借金はこのようにさせてください」といった申し出をするのです。
免責的債務引受に切り替えられるかは交渉次第になるため、借金のとり扱いを債権者にしっかり確認しておきましょう。
③見えない債務に注意
明らかにプラスの財産(預金など)のほうがマイナスの財産(借金など)よりも多ければ、相続放棄をする必要はないと思うでしょう。
ところが、そうした場合でも油断は禁物なのです。「お父さんには借金なんてない」と思い込んで単純承認をしたら、あとから多額の借金の返済を求められることもあるからです。
とくに恐いのが、被相続人が第三者の借金の連帯保証人になっていた場合です。この場合、連帯保証人になっていたことを本人が言わないと、家族は知りようがありません。
たとえ知らなくても、法律上は相続人が連帯保証人の立場を引き継ぐことになり、場合によっては知らない人の借金を連帯保証人として肩代わりしなくてはなりません。
■実際の事例から学ぶリスク
私が実際に遭遇した事例を簡単に紹介しましょう。ある会社経営者が亡くなったとき、自分の会社の借金2億円の連帯保証人になっていました。相続人は長男・長女の2人で、長男が会社の経営を引き継いだのですが、業績が悪化して借金を返済できなくなりました。
その後、会社を継いだ長男はもちろん、長女も借金の返済を迫られてしまいました。
前述の「重畳的債務引受」のルールから、連帯保証した債務が法定相続分で引き継がれていたからです。
このような連帯保証人としての債務も、相続放棄をすれば免れることができます。しかし、3カ月の期限を過ぎるともはやどうしようもなくなるので、その前に弁護士などに相談し、致命的な事態に陥らないようにしてください。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)