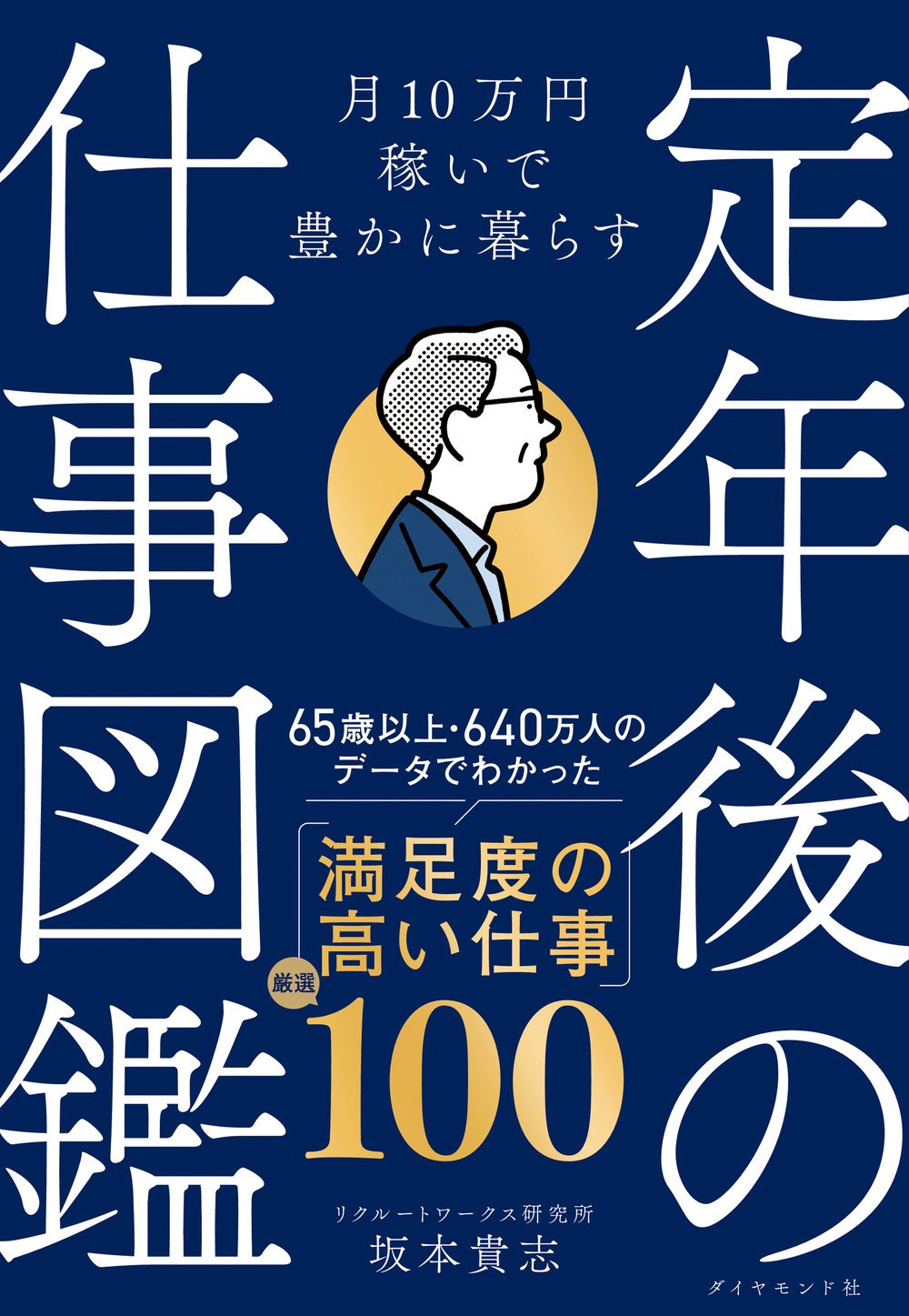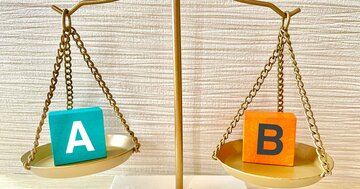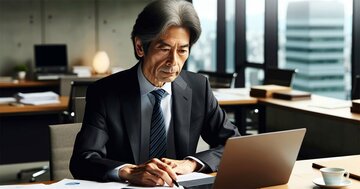「60歳以降の仕事人生にも、ガイドが必要だ」――そう語るのは、リクルートワークス研究所の坂本貴志さん。高齢期の就労・賃金を専門とする坂本さんが、65歳以上・640万人のデータを分析し、まとめた書籍が『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』です。
定年退職=引退だった時代は終わり、いまや「定年後の仕事探し」を自分自身で行う時代がやってきました。本書では、実際に働いている人のデータを参照しながら、19カテゴリ、100種類の仕事を紹介。現役時代とは全く違う仕事選びのコツについても解説しています。この連載では、本書より一部を抜粋・編集して掲載します。今回は、実際に定年後の仕事をしている方のインタビューを掲載します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
年金支給額は平均的な世帯で「月20万円超」
老後に漠然と不安を抱いている人は多いが、意外と毎月のフロー、つまり「収入」と「支出」がいくらになるのかを把握している人は少ない。
本書では1人あたり「月10万円を無理なく稼ぐ」ことを定年後の仕事のベンチマークとして用いている。夫婦ともに働く場合であれば、世帯で月20万円程度稼ぐというところをひとつの目標としたい。
65歳以降のフロー=定期収入の中心は「公的年金」である。年金の支給額については、厚生労働省がモデル世帯の厚生年金保険新規裁定者の支給月額を毎年公表している。新規裁定者というのは新しく年金をもらい始める人のことで、モデル世帯とは妻が専業主婦、夫は会社員で継続的に厚生年金保険を支払っている家庭を指す。
このモデル世帯をみると、2024年の年金支給額は約23万円。年金は物価に応じて変動するので、足元の物価上昇に伴って名目額は増えているが、実質年金支給額は過去から抑制されている。最近の女性の労働参加の拡大や資産価格の高騰などで年金財政の健全性自体は保たれているものの、2010年代から年金支給の実質額は減少傾向にあり、今後も長期的には減っていくと見られる。
正社員は自営業より多い
公的年金の支給額は、
・自身が現役時代にどのような働き方をしていたか(厚生年金保険の対象となる会社員か、国民年金のみの自営業か)
・自身の現役時代の収入がいくらだったか(厚生年金の平均報酬月額がいくらか)
・配偶者が雇用されて働いていたか。またその収入はどの程度だったかによって支給額の水準が大きく変わる。
正社員中心で働いていた場合と自営業中心で働いていた場合の年金受給額を比較すると、正社員中心で働いていた男性では1人あたり月20万円ほどもらえる割合が最も高くなっている。一方、自営業中心で働いている場合は、約半数の人の年金受給額が月4~8万円程度という水準だ。
自営業は元々の制度の建て付けとして、農業等を典型として長く働けることが前提となっている。そのため、定年制のあるサラリーマンと違い、現役時代の年金保険料が少ない代わりに、定年後のフローが保証されるような仕組みになっていないのが現状である。
男女別に見ると、女性も雇用されて働いていた方が年金の受け取り額が多くなるが、正社員中心で働いていた場合でも月10万円程度で、男性より年金額が低くなっている。女性の場合は標準報酬月額がもともと少なかったり、キャリアの途中で退職した時期や雇用形態が変わった時期があることなどが年金額が少ない原因となっている。もっとも、女性の社会進出が進んでいる現役世代においては、女性の金額がより男性に近づくと考えられる。