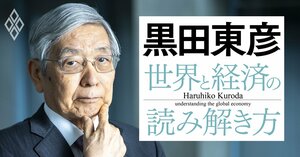前職での成果を再現できることを
どれだけ明確に伝えられるか
転職は自分を「商品」とし、その価値を売り込むための「棚卸し」ができるかが、まず一歩。それができたら、次に重要なのは「成果の再現性」をいかに伝えるかです。
採用担当者が知りたいのは過去の成果ではなく、その成果が転職後も再現できるかどうかです。Aさんも前職での実績や成果は伝えていましたが、成果を出せた背景や条件、要因などを十分に説明できていませんでした。これでは採用担当者も「前職では環境が良かったから達成できただけでは?」などと疑問を抱いてしまいます。
一方のBさんは、前職の環境や課題はもちろん、そこからどんなアクションをして成果につなげたか一連の流れをしっかり説明していました。採用担当者はBさんが成果を出すまでのプロセスを理解できたことで、転職後の活躍も期待できると納得したのです。
Aさんの説明は過去の実績という「結果」にとどまる一方、Bさんは「プロセス」を丁寧に伝えていました。この違いが面接評価を大きく分けます。業界や会社が変わっても成果を生み出す力が備わっていること、すなわち再現性の高さを証明するのが、転職の面接をクリアする最低条件なのです。
転職の成否は動機で決まる
「逃避型」と「志向型」の違いとは
さらに言えば、転職で失敗する人と成功する人の違いは、転職活動を始めるずっと前から発生しています。それは、転職の動機が「逃避型」か「志向型」かの違いです。
AさんはSNSなどで他人の成功例を見て、「自分も年収を上げたい」「取り残されたくない」といった外的要因によって転職を考え始めました。加えて実は、「今の環境への不満や不安から逃れたい」という逃避型の思考のクセがありました。
一方でBさんは、培った経験をどのように積み重ねていくか、次の職場でどのように生かすかイメージが明確で、キャリアビジョンを達成する志向型でした。ここに大きな差があったのです。
両者の格差は、動機の違いに行き着きました。では、なぜ動機にこれほど差が出たのでしょうか。それは人生の「目的意識」の違いに行きつきます。
Aさんは「年収を上げたい」「生活水準を高めたい」という目標は持っていましたが、人生の目的意識は曖昧でした。対してBさんは、人生の目的を達成するための手段として転職を位置づけていました。
軸があり、一貫性を持った行動ができるか――。転職は、量より質で勝負しましょう。周囲と比較して焦るのではなく、自らの人生設計に沿った転職こそ、長期的なキャリアアップを実現する最良の道となるでしょう。